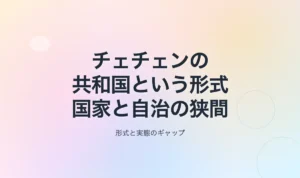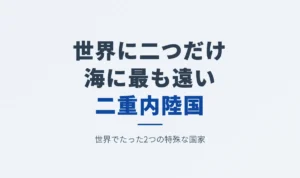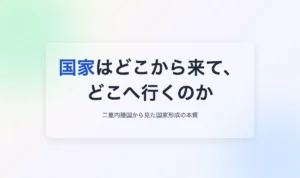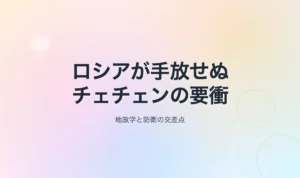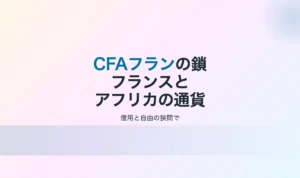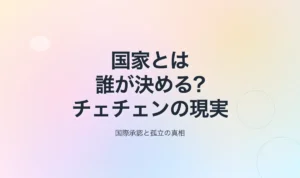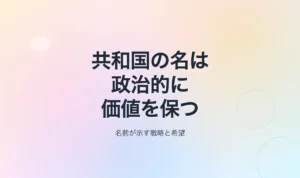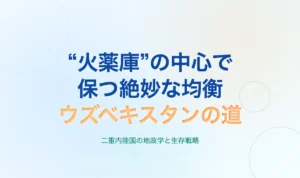第一次チェチェン紛争:勝利のように見えた瞬間
1991年、ソビエト連邦の崩壊とともに、チェチェンは独立を宣言した。指導者ジョハル・ドゥダエフのもとで独立国家としての構築を試み、ロシアの干渉を排除しようとした。ロシアは当初、内政の混乱と経済的危機もあり、明確な対応を取れずにいたが、1994年になって軍事介入を開始する。
これが第一次チェチェン紛争の始まりである。ロシア軍はグロズヌイを中心に総攻撃を加え、激しい市街戦が展開された。しかし、ゲリラ戦と地元住民の抵抗が予想以上に激しく、ロシア軍は多くの死傷者を出しながら苦戦を強いられた。1996年、ロシアはチェチェンとの停戦協定(ハサヴユルト協定)に応じ、軍を撤退させる。
この戦闘の終結は、チェチェンにとって一時的な勝利を意味した。ロシア軍を撤退させたことで、事実上の独立状態が確立されたといえる。しかし、それは国家としての完成を意味するものではなかった。
戦後の混乱:国家機能の不在
ロシア軍の撤退後、チェチェンは名目上の独立国家として機能するはずだったが、その実態は混沌と無秩序の連続であった。統治の経験を持つ官僚機構は存在せず、政治的指導者も軍閥出身者が多かったため、安定的な国家運営が困難だった。
加えて、紛争でインフラや行政機構が壊滅状態にあったことも影響した。税収は乏しく、治安も確保されず、実質的な無政府状態に陥った。組織犯罪や武装勢力が権力を握り、住民の生活は不安定を極めた。
この空白を埋めるようにして、外部からイスラム過激派が流入し、チェチェン国内に影響力を強めていく。こうした過激派は、単なる国家建設を超えて「カフカス・イスラム国家」構想を掲げ、近隣のダゲスタンなどにも武装侵攻を行うようになる。
国際社会の承認なき独立
チェチェンが直面したもう一つの大きな問題は、国際社会からの承認を得られなかったことである。ロシアはこの紛争を「内政問題」として扱い、他国の介入や承認を拒絶した。一方で、チェチェンに対して国交を樹立した国家は存在せず、国連にも加盟できなかった。
これにより、チェチェンは国家としての象徴(国旗や通貨)は持ちながらも、外交的には“存在しない国”として扱われ続けた。国際的な支援も乏しく、孤立した中での再建はますます困難を極めた。
国際社会にとって、ロシアという大国との関係を損ねてまでチェチェンの独立を支持する政治的メリットは乏しかった。これが、チェチェンの「独立の限界」を決定づける要因の一つとなった。
第二次チェチェン紛争への導火線
内部の無秩序、過激派の拡大、そして周辺地域への武装勢力の波及——これらが重なり、1999年、ロシアは再びチェチェンへの軍事介入を決断する。これが第二次チェチェン紛争の始まりであり、以降のチェチェンはロシアの強固な管理下に置かれることになる。
第一次で勝利を得たかに見えたチェチェンだったが、紛争での勝利は国家としての成立を保証するものではなかった。
国際的承認の欠如、政治的未熟さ、経済的自立の不在、治安の不安定化。これらの条件が揃ったことで、チェチェンは独立を維持するための地盤を築くことができなかった。
チェチェンの経験は、「戦って勝てば国家になれる」という楽観を打ち砕く冷徹な教訓でもある。国家とは戦争の勝利ではなく、その後の統治と持続性によって初めて成り立つものであるという現実を、私たちはこの歴史から学ぶ必要がある。