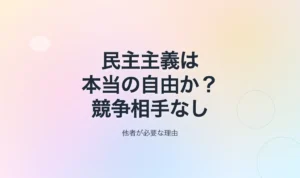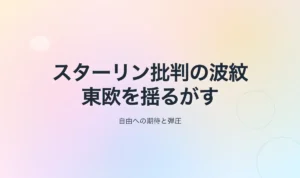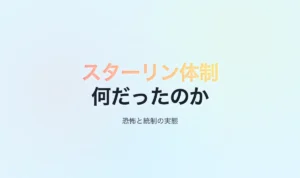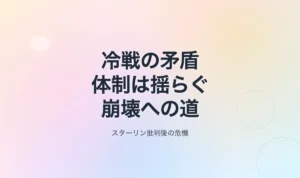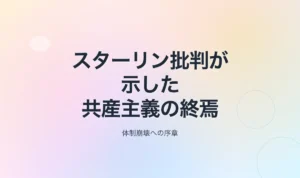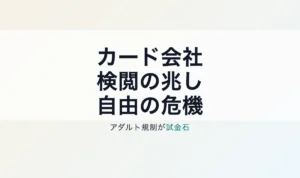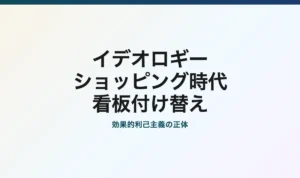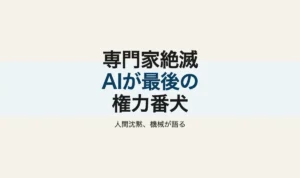1953年、スターリンの死去をもってソビエト連邦の「絶対的恐怖政治」の時代は終わりを迎えた。その死は国家の頂点に巨大な空白を生み出し、党内での後継者争いが激化する。ここで徐々に台頭していったのが、ニキータ・フルシチョフである。彼はスターリンの側近の一人でありながら、やがてその遺産を否定するという歴史的転換を遂げた。
本稿では、フルシチョフの権力掌握の過程と、1956年に行われた「スターリン批判」がもたらした意味と影響について詳述する。
権力掌握の舞台裏
スターリン死後、ソ連の指導部は「集団指導体制」を標榜してスタートしたが、実際には熾烈な権力闘争が水面下で繰り広げられていた。表向きのナンバーワンは首相ゲオルギー・マレンコフ、警察権力を握るベリヤ、そして党の要職にいたフルシチョフの三者が中心であった。
最初に動いたのはフルシチョフと他の幹部たちで、1953年6月、ベリヤを「反革命的陰謀者」として逮捕・処刑に追い込んだ。この時点で、国家の恐怖装置であった秘密警察(MVD)はフルシチョフ陣営の手から離れた。次に1955年、マレンコフが首相を辞任し、フルシチョフの影響力はますます強まる。1956年にはソ連共産党第一書記として、事実上の最高権力者の地位を手中に収めていた。
しかし、フルシチョフが単なる権力者ではなく、歴史に名を残す存在となったのは、その後の一手、すなわちスターリン批判である。
「スターリンの個人崇拝とその帰結」:秘密演説の衝撃
1956年2月25日、ソ連共産党第20回大会の最終日、フルシチョフは「スターリンの個人崇拝とその帰結について」という題名の演説を秘密裏に行った。これは党の限られたメンバーのみに向けた非公開セッションであり、外部には報道されなかった。
内容は驚くべきものであった。スターリンが行った数々の粛清や、大粛清における冤罪、違法な弾圧手法、レーニンの遺言におけるスターリン批判などが次々と明かされ、「個人崇拝」という言葉でスターリンの独裁とその暴走を糾弾した。とくに1930年代のショウ裁判や粛清については、「無実の同志たちが恐怖の中で命を奪われた」として、体制そのものの誤りが暴かれた。
この演説の核心は、スターリンの個人的責任を追及しつつ、ソ連共産党そのものの正統性は保とうとする巧妙なバランスにあった。つまり、「スターリンだけが過ちを犯した」という構図を作り上げることで、体制への信頼をつなぎ止めようとしたのである。
国内外への波紋
この秘密演説は、当初は党内資料として管理されていたが、各地の支部で回覧されるうちに情報が漏洩。最終的にはポーランドやハンガリー、さらにイスラエル共産党員を通じてアメリカCIAの手に渡り、1956年6月、『ニューヨーク・タイムズ』が全文を掲載したことで全世界に知れ渡った。
国内では、政治犯の釈放や検閲の緩和、一定の言論自由が認められるなど、「雪解け」と呼ばれる相対的自由化が始まった。しかし同時に、スターリンを信じていた官僚や軍部、そして高齢の共産党員たちの間には強い動揺が走る。一方で、東欧諸国ではこの演説が爆発的な反応を引き起こし、同年のハンガリー動乱へとつながっていく。
国際共産主義運動も大きく揺らいだ。西側諸国の共産党は信念の根幹を揺さぶられ、特に知識人層は次々と党を離脱した。さらに、スターリンを肯定していた毛沢東との関係も悪化し、のちの中ソ対立の伏線がここに生まれた。
フルシチョフの意図とその限界
フルシチョフのスターリン批判には、明確な政治的意図が存在した。それは、自身の権力を正当化し、スターリンとは異なる「人間的社会主義」への道を模索することだった。彼は以後、農業改革や教育の拡充、軍縮政策を打ち出し、部分的には「開かれた社会」を志向した。
しかし、その改革は場当たり的で効果に乏しく、党内の保守派や軍部からの支持を失っていく。1962年のキューバ危機での対応も「弱腰」と見なされ、最終的に1964年、フルシチョフは平和的に解任され、ブレジネフが後継者となった。
スターリン批判は、共産主義体制の矛盾を一部あぶり出したが、フルシチョフ自身もその体制の産物であり、同時に限界を体現する存在でもあった。その演説は、共産主義の絶対性に対する最初の公式な疑義であり、ソ連体制の“ほころび”を象徴する出来事であった。