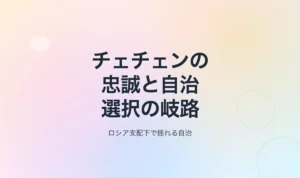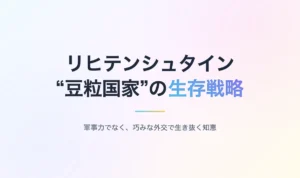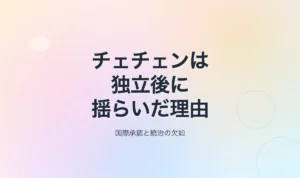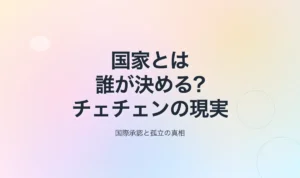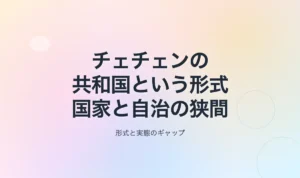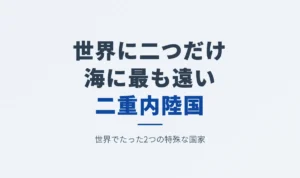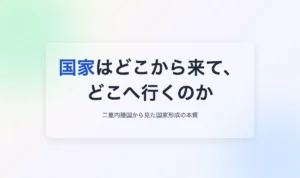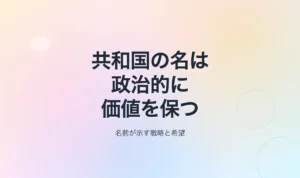「ドイモイ」とは何か?──刷新の合言葉
1986年、ベトナム共産党は国家の方向性を大きく転換する経済改革を打ち出した。
その名を「ドイモイ(Đổi Mới)」――ベトナム語で「刷新」「改革」を意味する言葉だ。
それは単なる政策ではなかった。国家の根幹を変える、大胆で冷静な“自己改造”の始まりだった。
ドイモイの前夜──破綻しかけた社会主義国家
1975年、ベトナムはアメリカとの長い戦争を勝ち抜き、南北統一を果たした。
だが、それは新しい地獄の始まりでもあった。
統一国家として再出発したベトナムは、ソ連型の計画経済を導入したが、待っていたのは物資不足、飢餓、インフレ、黒市の蔓延だった。加えてカンボジア侵攻と中国との武力衝突(中越戦争)により国際的に孤立。
西側からの制裁、ソ連の支援の限界、国内の疲弊。あらゆる面で国家は袋小路に追い込まれていた。
このままでは「戦争には勝ったが、平和を維持できない国」になりかねない。
そこでベトナムは現実を直視する。
イデオロギーを貫くのではなく、生き残るために変わる――それがドイモイ政策だった。
なぜドイモイは可能だったのか?──現実主義への切り替え
当時のベトナムには「変わるだけの理由」と「変われるだけの素地」が揃っていた。
まず、国家としての“統一”はすでに済んでいた。
戦争の勝者である北ベトナム主導の体制は強固で、共産党の支配は揺るがなかった。
だからこそ、政治体制を維持したまま、経済政策だけを大きく切り替えることが可能だった。
また、隣国・中国の「改革開放政策」がすでに始まっていたことも大きい。
あちらは社会主義の看板を掲げながら資本主義的な政策を取り込み、一定の成果を上げていた。
ベトナムはそれを冷静に観察し、「我々もやれる」と踏み切ったのである。
ドイモイ政策の内容──社会主義を脱がずに資本主義を取り込む
ドイモイ政策の核心は、政治の支配構造を維持したまま、経済の中身を市場経済に変えることだった。
農業では、国による収穫の一括管理をやめ、農民に土地の使用権と販売の自由を与えた。
これにより農産物の流通が劇的に改善され、飢餓は解消に向かった。
工業や商業では、民間企業の設立を許可し、外国からの直接投資も解禁。
外貨獲得のための輸出戦略も取られ、世界市場との接続が始まった。
こうしてベトナム経済は社会主義の殻を破り、現実的な発展路線へと向かった。
その成果──「社会主義市場経済国家」の実現
ドイモイ政策の成果は数字が語っている。
一人あたりGDPは1986年当時の250ドル前後から、2023年には4,300ドル超に。
輸出は同期間に数十億ドルから3,700億ドル以上へと拡大し、今ではサムスンやインテルなど世界的企業の製造拠点となっている。
貧困率も1990年には60%近くあったが、今では数%以下にまで改善。
識字率は98%を超え、工業化・都市化も着実に進んだ。
人口も2023年には1億人を突破し、若くて活力ある労働力を維持している。
ドイモイの意義──イデオロギーより生存、現実主義の勝利
ドイモイ政策の真の意義は、「国家は変われる」ということを証明した点にある。
共産党政権を維持しながら、経済的には完全に資本主義に近い構造を導入し、
それを混乱なく軟着陸させたのは世界的にも稀な成功例だ。
中国の「改革開放」と並ぶ“社会主義国家の現実主義化”のモデルとして、
ベトナムのドイモイは今も国のアイデンティティであり、誇りとなっている。
まとめ:ドイモイは今も続く「国家の自己改造」
ドイモイ政策は、1986年の一点突破の改革ではなく、今も続く国家運営の基本姿勢である。
体制の名前として、政策のブランドとして、そして何より「生き残り方針」として。
ベトナムは今もこのドイモイの延長線上で歩き続けている。
「理想ではなく、生存のために変わる」。
このリアリズムこそが、ベトナムという国の強さの根本にあるのかもしれない。