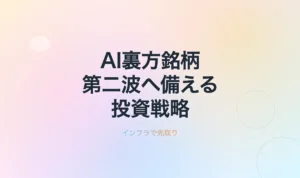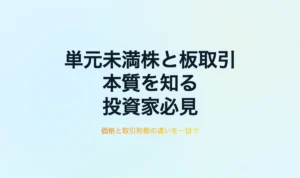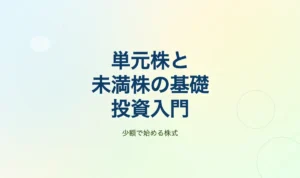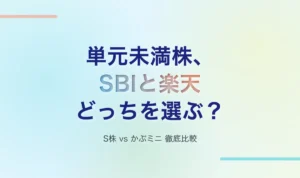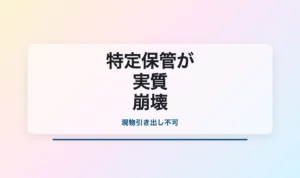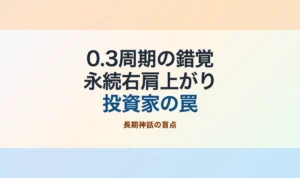米国株投資が日本の個人投資家の間で一般化してきた中で、証券会社の選択はますます重要になってきている。特に楽天証券とSBI証券は、ネット証券として高いシェアを誇り、機能・コスト・サービス面でしのぎを削っている。
本稿では、米国株投資という観点からこの2社を比較し、それぞれの長所と短所、どんな投資家に向いているのかを掘り下げて解説する。
取引手数料・為替手数料の違い
米国株投資を行う際にまず重要となるのが、取引手数料と為替手数料の構造である。2024年時点では、両社とも米国株の売買に関して次のような条件を提供している。
- 取引手数料:楽天証券・SBI証券ともに、通常は約定代金の0.495%(税込)。上限は22ドル。NISA口座での取引は手数料無料。
- 為替手数料:2023年以降、両社ともに為替手数料は無料とされた。ただし、提示される為替レートには実質的なスプレッド(上乗せ)が含まれている場合がある。
為替手数料がゼロとはいえ、実際のレートが市場実勢より0.1~0.2円程度不利に設定されているケースもあるため、コスト意識の高い投資家は為替レートの実測値を確認することが望ましい。
また、頻繁に売買する場合、0.495%の手数料は意外と重くのしかかる。特に少額投資では、売買往復で1%近くのコストがかかるため、長期投資前提でまとめ買いを行うスタイルが有利となる。
取扱銘柄数と投資情報の充実度
米国株の取扱銘柄数はSBI証券がやや優勢である。2024年時点で、SBI証券は約5,100銘柄、楽天証券は約4,700銘柄を取り扱っている。
また、SBI証券はNASDAQやNYSEの他に、OTC銘柄(店頭取引株式)も一部取り扱っており、マイナーな中小型株やバリュー株を狙う投資家にとっては選択肢が広い。
一方、楽天証券は初心者向けの情報提供に力を入れており、企業情報やランキング、チャート機能の視認性が高い。楽天証券の「トウシル」などのコンテンツも、情報収集が苦手な投資初心者にとって有用なサポートとなる。
したがって、情報を自力で掘る投資家にはSBI証券、ガイド付きで進めたい投資家には楽天証券が向いている。
単元未満株とNISA対応の違い
米国株は基本的に1株単位での売買が可能であり、いわゆる「単元株制度」が存在しない。そのため、単元未満株に関して両社に大きな違いはないように見えるが、細かい点で差がある。
楽天証券では、「かぶミニ」などの国内株式に関するサービスの利便性が米株ユーザーにも影響を与えている。たとえば、楽天キャッシュによる入金・購入が可能であったり、楽天ポイントを投資に利用できたりするなど、楽天経済圏との連携が強みとなっている。
一方、SBI証券は住信SBIネット銀行やTポイント・Vポイントとの連携に強みがあり、グループ全体として資金移動や資産管理がしやすい設計になっている。
また、NISA(少額投資非課税制度)への対応も両社ともに行っており、新NISA制度下では米国株の売買手数料が無料である点は共通している。NISA枠内での米株投資は、楽天でもSBIでも条件面で大きな差はない。
ユーザー体験・ポイント還元・システム面
ユーザー体験(UX)という観点では、楽天証券はアプリやブラウザの使いやすさにおいて一歩リードしている。取引画面の設計、チャートの操作性、注文のしやすさなど、視覚的・操作的な快適さを求めるなら楽天証券が快適に感じられるだろう。
対して、SBI証券は機能面がやや複雑だが、高度な注文方法やスクリーニング機能、レポートの詳細性など「深く使う人」には適している。
また、ポイント還元制度についても注目に値する。楽天証券では楽天ポイントを使った投資や、取引額に応じたポイント付与(最大1%)が魅力。一方、SBI証券ではTポイント・Vポイントの還元があり、こちらも取引手数料に応じて付与される。
楽天経済圏に深く関与しているユーザーなら楽天証券、SBIグループをメインバンクにしているならSBI証券という住み分けが自然な流れである。
総合評価:どちらが自分に合っているか?
楽天証券とSBI証券の米国株サービスは、基本的なスペックではほぼ拮抗している。しかし、ユーザーの投資スタイルや経済圏への親和性によって、選ぶべき証券会社は変わってくる。
以下に、簡単なまとめを示す:
| 観点 | 楽天証券 | SBI証券 |
|---|---|---|
| 取扱銘柄数 | やや少ない | より多い |
| 手数料 | 同等(0.495%上限22ドル) | 同等 |
| 為替手数料 | 無料(実質スプレッドあり) | 同左 |
| NISA対応 | 対応(無料) | 対応(無料) |
| アプリ・UX | シンプルで分かりやすい | 多機能・やや複雑 |
| ポイント制度 | 楽天ポイント連携 | Tポイント/Vポイント連携 |
どちらが優れているというより、「どちらが自分の投資スタイルに合っているか」が重要である。少額からシンプルに始めたいなら楽天証券、取扱銘柄数や機能性を重視するならSBI証券が向いている。
自分の資金規模、投資頻度、情報収集スタイルをもとに、どちらが長期的なパートナーになりうるかを冷静に見極めよう。