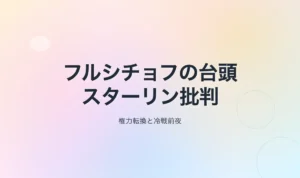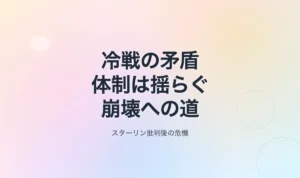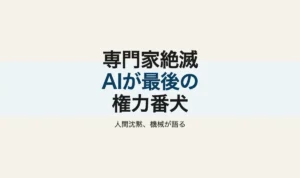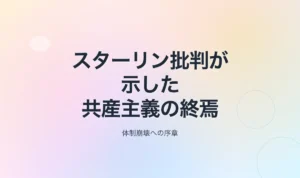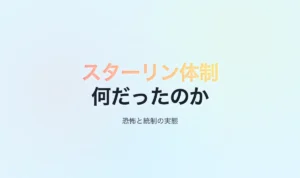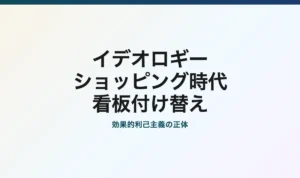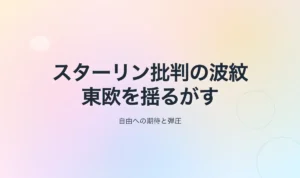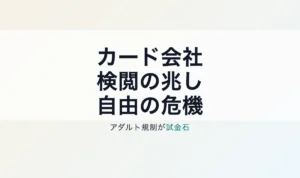21世紀初頭、民主主義は「歴史の勝者」として世界の政治舞台を制したかのように見えた。冷戦が終結し、ソビエト連邦が崩壊した1991年以降、リベラル・デモクラシーは唯一の正統な体制とみなされ、西側諸国はその価値を世界中に広めることに躍起になった。しかしここで、一つの仮説を提示したい──民主主義が本当に民主主義であり続けるには、対抗する“他者”が必要なのではないか?
この問いは、民主主義そのものに対する懐疑ではない。むしろ、民主主義が理念通りに機能するための「外部的条件」を探る試みである。
冷戦という緊張装置:理想が現実を律していた時代
第二次世界大戦後から1991年のソ連崩壊まで、世界は資本主義・民主主義陣営と、社会主義・共産主義陣営の二大ブロックに分かれていた。これは単なる軍事・経済の対立ではなく、「どちらの社会がより人間的で、より理想的か」という価値の競争でもあった。
この競争は、民主主義国家にある種の健全な緊張をもたらした。たとえば、西ヨーロッパ諸国が福祉国家を発展させ、アメリカが公民権運動を推進した背景には、「資本主義は冷酷だ」「自由主義は少数者を抑圧している」という共産主義側の批判への対抗意識があった。
共産主義の存在が、自由主義の側に“自らの正義を証明しようとする努力”を促していたのだ。
一極化の罠:競争相手を失った「正義」の鈍化
ところが、ソ連が崩壊し、共産主義が現実的な対抗モデルとして瓦解したことで、リベラル・デモクラシーは世界の「唯一の正義」と化した。「民主主義に代わるものは存在しない」という空気が支配し、制度そのものが批判や問い直しから解放されてしまった。
ここで始まったのは、「理念が空転する民主主義」である。人権、多様性、気候変動対策、ジェンダー平等──いずれも重要な課題であるにもかかわらず、それが“絶対的正義”として語られることで、異論が許容されにくい空気が広がっていく。
この現象は、暴力や粛清を伴う独裁とは異なるが、“道徳による支配”という意味では極めて統制的であり、異論者の社会的排除という「やわらかい弾圧」が生まれる構造に他ならない。
中国の台頭と再び現れる緊張の構図
近年、技術・経済・軍事において中国が急速に台頭してきたことにより、再び世界は二極的な構図へと傾きつつある。特にAIや監視技術の分野で中国が圧倒的な実行力を見せつけたことで、欧米の理念主導の規制や倫理議論が空回りしている実態が浮き彫りとなった。
たとえば、欧州連合(EU)はAI規制において「人権尊重」や「説明可能性」を重視する姿勢を示してきたが、実際には自前の競争力が乏しく、理想だけが先行する状態に陥った。一方で、アメリカと中国は技術開発で激しく競争し、「理念より成果」が優先される現実を突きつけた。
このような状況は、かつての冷戦構造とは異なるが、再び民主主義体制に“現実に向き合わざるを得ない緊張”を呼び戻しているとも言える。
民主主義は常に問い直されなければならない
本稿で述べた仮説──「民主主義には競争相手が必要である」という考え方は、民主主義を否定するものではない。むしろ、民主主義を民主主義たらしめるためには、常に相対化され、批判に晒される環境が必要であるという立場からの問題提起である。
絶対的な正義は存在しない。だからこそ、民主主義もまた、外部の他者や内部の異論との対話を通じて、自らの誤りや偏りを修正し続けることによってのみ、生きた制度であり続けられる。
そしてもしそれがなければ、制度的には選挙があり、言論の自由があるように見えても、実質的には“正しさの独裁”が支配する、もうひとつの権威主義”へと堕していく危険がある。
歴史が教えてくれるのは、どんな理念も、それが問われなくなったときから腐敗が始まる、という厳しい真理である。