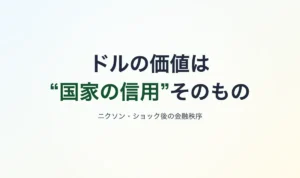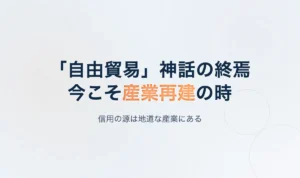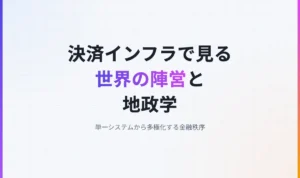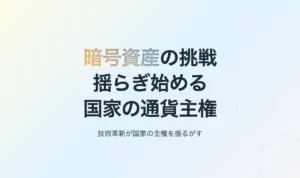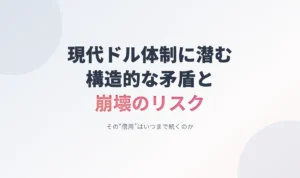金本位制の起源と仕組み
金本位制とは、通貨の価値が一定量の金と交換できることを保証する制度です。たとえば、1ドルが0.05オンスの金と交換できると定められていれば、ドル紙幣の価値はその金に裏打ちされたものとなります。これは、通貨の信用を国家の保証ではなく、金という普遍的な価値のある資源に基づかせる仕組みです。
この制度は19世紀から20世紀初頭にかけて広く採用され、イギリスをはじめとする先進諸国の経済を支えました。国際取引においても金本位制は有効に機能し、為替レートは固定され、物価も安定しやすいという利点がありました。
しかしその反面、国家の経済政策が硬直化し、経済成長のために必要な通貨供給の拡大が制限されるという欠点もありました。また、戦争や恐慌などの非常時には金準備の不足が深刻な問題を引き起こすこともありました。
ブレトン・ウッズ協定の成立背景
第二次世界大戦が終わりに近づいた1944年、連合国の代表がアメリカ・ニューハンプシャー州のブレトン・ウッズに集まり、新しい国際通貨体制を構築するための会議を開きました。この会議で成立したのが、いわゆるブレトン・ウッズ協定です。
当時、戦争の被害が少なかったアメリカは、世界の金保有の半分以上を手中にしており、ドルの信頼性は非常に高いものでした。これを背景に、ブレトン・ウッズ協定では次のような制度が決められました。
- 各国通貨をアメリカドルに固定する(ドル・ペッグ制)
- アメリカドルは1オンス=35ドルの固定レートで金と交換できると保証する
- IMF(国際通貨基金)とIBRD(世界銀行)を設立して、国際金融の安定を図る
このように、ブレトン・ウッズ体制は一見すると金本位制の延長のように見えますが、実質的にはアメリカドルが世界の基軸通貨となることを意味していました。各国の通貨は金ではなく、ドルを通じて間接的に金と結びついていたのです。
ブレトン・ウッズ体制の矛盾と崩壊
この新しい体制は、戦後の復興と世界経済の安定に一定の効果をもたらしました。ドルを通じて各国の通貨は安定し、貿易も活発化しました。IMFを中心とした国際金融体制も機能し、経済協力の土台が築かれました。
しかし、1960年代後半から次第に矛盾が表面化します。アメリカはベトナム戦争や大規模な社会政策(たとえばジョンソン政権の「偉大な社会」計画)によって財政赤字を拡大させていきます。一方でドルの供給量は世界に溢れ、各国は「このドル、ほんとうに金と交換できるのか?」と疑念を抱くようになります。
とりわけフランスを中心としたヨーロッパ諸国は、アメリカに対してドルを金と交換するよう要求を強めました。これによってアメリカの金準備は急激に減少し、ドルの裏付けが揺らぎ始めます。
ついに1971年、リチャード・ニクソン大統領は金とドルの交換停止を宣言します。いわゆる「ニクソン・ショック」です。これにより、ブレトン・ウッズ体制は実質的に崩壊し、通貨は金によって支えられる時代が終焉を迎えました。
その後への影響
ブレトン・ウッズ体制の崩壊以降、世界は変動相場制へと移行しました。通貨の価値は市場の需給によって決定されるようになり、政府が為替レートを管理することはなくなりました。
しかし、アメリカドルが依然として基軸通貨であることには変わりありませんでした。石油をはじめとする主要商品の取引がドル建てで行われる体制(いわゆるペトロダラー体制)は、ドルの国際的な地位を維持させる大きな要因となりました。
このように、金本位制からブレトン・ウッズ体制、そして変動相場制への移行は、単なる制度変更ではなく、覇権と信用の構造を根本から変えるものでした。ドルを支えるものが「金」から「アメリカの国力」へと移行したことで、通貨の本質そのものが変化したのです。