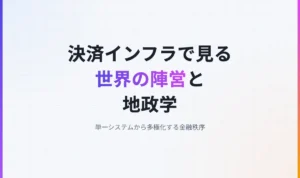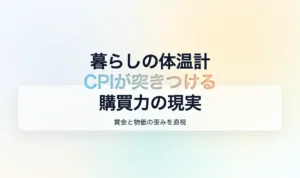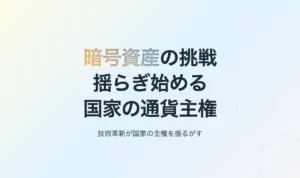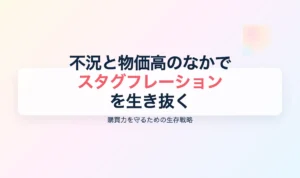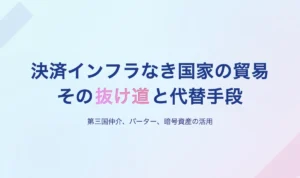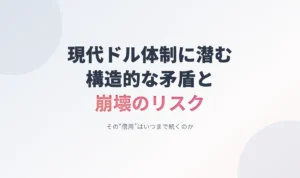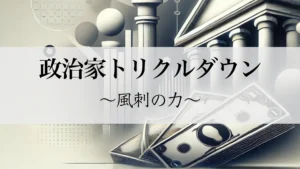国際送金の中枢を担ってきたSWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)は、現代のグローバル経済において不可欠な存在です。SWIFTは1973年にベルギーに設立され、現在では200以上の国と1万1,000以上の金融機関が参加する世界最大の金融通信ネットワークとなっています。その役割は、銀行間の送金情報、すなわち「お金をどこからどこへ、いくら送るか」といった情報を、安全かつ正確に伝達することにあります。
SWIFTは金融取引そのものを行うわけではなく、あくまで送金に関するメッセージをやり取りするシステムです。たとえば、日本の銀行からブラジルの企業へ代金を送金する場合、実際の資金移動はそれぞれの国の銀行や中継銀行が担いますが、その指示を送る経路としてSWIFTが利用されます。このように、SWIFTは国際貿易の裏側で信頼性の高い情報インフラとして機能してきました。
SWIFTの中立性とアメリカの影響力
SWIFTはベルギーに本部を置く非営利法人であり、建前としては中立性を保つ組織とされています。しかし、現実にはアメリカや欧州連合の政治的意向に強く左右される一面を持っています。特に注目すべきは、アメリカの財務省がSWIFTを利用した制裁措置を実施できる点です。
2000年代初頭、アメリカは対テロ資金対策の一環としてSWIFTのデータにアクセスし、資金の流れを監視してきました。2012年には、EUの決定を受けてSWIFTがイランの銀行をネットワークから遮断し、イランの国際取引を実質的に麻痺させたことは記憶に新しいところです。これによりSWIFTは、単なる技術インフラではなく、金融制裁の有力な手段としての性格を強く帯びるようになりました。
ロシアに対しても同様の措置が取られています。2022年のウクライナ侵攻を受けて、EUおよびアメリカはロシアの主要銀行をSWIFTから排除しました。これによりロシアは、国際的な送金ネットワークへのアクセスを大きく制限され、実際に貿易や投資の面で深刻な影響を受けています。
SWIFT排除の影響と代替手段の模索
SWIFTから排除されるということは、単に送金が遅れるというレベルの話ではありません。実質的には、当該国の金融機関が国際的な資金のやり取りから締め出されることを意味します。相手国の銀行と安全に情報をやり取りする手段を失い、信用状の発行、輸出入決済、海外送金など、あらゆる国際金融取引が困難になります。
こうした事態を回避するため、排除された国々は代替手段の開発・導入に取り組んでいます。ロシアは独自の決済ネットワークであるSPFS(System for Transfer of Financial Messages)を立ち上げ、中国はCIPS(Cross-Border Interbank Payment System)を拡張し、非ドル圏での金融インフラ強化を図っています。イランもまた、独自の決済システム「ACUMER」の導入に動いていますが、いずれもSWIFTの規模や信頼性にはまだ遠く及びません。
一方で、仮想通貨のような非中央集権型の決済手段も選択肢として浮上しています。北朝鮮が仮想通貨取引所を狙ったサイバー攻撃を繰り返している背景には、まさにこうした金融遮断への対応としての外貨獲得手段という現実があります。仮想通貨は国家の枠組みを超えて資産移転が可能なため、国家による監視・制裁をすり抜ける手段として注目されています。
SWIFTの今後と多極化する金融秩序
SWIFTはこれまで、金融のグローバルスタンダードとして圧倒的な影響力を持ってきましたが、その中立性が揺らぐ中で、各国が独自の金融ネットワーク構築を模索し始めています。アメリカに対する政治的・経済的な対抗意識を持つ国々だけでなく、アジア・アフリカ・中東の多くの国々も、自国の金融主権を確保するための代替インフラに関心を示しています。
今後、世界の金融インフラはSWIFT一極集中から、CIPSやSPFS、さらには地域的な決済ネットワーク(例:アフリカのPAPSSなど)を含む多極構造へと移行する可能性が高いと見られます。こうした動きは、単なる送金技術の変化にとどまらず、国際秩序そのものに関わる地殻変動を意味しています。
次回は、こうした多極化の動きが実際に各地域でどのように進んでいるのかを、アジア・中東・アフリカ・南米などの事例を通して見ていきます。