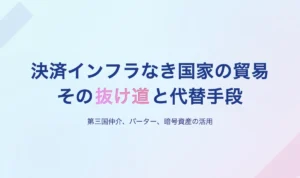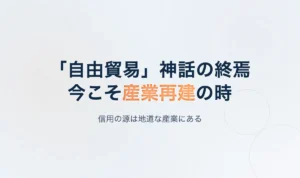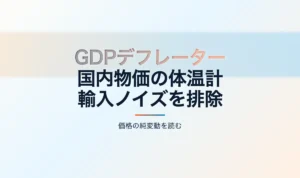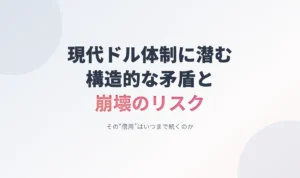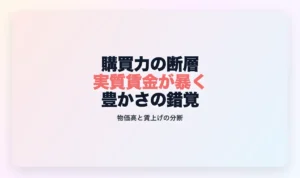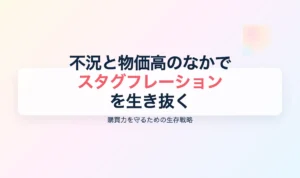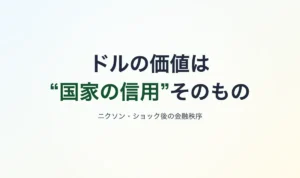国際送金や貿易決済の仕組みは、単なる金融技術ではありません。そこには国家間の信頼、政治的な立場、通貨の影響力といった地政学的な要素が色濃く反映されています。前回までに紹介したSWIFT、CIPS、SPFSのような決済ネットワークは、それぞれが単なるインフラを超えて、国家の陣営、外交姿勢、経済戦略を体現するものとなっています。本稿では、主要な地域や国がどのような決済インフラを採用しているのかを概観し、その背後にある政治的・経済的背景を読み解いていきます。
西側諸国:SWIFT中心の体制維持
アメリカ、欧州連合、日本、韓国、カナダ、オーストラリアなど、いわゆる西側先進国は、現在もSWIFTを中心とした国際決済体制の中にあります。これらの国々はドルやユーロを主要な決済通貨とし、通貨の信頼性や流動性、金融市場の整備という点でも既存システムの恩恵を強く受けています。
日本は特にこの体制に深く組み込まれており、金融機関の送金インフラはほぼ全てSWIFTに準拠しています。韓国やカナダなども同様に、米ドルとの結びつきが強く、SWIFTの維持が自国の経済安定と直結しているため、独自インフラを開発するインセンティブは少ないのが現状です。
中国とその接続国:人民元圏の拡大を目指すCIPS陣営
中国はCIPSを通じて、人民元を中心とする新たな国際決済圏の構築を目指しています。この動きに呼応するように、ロシア、中東、ASEAN諸国、アフリカの一部、南米などの国々が徐々にCIPSネットワークへの接続を進めています。
ロシアはウクライナ戦争を機にSWIFTから部分的に排除されて以降、CIPSと人民元決済への依存を急速に強めています。特に石油や天然ガスの対中輸出では人民元建て契約が増加しており、CIPSの重要性が高まっています。また、サウジアラビアをはじめとする中東諸国も、中国との貿易拡大を背景にCIPS参加を検討する動きがあります。
ASEAN諸国も、地理的・経済的な近接性からCIPSを選択肢の一つとしています。マレーシアやタイでは人民元建て貿易の割合が拡大傾向にあり、特定の銀行がCIPSを利用して人民元決済を実施しています。ただし、全体としてはまだSWIFTと並行しての運用にとどまっています。
ロシア・イラン・非西側強硬派:SPFSや独自インフラの模索
ロシアは2014年のクリミア危機以降、アメリカ主導の経済制裁に備える形で、SPFS(System for Transfer of Financial Messages)という独自の決済ネットワークを構築しました。2022年のウクライナ侵攻以降はこのSPFSへの依存度がさらに高まり、中国やイランとの接続も進んでいます。
イランもまた、長年の経済制裁の中でSWIFTを使えない状況が続いており、2024年には独自の決済ネットワーク「ACUMER」を発表しました。これにより、アジア諸国などとの貿易における資金決済の独立性を高めようとしています。これらの動きは、制裁を受ける側が金融面での自立と連携を深めようとする姿勢の表れです。
グローバルサウス・中立圏:柔軟な並立運用と地域連携
アフリカや南米、東南アジアの一部諸国は、SWIFTを基盤としつつも、CIPSやその他の選択肢を並行して導入する動きを見せています。特にアフリカでは、PAPSS(Pan-African Payment and Settlement System)という地域内決済ネットワークが開発され、域内貿易の効率化とドル依存の低減を目指しています。
ブラジルやアルゼンチンといった南米諸国も、中国との貿易増加に伴い人民元建て決済を拡大しつつあり、CIPS接続が進んでいます。ただし、依然としてドル決済の比率は高く、地域としての金融戦略はまだ模索段階にあります。
このような国々にとって、決済インフラの選択はイデオロギーというよりも実利の問題です。どのネットワークを選ぶかは、政治的対立よりも、利用コスト、信頼性、相手国との関係性など現実的な判断による場合が多いのです。
結語
世界の決済インフラは、かつてのような単一システムへの依存から、多極的な構造へと移行しつつあります。これは、単なる技術的進化ではなく、国家の経済戦略と主権に関わる問題であり、同時に国際政治の力学が反映された結果でもあります。
今後、グローバルな金融秩序はさらに細分化され、複数の決済ネットワークが並立し、相互に補完・競合する状況が続くことが予想されます。次回は、こうした分断された決済インフラの中で、直接繋がっていない国同士がどのようにして貿易や資金移動を成立させているのか、その実態に迫っていきます。