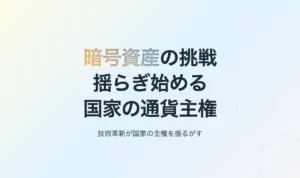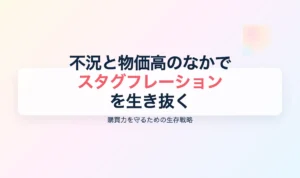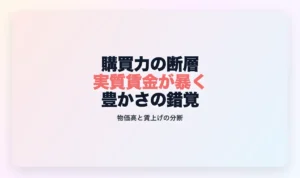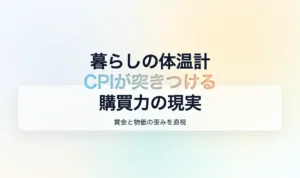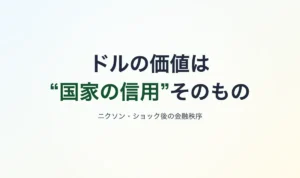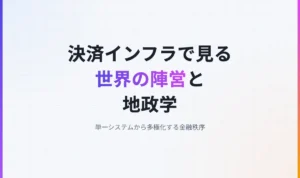
国際貿易においては、通常、送金や信用状などの決済手段がスムーズに行われることが前提となっています。しかし、現実には金融制裁や地政学的対立などの理由で、国際的な決済ネットワークにアクセスできない、あるいはアクセスを遮断された国が存在します。代表的なのがイランや北朝鮮、そしてSWIFTから部分排除されたロシアなどです。では、こうした国々が他国と貿易を行う場合、どのように決済を成立させているのでしょうか。
この問題は、国際金融の制度設計だけでなく、現場の実務、さらには外交と情報戦にも関わる複雑な領域です。本稿では、決済インフラが直接繋がっていない国同士が、いかにして経済活動を継続しているのか、その方法とリスクを整理していきます。
第三国を経由した仲介取引
もっとも一般的な手法が、第三国を介在させた取引です。これは、両国が共通してアクセス可能な金融ネットワーク、あるいは信頼できる中継国を通じて、貿易の決済と物流を分断・再構成する方法です。
たとえば、制裁下にある国と直接取引できない場合、その国の企業がいったん中立的な第三国(例:ドバイ、シンガポール、トルコなど)の企業に商品を売却し、そこから相手国に再輸出されるという形式が取られます。支払いも同様に、第三国の銀行を経由することで、直接の資金移動を回避します。
このような手法は表向きには合法な商取引に見えるため、摘発が難しく、実際に多くの取引がこの形で行われていると見られています。ただし、取引の透明性が低く、リスクやコストも高くなるため、すべての業者が利用できるわけではありません。
バーター取引とクロスボーダークレジット
物々交換、すなわちバーター取引も、金融決済が不可能な状況で用いられる手段のひとつです。これは、双方が必要とする商品や資源を相互に提供し合い、通貨を介さずに取引を成立させる方法です。
イランが医薬品と石油を交換した事例や、ベネズエラと北朝鮮が農産物と鉱物資源を交換したとされる事例などが存在します。こうした取引は信頼関係が前提となるため、国家主導での交渉や、政府系商社の介在が不可欠です。
また、クロスボーダークレジットと呼ばれる形式もあります。これは、片方が一時的に信用供与を行い、将来的な資源供給や別の取引で債務を相殺する方式です。通貨が関与しない分、国際的な監視を回避しやすい一方で、返済不履行や価格変動といったリスクが常に伴います。
仮想通貨の利用とサイバー手段
近年、注目を集めているのが仮想通貨(暗号資産)を用いた貿易決済です。特に、金融制裁下にある国々では、国家ぐるみで仮想通貨の獲得や運用が行われているとされます。代表例が北朝鮮です。
北朝鮮は、自国のサイバー部隊を使って海外の仮想通貨取引所を攻撃し、ビットコインやイーサリアム、ステーブルコインなどを不正取得しています。取得した仮想通貨は、匿名性の高い取引手段やミキサーサービスを用いて資金洗浄され、最終的には物資の購入などに使われていると見られています。
また、民間でもUSDTなどのステーブルコインを使って相手国に送金し、相手側で現地通貨に換金する形で資金移動を行う事例があります。これは銀行を通さないため、SWIFTなどの国際金融ネットワークの外で行われ、一定の自由度と迅速性を持っています。ただし、仮想通貨の価格変動や規制の強化、不正利用リスクといった問題も常につきまといます。
地方通貨・ローカル決済ネットワークの活用
一部の国では、ドルやユーロといった基軸通貨を介さずに、相手国と自国通貨の直接交換(通貨スワップ)による決済を行う事例も出てきています。人民元やルーブル、ディルハムなどのローカル通貨を使った直接決済は、特に中国やロシア、アラブ諸国の間で拡大しつつあります。
これらは必ずしもSWIFTやCIPSといった大規模ネットワークに依存せず、両国間で合意されたローカルな仕組みに基づいて行われることが多く、相互の金融主権を守りつつ貿易を継続できる手段として機能しています。
結語
金融インフラが断絶された環境下でも、国家や企業はあらゆる手段を駆使して経済活動を維持しようとします。仲介国を通じた三国間取引、バーターや信用取引、仮想通貨の活用、ローカル通貨による決済など、その方法は多岐にわたります。
こうした手法は決して万能ではありませんが、制裁や政治的分断という制約下において、現実的に生き残るための「知恵と執念」の現れでもあります。次回は、国家の統制を超えて通貨主権を揺るがす存在――ビットコインをはじめとする暗号資産の地政学的意味に踏み込んでいきます。