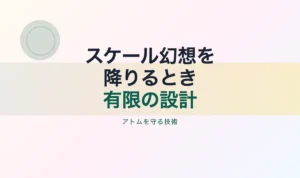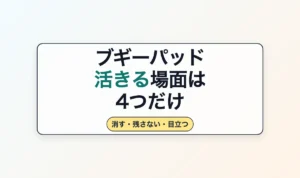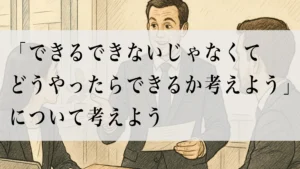ソフトウェアエンジニアとして10年働いてきて、学生時代を含めれば15年この業界にいる。そして今、一つの確信に至った。我々が「ドッグイヤー」と呼んできたものは、技術の進歩ではない。単なる支配者の都合である。
20年前のbashが動き、5年前のAWSが動かない不条理
学生時代に書いた15年前のbashスクリプトは、今でも問題なく動作する。一方で、プロとして給料をもらい、「ベストプラクティス」に従って書いたAWSのコードは、わずか5年でエラーを吐く。この現実は何を意味しているのだろうか。
本当に技術の進歩が必然的に古いものを淘汰するなら、1970年代のC言語や1980年代のbashこそ「古すぎて使い物にならない」はずだ。しかし現実は逆である。Linuxカーネルは今でもCで書かれ、世界中のサーバーを支えている。40年前のシェルスクリプトが現在も稼働し続けている。一方で、つい数年前のJavaScriptフレームワークは「レガシー」扱いされ、クラウドAPIは頻繁に「非推奨」となる。
この矛盾は、技術的必然性では説明できない。では何が本当の理由なのか。
支配者の存在が決める技術の寿命
答えは権力構造にある。AppleSiliconの登場を考えてみよう。この変更によって、ほぼすべてのMacアプリケーションが対応を余儀なくされた。影響は甚大だったが、それが可能だったのはAppleがプラットフォームを完全に支配していたからである。
一方で、Cやbashが安定しているのは、これらを支配する単一の企業が存在しないからだ。ISOの標準化委員会やGNUプロジェクトのような分散した組織では、一方的な破壊的変更を強制することができない。
つまり、支配者がいない技術は安定し、支配者がいる技術は頻繁に変更される。これが「ドッグイヤー」の正体である。技術の進歩の速さではなく、支配者の都合の変更スピードなのだ。
ムーアの法則という免罪符
「技術の変化が速いのは当然だ」という論調の背景には、半導体技術の急速な進歩がある。確かにムーアの法則は驚異的だった。処理能力は指数的に向上し、メモリ容量は劇的に増大し、ネットワーク速度も飛躍的に改善された。これは間違いなく本物の技術進歩である。
しかし、この本物の進歩に便乗して、技術的必然性のない変更まで正当化されてしまった。UIフレームワークの頻繁な入れ替え、API仕様の恣意的な変更、「モダン」な開発手法の乱立。これらは半導体の進歩とは何の関係もない。
ムーアの法則が示したのは「もっと高速に、大量に処理できる可能性」であって、「今までのやり方を捨てる必然性」ではない。人間がデータを保存し、検索し、変換し、表示するという根本的なニーズは変わっていないのだから。
変わらないものと変わるものの境界線
20年前のデータベース設計の本には、こんな記述がある。「ドッグイヤーと呼ばれる業界だが、業務知識は変わらない」。この洞察は鋭い。商習慣や業務フローは業界全体が作り上げるものであり、一社の都合で変わらない。データベースの正規化理論も、現実世界のデータの性質という普遍的な制約に基づいている。
変わらないのは、集合的な知恵や物理的制約に基づくものだ。変わるのは、単一企業の意思決定に依存するものである。この区別を曖昧にすることで、「ドッグイヤー」という言葉は企業の都合を技術的必然性にすり替える効果を持った。
高給エンジニアという共犯者
現代の上級エンジニアの地位と給与が高まっているのは、それだけ企業にとって都合がいいからだ。しかし、リーナス・トーバルズやブライアン・カーニハンの給与を気にする人がいただろうか。
現代の「エンジニア市場価値」が高いのは、企業が優秀な人材を囲い込み、自社の利益のために活用したいからである。そしてその人材に期待されているのは、企業都合の変更を技術的権威で正当化し、組織に浸透させることだ。
本来、エンジニアは「あまねく人々の役に立ちたい」という純粋な動機を持っていたはずだ。それが今では「高給をくれる人の犬」となってしまった。技術的美学よりビジネス価値を優先し、良いコードより素早いデリバリーを求める。結果として、技術的負債と企業依存が拡大し続けている。
才能なき者の洞察
振り返ってみれば、この構造に気づけたのは「才能がない」からかもしれない。ベストプラクティスについていけなくなったからこそ、「いったい何をしてきたんだ?」と立ち止まって考えることができた。
もし才能があってついていけたら、あるいは自分がベストプラクティスを作る側になってしまったら、自分がやっていることの愚かさに気づけなかっただろう。カーニハンの仕事とは本質的に違うことをしていることに気づけなかっただろう。背後にある力の構造を見抜くことはできなかっただろう。
技術者としての尊厳を取り戻すために
我々は今、選択の時にいる。企業の都合に振り回されて「明日変わるベストプラクティス」を必死に追いかける駄馬であり続けるか。それとも、技術の本質を見極める目を持った、本当の意味での技術者になるか。
真の技術者とは、流行や権威に惑わされず、技術的合理性で判断する人である。「なぜその技術が必要なのか」「誰がその変更を求めているのか」「それは本当に技術的必然性があるのか」を問い続ける人である。
ドッグイヤーという美名の下に隠された、極めて人間的で商業的な動機を見抜く時が来た。技術の本質に向き合い、20年後も価値のある普遍的な原理原則に投資しよう。企業の都合という「人参」ではなく、真に人類の役に立つ技術を追求しよう。
それが、技術者としての尊厳を取り戻す唯一の道である。