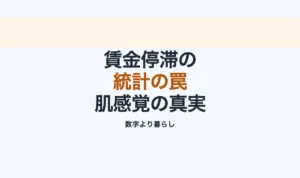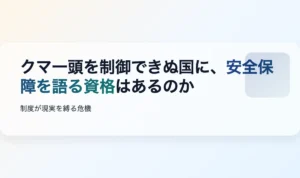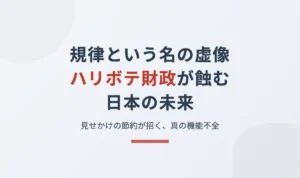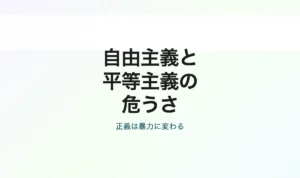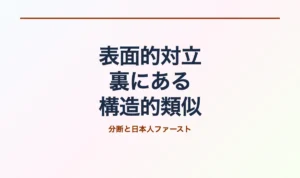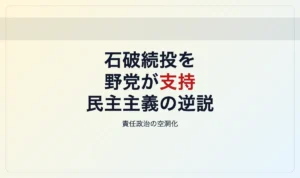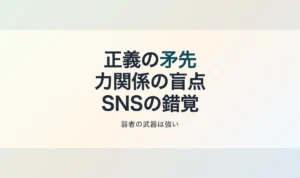参政党が掲げる「日本人ファースト」というスローガンが、現在の日本政治において一定の支持を集めている。2025年の参議院選挙において、同党は急速な支持拡大を見せ、各種世論調査でも存在感を増している。選挙ドットコムの調査によれば、この政党への支持は電話調査とネット調査で拮抗し、むしろ電話調査での支持が高いという結果も出ている。これは、従来想定されがちな「特定のネット層による支持」という図式では説明できない、より幅広い層への浸透を示している。
実際、参政党の街頭演説には若い世代から高齢者まで幅広い年齢層が集まっており、会社員、自営業者、主婦など多様な職業の人々が参加している。これまでの政治的枠組みでは捉えきれない新たな政治現象が起きていることは間違いない。この現象を理解するためには、まずそのスローガンの内容そのものを冷静に検討する必要がある。
スローガンの内容についての検証
「日本人ファースト」というスローガンは、メディアや知識人からしばしば批判の対象となる。「排外主義的」「差別的」「時代錯誤」といった批判が繰り返されているが、その内容を虚心坦懐に検討すれば、全く異なる姿が見えてくる。
国家を構成する国民の権利と利益を優先することは、国家の基本的な存在理由そのものである。これは政治学や国際関係論における基本中の基本であり、あらゆる国家が実践している原理である。国家とは何かと問われれば、それは特定の領域において特定の人々(国民)の安全と福祉を保障する政治的共同体である、というのが最も簡潔な定義であろう。
世界を見渡しても、他国民を自国民より優先する国家など存在しない。アメリカは「アメリカファースト」を明確に掲げ、中国は中国人民の利益を最優先に政策を策定し、ヨーロッパ各国も自国民の福祉を第一に考えている。これは当然のことであり、もしそうでなければ、その国家の正統性そのものが問われることになる。
選挙権は国民にのみ与えられ、社会保障制度は国民を対象とし、雇用政策は自国民の就業機会確保を目指し、災害対応では自国民の救助が最優先される。国防は自国民の生命と財産を守るためのものであり、外交は自国の国益追求のために行われる。これらはすべて「自国民ファースト」の原理に基づいている。
この原理を否定することは、国家という制度そのものを否定することに等しい。なぜなら、国民を優先しない国家に、一体何の存在意義があるというのだろうか。税金を納め、法律に従い、時には兵役の義務まで負う国民が、その見返りとして国家から保護と福祉を受けるのは、社会契約の根本原理である。
したがって、「日本人ファースト」という考え方そのものを批判することは、論理的に極めて困難である。問題があるとすれば、それは内容ではなく、表現や文脈の問題であろう。
しかし、わざわざ言うことの意味
では、このような当然の原理を、なぜわざわざ政治スローガンとして掲げる必要があるのか。あまりにも自明な事柄を声高に主張することは、確かに奇異に映り、時としてグロテスクですらある。
普通の状況であれば、「国民を優先する」などということをわざわざ言う必要はない。それは空気を吸うのと同じように当然のことだからである。政治家が「私は呼吸をします」と宣言しないのと同様に、「国民を優先します」などと言う必要もないはずである。
しかし、別の見方をすれば、そう言わねばならないほど切迫した状況にあるということでもある。当然であるはずのことが当然でなくなった時、人はそれを明言せざるを得なくなる。生理現象に例えれば、普段は口にしない事柄も、緊急事態には直接的に表現せざるを得ない場合がある。
「日本人ファースト」というスローガンがこれほど注目を集め、支持を獲得しているということは、多くの国民が「自分たちの利益が適切に保護されていない」と感じているということの表れである。当然の権利が当然に保障されていないという認識が広がっているからこそ、それを明確に要求する必要が生じているのである。
日本の現状
実際、日本の状況は統計的にも悪化している。厚生労働省の毎月勤労統計調査によれば、実質賃金は長期にわたって低下傾向にある。1997年をピークとして、日本の平均賃金は先進国の中で唯一下がり続けている。この間、アメリカやヨーロッパ諸国の賃金は上昇を続けており、日本だけが取り残されている状況が鮮明になっている。
非正規雇用の割合は総務省統計局のデータによれば4割近くに達し、将来への不安を抱える労働者が激増している。特に若い世代では、正規雇用に就けない、就けても昇進や昇給の見込みが立たない、という状況が常態化している。かつて日本社会の安定を支えてきた中間層の没落は深刻で、「一億総中流」と言われた時代は遠い過去のものとなっている。
社会保障制度への不安も高まっている。年金制度の持続可能性への疑問、医療費負担の増加、介護保険制度の綻びなど、将来への展望を描くことが困難になっている。内閣府の国民生活に関する世論調査では、将来への不安を抱く国民の割合が過去最高水準に達している。
一方で、海外援助や国際機関への拠出は継続され、その規模は決して小さくない。ODAの総額は年間数千億円規模に上り、国際機関への分担金や拠出金も相当な額になる。また、外国人労働者の受け入れは年々拡大されており、技能実習生制度や特定技能制度などを通じて、多くの外国人が日本で働いている。
これらの政策が間違えている、と主張しているのではない。ただ、自国民の生活が困窮している状況で、なぜ海外への支援や外国人労働者の受け入れが優先されるのか、という素朴な疑問を抱く国民が増えているのも事実である。「まず日本人の生活を立て直すべきではないか」という声が上がるのは、極めて自然な反応といえる。
教育分野でも深刻な問題が表面化している。奨学金返済に苦しむ若者の増加、教育費負担の重さによる少子化の進行、研究予算の削減による大学の国際競争力低下など、将来世代への投資が十分に行われていない現状がある。
地方の疲弊も深刻である。人口減少と高齢化が進む地方では、基本的な公共サービスの維持すら困難になりつつある。商店街の空洞化、公共交通の廃止、医療機関の撤退など、地方に住む日本人の生活基盤が根本から揺らいでいる。
政治への不信
同時に、既存の政治に対する信頼は失墜している。政治とカネの問題は繰り返され、国民の多くが政治家の清廉性に疑問を抱いている。自民党の派閥の裏金問題、立憲民主党をはじめとする野党の政権担当能力への疑問など、既存政党への不信は根深い。
国民生活の改善は後回しにされ、政局重視の姿勢が続いている。国会では党派対立ばかりが目立ち、建設的な政策論議は少ない。メディアも政局報道に偏重し、政策の中身を詳細に検討する報道は限られている。
「政治家は国民のことを本当に考えているのか」という根本的な疑問が広がっている。既存政党の政治家たちは、選挙の時だけ国民に近づき、当選すれば利権や派閥の論理に従って行動しているのではないか、という不信感が蔓延している。
特に、国際協調や外交関係を重視するあまり、国内問題が軽視されているという印象が強い。外国との関係では丁寧な配慮を示すのに、自国民の困窮には鈍感である、という批判が聞かれる。これでは、「政治家は外国人のことは気にかけるが、日本人のことは軽視している」という印象を与えても仕方がない。
また、エリート層と一般国民の乖離も深刻である。政治家、官僚、学者、メディア関係者などのエリート層は、グローバル化の恩恵を受ける一方で、その負の側面を直接経験することは少ない。一方、一般国民は雇用不安や生活苦に直面しており、この温度差が政治不信を増幅させている。
結論
「日本人ファースト」が支持されるのは、その結果としか言えない。当然であるはずの原理をわざわざ主張しなければならないほど、多くの国民が自分たちの利益が軽視されていると感じているということである。
統計が示す生活水準の低下、将来への不安の高まり、政治への不信の深刻化、これらすべてが複合的に作用して、「日本人の利益を最優先に考える政治」への渇望を生み出している。この現象は、日本社会が直面している構造的な問題の表れに他ならない。
重要なことは、この現象を単純に批判するのではなく、その背景にある国民の切実な思いを理解することである。自国民を優先するという当然の原理が政治スローガンとして機能している現実を直視し、なぜそのような状況に至ったのかを真摯に検討することが求められている。