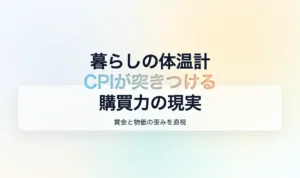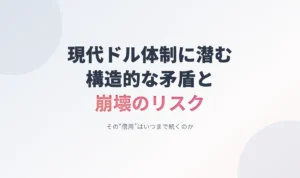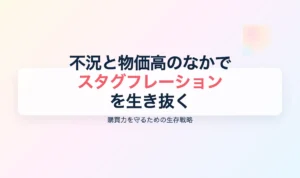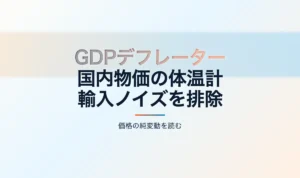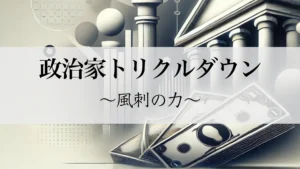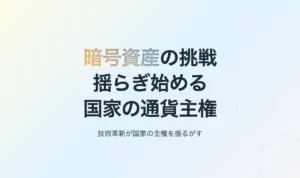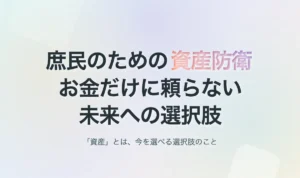
自由貿易の理想と現実
自由貿易は、経済学的には非常に洗練された理論です。各国が比較優位に基づいて得意な産業に特化し、貿易によってお互いに利益を得るという考え方は、理屈としては正しく、実際に国際経済の成長を支えてきた要素の一つでもあります。
しかし、この理想がそのまま現実の政策として適用されたとき、問題が生じます。自由貿易の導入によって効率の悪い産業は淘汰され、より安く高品質な外国製品が市場に出回るようになりますが、その一方で、国内の雇用が失われ、地域経済が衰退するという副作用が避けられません。
特にアメリカでは、製造業の空洞化が顕著に進みました。企業はコスト削減のために生産拠点を海外に移し、国内ではラストベルトと呼ばれる工業地帯が荒廃していきました。自由貿易の果実は一部の大企業や都市部の上層に集中し、労働者階級や地方には格差と疎外感だけが残ったのです。
覇権通貨の前提としての「産業力」
アメリカがドルという覇権通貨を維持できる理由の一つは、単に金融制度や軍事力が強いからではなく、かつては「実際に世界を支える産業」を持っていたからです。トラクターから自動車、家電から通信機器まで、アメリカは世界中に実物を供給できる国家でした。
しかし、現在ではドルは刷れてもモノは作れない、という皮肉な状況になりつつあります。NVIDIAやOpenAIといった一部のテクノロジー企業は突出していますが、これはあくまで例外的な存在であり、国民経済全体を支えるには不十分です。
製造業がなければ、国としての自立性やレジリエンスは損なわれ、通貨への信認も徐々に薄れていく可能性があります。つまり、ドルの信認はアメリカがモノを作れる国であり続けることと不可分なのです。
トランプ政権と関税政策の背景
近年、アメリカが保護主義的な政策に転じている背景には、こうした構造的な焦りがあります。トランプ政権による関税の引き上げや、中国製品への圧力は、表面的には貿易不均衡の是正を目的としていますが、その本質は「国内産業の再建」への試みであり、ひいてはドル体制の延命策とも言えます。
自由貿易の理念を放棄することには批判もありますが、現実にはアメリカが従来の“すべてを輸入で賄う”スタイルを見直さざるを得ない状況に来ているのです。国内に工場を戻し、雇用を生み、供給網を立て直すことは、単なる経済政策ではなく、安全保障の一環でもあります。
日本にとっての示唆
アメリカの状況は、他人事ではありません。日本もまた、長らく自由貿易の恩恵を受けてきましたが、同時に産業の空洞化や賃金停滞という問題を抱えています。円安による輸入コストの上昇も、製造業の再興がなければ持続可能ではありません。
自由貿易に頼りきるのではなく、「何を国内で生産できるか」「何を自前で確保すべきか」を真剣に見直す時期に来ています。安定した通貨、強い国民経済、信頼される社会基盤——これらはすべて、見えないところでつながっています。
経済の基盤は「きれいごと」では支えられない
自由貿易は理想です。しかし人間の社会は理屈だけでは動きません。感情、文化、地理、そして国家の安全といった非経済的要因が、最終的には通貨や制度の持続性を決定します。
きれいごとだけでは基軸通貨は保てません。モノを作り、雇用を守り、国を支える地道な産業こそが、長期的な信用の源となるのです。経済の土台は、見えないところでいつも揺れています。それを見ようとする意識こそが、今の私たちに求められているのではないでしょうか。