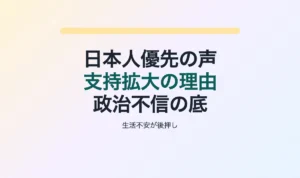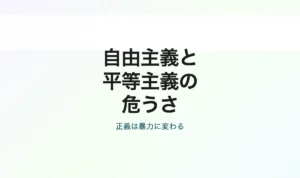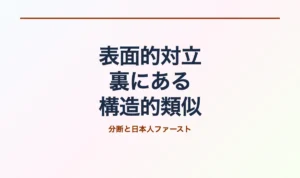十月十七日夜、仙台市青葉区――JR仙台駅からわずか三キロの広瀬川河川敷で、親子とみられるクマ五頭が目撃された。体長一メートル級が二頭、七十センチ級が三頭。警察は急行したが、姿は消えた。
この一報は単なる珍事ではない。東北最大の都市、政令市・仙台の中心圏に野生のクマが現れたという事実そのものが、社会の“想定外”を突き崩した。
山形方面から続く広瀬川は、クマにとって格好のグリーンコリドー(生態回廊)である。人間にとっては散歩道でも、野生動物にとっては都市へと続く安全路。つまり、地図上では市街地でも、生態的には山と地続きなのだ。
それでもこれまで「出るわけがない」と信じていた。その前提が崩れた瞬間、行政は制度の網の目に絡まって動けなくなった。
制度を守って人を守らず
現行法では、市街地や住宅密集地で猟銃を発砲することは原則禁止されている。人命を守るための制度が、いざという時、人命を縛る枷になる。箱わなを設置しようにも、河川敷での許可、通行人への安全確保、手続きの煩雑さ――どれを取っても現実的ではない。
制度は“山にいるクマ”を想定して作られており、“街に降りるクマ”には対応していない。つまり、制度の想定が時代に取り残されたままなのだ。
行政は「前例」を恐れ、「許可」を盾に動きを鈍らせる。現場の警察やハンターはリスクを理解しながらも、法律の網を越えられない。結果として、制度は厳守され、人は守られない。
この国では、マニュアルが命より強い。
思い出されるのは能登半島地震の光景だ。避難所には毛布も不足し、水も届かず、電気も回復しない。報道が繰り返したのは「ボランティアの献身」「地域の絆」。だがその美談の裏で、国家は本来の任務――国民の生命と尊厳を守ること――を果たしていなかった。
行政の遅れを「民の善意」で補う構図は、称賛ではなく敗北の証である。
ボランティアは尊い。しかし、彼らがいなければ回らぬ国は危うい。税を徴収しながら、最も弱いときに公が機能しないなら、それは国家ではなく“徴税機構”にすぎない。
能登の避難所に毛布がなかったように、仙台の河川敷でクマが歩く夜にも、行政の現場には空白がある。
予兆はあった、だが握りつぶされた
青葉区にクマが出る以前から、猟友会や地域の住民は何度も異変を報告していた。山の餌が少ない、民家裏での目撃が増えている、畑が荒らされる――それらの声は「一時的なもの」として処理され、議会に上がる前に消えた。
行政は“騒ぎになること”を恐れ、“現実を見ること”を避けた。
しかし自然は忖度しない。人間が線を引こうと、クマには関係ない。食える匂いがあれば、境界を越える。
山と街を隔てていた“緩衝地帯”――かつての里山――を放棄したのは人間だ。耕作放棄地は藪となり、廃屋は夜の匂いを溜める。人が自然から距離を取ったつもりで、実際には野生を呼び寄せる道を整備した。
それが現代の歪みだ。クマは悪くない。責任を取るべきは、人間のほうである。
人が死なねば動かぬ国家
このままでは、人的被害が出るまで何も変わらない。
いや、被害が出ても変わらないかもしれない。なぜなら、この国の行政は“事件の後”を処理することには長けているが、“事件の前”を防ぐことには致命的に弱いからだ。
クマに襲われ、人が命を落とせば、メディアは騒ぎ、国会は「再発防止策」を掲げ、関係閣僚が現地視察に行く。だがそれは「政治的儀式」でしかない。
そうなれば国民は悟る。
高い税を納めても、国は守ってくれない。
クマ一頭を制御できない国家が、安全保障を語る――それは笑い話にもならぬ。
“敵国の脅威”よりも、“自国の怠慢”が、よほど恐ろしい。
制度の更新なき国家は、ゆるやかに崩れる
クマの出没は偶然ではない。能登の遅滞も偶然ではない。両者は同じ病から生じた――「現実より制度を信じる病」だ。
自然はマニュアルを読まない。災害も法律を守らない。人間の作ったルールは、人間の都合でしかない。
いま必要なのは、制度の修正ではなく、思想の刷新である。
国とは、文書や法令ではなく、“生きている人間”を守るために存在するものだ。
それを忘れた瞬間、国家はただの空洞になる。
仙台の夜を歩いた五頭のクマは、その空洞の輪郭をはっきりと照らし出した。