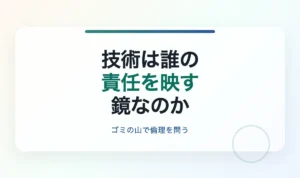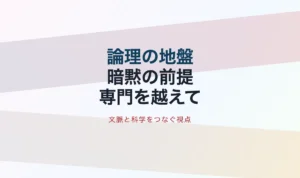Sandy Bridge。2011年に登場したこの名を覚えている人は、今や少数派かもしれない。だがそれは、ひとつの節目であった。コンピューティングの世界で「人間が必要とする性能」と「企業が供給し続ける性能」が決定的に乖離した瞬間である。あの頃のCPUを積んだパソコンはいまだ現役であり、ウェブもオフィスも動画編集も問題なくこなす。むしろ、近年の機種より軽快に感じることすらある。なぜか。それは「進歩のための進歩」が始まったからである。
かつて技術の進化は、生活を直接的に豊かにした。Pentiumが登場した時代、確かに新しいCPUは作業の待ち時間を劇的に減らした。しかしSandy Bridge以降、性能の上昇は人間の知覚を超えた。性能は伸び続けたが、体感は変わらない。ユーザーが求めるのは安定と信頼なのに、企業は更新を強いる。ここに文明の転倒がある。技術が人を解放するのではなく、人が技術の寿命に合わせて生きるようになった。
惰性と傲慢が生んだIntelの没落
Intelは長年その頂点にいた。Sandy Bridge以降、進化を止めた彼らは市場を支配していたが、支配は怠惰を呼んだ。第7世代のノートPCがいまだに2コアしか持たなかった事実は、彼らがどれほど市場を軽視していたかの証拠である。その隙を突いたのがAMDのRyzenだった。あれは単なる製品ではない。沈滞した業界への怒号であり、「性能を奪還せよ」という反乱だった。
Ryzenは「価格に対して誠実」であった。Intelがブランドと市場独占で高値を維持していた間に、AMDは現実的な性能を、現実的な価格で提供した。その瞬間、ユーザーは初めて“選択肢”を取り戻した。技術的革新以上に重要だったのは、この精神の転換である。つまり、コンピューティングの世界は「信仰」から「判断」へと回帰したのだ。Intelの衰退とは、技術ではなく倫理の敗北だったのである。
「進歩」という言葉の堕落
進歩という言葉は、もはや呪文のように使われている。新しいCPU、新しいOS、新しいスマートフォン――それらは確かに速く、賢く、美しくなったように見える。しかし、その背後では互換性が破壊され、ユーザーの自由が削られている。更新を拒否すればアプリが動かず、ハードを更新すれば設定が勝手に変わる。「便利さ」はいつの間にか「従順さ」と同義になった。進歩は人間を自由にするための手段であったはずなのに、いまや管理のための口実になっている。
文明が成熟するとは、本来「余裕が生まれること」である。だが現代のコンピューティングは、余裕ではなく焦燥を生む。新しいものを追わなければ取り残されるという強迫観念が、企業の宣伝によって制度化されている。進歩が加速するほど、私たちはその速度に縛られ、思考する暇を失う。これはもはや技術の問題ではない。文明そのものが、人間中心から技術中心へと重心を移しているのだ。
文明の転倒、そして人間の再定義
コンピュータは人間のための道具であるはずだった。しかし、現代の人間はその道具の更新サイクルの中で生きている。寿命を決めるのは肉体ではなくサポートポリシーであり、自由を制限するのは法律ではなく利用規約だ。ここで起きているのは、道具が文明の主語になったという転倒である。
だが希望はある。Linuxという“自由の残響”がそれを証明している。古いマシンに新しい息を吹き込み、企業が切り捨てた機械を再び生かす。この行為は単なる技術趣味ではない。人間が自分の手に技術の支配権を取り戻すための、最小単位の抵抗である。
文明が転倒しているいま、人間が問うべきは「次のCPUは何か」ではなく、「自分の手で動かせるか」である。技術の進歩が本当に人を進めるものであるためには、まず人間が“止まる”覚悟を持たねばならない。進歩の終わりは、退化ではない。盲目的な加速から降り、再び考える権利を取り戻すこと――それこそが、今世紀の文明が求める真の再起動である。