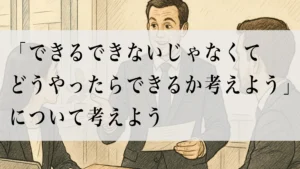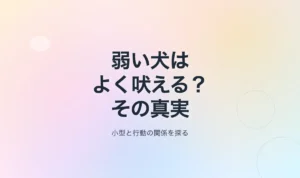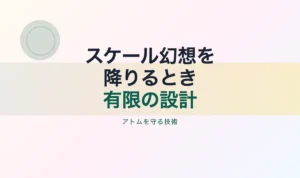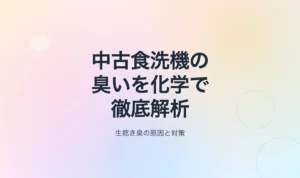ネタ元:ロッテ「チョコパイ」が過去最高売り上げ 約40年間で変えたこと、変えなかったこと:ロングセラーの秘密(1/5 ページ) - ITmedia ビジネスオンライン
はじめに: チョコパイ売上増加の現象
ロッテの「チョコパイ」に代表される定番スイーツ菓子は近年売上を伸ばしています。実際、ロッテのビスケット菓子カテゴリーでは主力の「チョコパイ」ブランドが前年比約18.7%増という大幅な成長を達成しました (ビスケット特集:ロッテ 「チョコパイ」大幅伸長 - 日本食糧新聞・電子版)。これは単年の偶発的な現象ではなく、新型コロナ禍以降の生活環境や消費者意識の変化を背景とした継続的なトレンドと考えられます。本稿では、日本の広義のスイーツ市場全体の動向や社会的背景を踏まえ、なぜ今このタイミングでチョコパイのような定番スイーツが前年比を超える成長を遂げたのか、その要因を論考します。
(注記:ネタ元の記事のとおり、2024年4月〜2025年2月にかけては前年度比102%増となっています)
広義のスイーツ市場の規模と動向
まず日本のスイーツ市場全体の規模を概観します。菓子類全般に対する家計の支出は近年増加傾向にあり、2023年には1世帯当たり約99,520円を菓子に支出しており前年比5.5%増となりました (グラフで見る! 菓子類の家計消費支出 1世帯当たりの年間消費支出額の推移〖出所〗総務省 家計調査)。この金額は2000年以降で最高水準であり、コロナ禍前の水準を上回る回復を示しています(下図参照)。 (グラフで見る! 菓子類の家計消費支出 1世帯当たりの年間消費支出額の推移〖出所〗総務省 家計調査) 家庭で菓子に費やす支出が増えた背景には、巣ごもり需要や物価上昇による単価アップなど複数の要因が絡んでいます。実際、2020~2021年はコロナ禍で一時市場が停滞しましたが、2022年以降は原材料高による値上げもあって菓子メーカーの売上高は増加傾向に転じました (菓子業界の動向およびM&Aについて - M&A・事業承継なら経営承継支援)。需要面では、2022年後半以降の経済再開によって外出や観光が活発化し、コンビニや職場での間食需要や土産需要が回復しています (菓子業界の動向およびM&Aについて - M&A・事業承継なら経営承継支援)。インバウンド(訪日観光客)の戻りも菓子市場には追い風となり、和菓子・洋菓子の市場はコロナ期の落ち込みからプラス成長に転じました。例えば観光土産向けの高級菓子だけでなく、手軽な焼き菓子やドーナツといったカテゴリーでもブームが起き、各社が新商品を投入して市場の活性化に努めています。一方で消費者物価の高騰下では「コスパの良さ」も重視されており、スイーツ市場全体としては量より質・単価重視の消費に支えられて成長している状況です。
特にコンビニエンスストアのスイーツ市場はこの数年で確立され、大きな伸びを示しました。コンビニ各社はオリジナルのデザートブランドを展開し、若年層を中心に高い認知を獲得しています。コンビニスイーツ市場規模は昨年時点で推定約950億円規模に達し前年比4%増と堅調で、ついに市場規模1,000億円が視野に入るまで成長しています (スイーツ市場動向:CVS “コンビニスイーツ”市場を確立 - 日本食糧新聞・電子版)。スーパー・コンビニで買える手頃な洋生菓子(シュークリームやプリン、ロールケーキ等)は「小腹満たし」や「自分へのご褒美」として幅広い世代に定着し、購入単価も毎年上昇傾向です。ある調査では、スーパー・コンビニのスイーツ購入に1回あたり平均211~225円程度を使っており過去最高値を更新中と報告されています (モンテール 現代の休憩実態とスイーツの喫食状況を調査 ... - PR TIMES)。また購入チャネルのシェアも変化しており、スイーツを買う場所として従来トップだった洋菓子専門店を押さえ、「スーパー」「コンビニ」が1位・2位を占めています(例:ある調査ではスーパー利用63%、コンビニ56%、専門店23%という結果)。このように広義のスイーツ市場は量的にも金額的にも拡大傾向にあり、その牽引役の一つがコンビニや量販店で買える定番スイーツ商品なのです。
洋菓子店の衰退とコンビニスイーツ台頭
一方で、街角の洋菓子店やケーキ専門店の経営環境は厳しさを増しています。帝国データバンクの調査によれば、2024年は1~5月だけで洋菓子店の倒産が18件発生しており、このペースが続けば過去最多だった2019年(49件)を上回る可能性があると指摘されています。実際、2024年1~10月累計では「スイーツ店」倒産が36件に達し前年同期比2倍と急増しており、2000年以降で最多ペースです (1‐10月「スイーツ店」倒産36件 前年同期の2倍増 物価高)。倒産に至っていないまでも、個人経営のケーキ屋が廃業するケースも増えているとみられます。こうした洋菓子専門店の衰退には大きく二つの局面がありました。第一に2010年代後半~2019年頃には、コンビニなど手軽で安価なスイーツとの競争激化に耐えられず市場退出を余儀なくされる店が相次いだことです。コンビニ各社が充実させたプチ贅沢感のあるデザートは、味や品質も向上しつつ数百円で買えるため、「高い専門店ケーキでなくても十分」という消費者も増えました。その結果、かつて誕生日ケーキやご褒美スイーツを求めて地元の洋菓子店に通っていた層がコンビニスイーツなどに流れ、一部の街のケーキ屋は客足を奪われました。
第二に2022年以降の原材料高騰とコスト増が、洋菓子店を直撃しています。砂糖、生クリーム、小麦粉、フルーツといったケーキ材料の価格が軒並み上昇し、特にチョコレートはカカオ豆不足や円安の影響で過去5年で価格が約2倍に跳ね上がりました。電気代や包装資材、人件費も上昇する中で、小規模店では十分に価格転嫁できず採算悪化に陥っています。こうした状況に耐え切れず廃業や倒産を決断する例が増えているのです。皮肉にも、コロナ禍を経て菓子需要自体は全体として上向いたものの、その恩恵は規模の大きいメーカーやチェーンに集中し、体力のない個人店はコスト高に沈むという二極化が進んだといえます。実際、全国展開する菓子チェーンのシャトレーゼは2022年度に売上高1,175億円を計上し菓子業界5位に入るなど好調ですが (菓子業界の動向およびM&Aについて - M&A・事業承継なら経営承継支援)、同時期に地域の老舗ケーキ店が閉店するニュースが各地で聞かれています。このようにスイーツ市場の成長の陰で、従来型の洋菓子専門店は衰退傾向にあり、消費者の「甘いもの購入」先が専門店から市販菓子・コンビニスイーツへシフトしていることがうかがえます。
スイーツ市場はどこから時間・お金・関心を奪ったのか
では、スイーツ市場全体の拡大は他のどの市場から消費者の時間やお金を奪っているのでしょうか。考えられるのは外食や娯楽、旅行などの「大きな消費」から「小さな消費」へのシフトです。コロナ禍では外食産業や旅行産業が大打撃を受けましたが、その反動として「おうち時間」にお金をかける傾向が強まりました (スイーツ激戦期必勝法/決め手は情報誌の“連載”にあり! | 〖中広〗地域みっちゃく生活情報誌Ⓡ販促ブログ)。特に2020年以降、人々は自宅で過ごす時間を充実させるために「癒し」や「プチ贅沢」としてのスイーツに注目し始めました (スイーツ激戦期必勝法/決め手は情報誌の“連載”にあり! | 〖中広〗地域みっちゃく生活情報誌Ⓡ販促ブログ)。旅行やレジャーに行けない代わりに、ちょっと高級なお取り寄せスイーツを注文したり、コンビニで新作デザートを買って家で映画を観ながら楽しんだりする人が増えたのです。つまり、コロナ禍で減少した娯楽・レジャー消費の一部がスイーツ購買に置き換わった側面があります。実際、「巣ごもり需要」によってスイーツ業界全体の業績はコロナ前の予想に反して好転し、2020年以降も好調が続いています (スイーツ激戦期必勝法/決め手は情報誌の“連載”にあり! | 〖中広〗地域みっちゃく生活情報誌Ⓡ販促ブログ)。外食が減った分、自宅で菓子を食べる頻度が増えたことは複数のアンケート調査でも明らかになっています。
さらに、可処分所得に限りがある中での優先順位の変化も考えられます。コロナ禍から現在に至るまで、景気の不透明感や物価高によって高額な買い物を控えるムードが続いています。その中で「それでも何か楽しみが欲しい」というニーズが、安価な贅沢品であるスイーツへの関心を高めたといえます。経済危機時に口紅など手頃な贅沢品が売れる「リップスティック効果」に例えられるように、不況期には高額な娯楽や耐久消費財は我慢しても、小さな楽しみへの支出はむしろ増える傾向があります (コロナ不況で発生した「リップスティック・エフェクト」って何?)。コロナ禍でも同様に、外食や旅行を諦める代わりに、高級スイーツや話題のお菓子を自宅で楽しむことでストレスを解消しようとする消費行動が見られました (コロナ禍の食品B2Cビジネス - J-Stage)。特に若年層ではSNSで話題の映えるスイーツに飛びつく傾向も強まり、従来はファッションや外出に使っていたお金や時間がスイーツ探し・購入に向けられるケースもあります。つまりスイーツ市場の成長は、レジャー・外食・ファッションなど他の娯楽消費から少しずつ時間と財布の中身を奪い取っているとも言えるでしょう。
「手の届くご褒美」としてのスイーツの心理的役割
スイーツ市場拡大のもう一つの背景には、消費者心理の変化があります。不安やストレスが多い時代において、甘いものは手軽に幸福感をもたらす存在です。コロナ禍で先行きが見えないストレスに直面した人々にとって、コンビニで買えるケーキやチョコレートは「自分へのご褒美」としての地位を確立しました。実際、ある調査では「自分へのご褒美に何をするか」という問いに対して、内容はダントツで「スイーツを食べる」が選ばれています (コロナ自粛で頑張った私へのごほうびはやっぱり「スイーツ」6割 月イチ・プチ贅沢が癒やしのカギ? | 株式会社ONE COMPATHのプレスリリース)。約6割の女性が「頑張った自分を癒すご褒美」にスイーツを挙げ、購入場所はスーパーやコンビニで日常の買い物ついでに手に入れるケースが多いといいます (コロナ自粛で頑張った私へのごほうびはやっぱり「スイーツ」6割 月イチ・プチ贅沢が癒やしのカギ? | 株式会社ONE COMPATHのプレスリリース) (コロナ自粛で頑張った私へのごほうびはやっぱり「スイーツ」6割 月イチ・プチ贅沢が癒やしのカギ? | 株式会社ONE COMPATHのプレスリリース)。この「手の届くご褒美」という位置づけは重要です。高額なご褒美(高級ブランド品や旅行など)は頻繁にはできませんが、数百円のスイーツなら日常的に自分を甘やかすことができるため、リピート消費が促されます。新型コロナによる自粛生活下では、「疲れた自分を癒したい時」や「ストレスを感じている時」に甘いものを食べる人が増え、「コロナストレス」を発散する手段としてスイーツの需要が高まったとの報告もあります (コロナ自粛で頑張った私へのごほうびはやっぱり「スイーツ」6割 月イチ・プチ贅沢が癒やしのカギ? | 株式会社ONE COMPATHのプレスリリース)。
また、「毎日が同じ繰り返し」という閉塞感の中で、季節限定や新商品スイーツはちょっとしたイベント的な楽しみを提供しました。コンビニ各社が週替わりで発売するスイーツや、有名パティシエ監修の期間限定商品などはSNSでも話題となり、「今日はあれを買って帰ろう」という小さなモチベーションを生む存在となっています。こうした商品開発・マーケティングの巧みさもあり、消費者はスイーツを単なる間食というより自分への投資や癒やしの儀式のように捉えるようになってきました。特に若い世代では、甘いものを食べることで「リラックスできる」「落ち着く」と答える人が9割以上にのぼり (スイーツとウェルビーイング「スーパー・コンビニ スイーツ白書 ...)、スイーツを食べること自体がウェルビーイング(幸福感)に直結するという認識が広がっています。つまり、現代のスイーツは安価に買える嗜好品であると同時に、心理的な満足を提供する重要なアイテムとなっており、このことが定番スイーツ商品の底堅い売上につながっているのです。
なぜ今、この傾向が顕在化したのか
以上のような市場動向と社会背景は徐々に進行してきたものですが、それが顕在化したタイミングが「今」である理由を考えてみます。大きな契機はやはり新型コロナウイルスの流行でした。2020年から始まったコロナ禍は、人々の生活様式と消費行動を劇的に変えました。巣ごもり生活によってスイーツ需要が喚起されたこと (スイーツ激戦期必勝法/決め手は情報誌の“連載”にあり! | 〖中広〗地域みっちゃく生活情報誌Ⓡ販促ブログ)、外出制限で余ったレジャー費がスイーツに振り向けられたこと、そして「いつ終わるか分からない不安」を紛らわすために日常的な甘いご褒美を求める心理が芽生えたこと—これらはすべてコロナ禍という特殊な状況下で生まれた現象です。そして2022年以降、コロナ禍が落ち着き社会活動が再開すると、人々はコロナ以前と以後の消費行動を組み合わせた新しい習慣を身につけるようになりました。その結果、「巣ごもり期間に覚えた日々のスイーツ習慣」がそのまま定着し、アフターコロナの世界でもスイーツ市場の底上げ要因として働いています。いわばコロナ禍で形成された需要が顕在化し持続しているのです。
またちょうど同じ時期に、物価高・実質所得の目減りという経済状況も進行しました。2022~2023年にかけて生活必需品の値上がりが相次ぎ、消費者の節約志向が高まる一方で、「たまの外食より日々のちょっとした楽しみ」を重視するマインドが強まったと考えられます。エンゲル係数(家計に占める食費割合)の上昇が報じられる中でも、スイーツへの支出は削られにくいようです。実際、2023年の菓子類支出が過去最高を記録したこと (グラフで見る! 菓子類の家計消費支出 1世帯当たりの年間消費支出額の推移〖出所〗総務省 家計調査)は、他の贅沢を我慢してでも甘いものを買う人が増えた現れとも解釈できます。「手の届くご褒美」で自分を労わるという行為は、コロナ禍の経験と物価高のストレスが掛け合わさった今だからこそ、広い共感を得ているのでしょう。さらに、メーカー側の戦略もタイミングよく合致しました。2023年前後にはコンビニ各社がスイーツ開発を強化し、老舗メーカーも定番ブランドに新フレーバーや高付加価値ラインを投入しています (ビスケット特集:ロッテ 「チョコパイ」大幅伸長 - 日本食糧新聞・電子版)。例えばチョコパイは食感や味わいを変えた新商品投入によりブランド全体を活性化させ、若年層にもアピールしました (ビスケット特集:ロッテ 「チョコパイ」大幅伸長 - 日本食糧新聞・電子版)。またドーナツブームの再燃など、市場に新鮮味を与えるトレンドがちょうど今起きています。こうした供給側の活発な動きと需要側のマインド変化が合流した結果、今このタイミングでスイーツ市場の成長が鮮明になったと考えられます。
おわりに: スイーツ市場の展望
チョコパイの売上好調に象徴されるように、定番スイーツ商品の市場は、社会環境の変化と人々の心の動きに支えられて成長を続けています。広義のスイーツ市場は依然拡大の余地があり、コンビニスイーツや市販菓子は生活に密着した「小さな幸せ」として定着しました。一方で洋菓子専門店の減少に見られるように、市場構造は変容しています。今後、少子高齢化による国内需要の先細りが懸念される中でも、スイーツが持つ「癒しとご褒美」の価値は大きく揺らがないでしょう。メーカー各社はその価値をさらに高めるべく、新たな商品提案や付加価値戦略を打ち出すと予想されます。消費者にとっても、スイーツは単なる嗜好品を超えて日常を彩る存在であり続けるはずです。チョコパイの成長要因を紐解いた本分析から浮かび上がるのは、経済状況やライフスタイルがどう変わろうとも、人々は手頃な甘い幸せを求めるという普遍的な真理かもしれません。そしてそのニーズに応え続ける限り、定番スイーツ市場には今後も明るい展望が開けていると言えるでしょう。
参考文献・出典:本稿では総務省「家計調査」データ【36】、日本食糧新聞【17】【11】、帝国データバンク調査【8】、PR TIMES調査【24】、モンテール「スイーツ白書」【12】等の情報を参照し、スイーツ市場の動向と背景要因を分析しました。