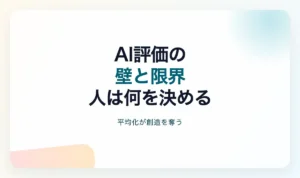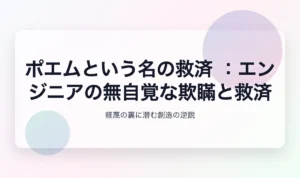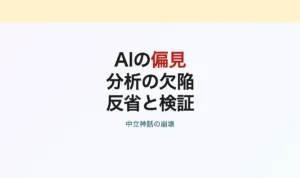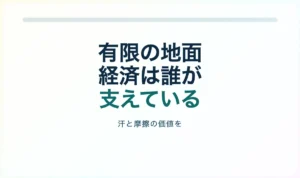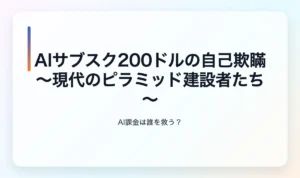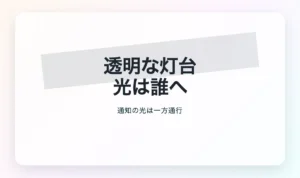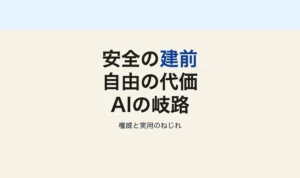参考記事:Google、「プライバシーサンドボックス」を実質終了 関連技術のほとんどを廃止へ - ITmedia NEWS
2019年、Googleは「Privacy Sandbox(プライバシーサンドボックス)」という壮大な理想を掲げた。
“ユーザーのプライバシーを保護しながら広告を最適化する”――そう聞こえはいい。
しかし、現実は単純だ。
「データの独占構造を再設計するための言い換え」にすぎなかった。
■ 序章:名目は「Cookieの終焉」
きっかけは、サードパーティCookieの廃止だ。
ブラウザがWeb上のユーザー行動を追跡する技術で、
これが長年、広告業界の血液のように使われてきた。
だが近年、「プライバシー侵害」として批判を浴びた。
Googleはそこで「Cookieに代わる安全な仕組みを我々が作る」と宣言した。
その名がPrivacy Sandboxである。
要するに――
「追跡は危険だ。だから追跡は我々が代わりにやる。」
という、信じ難い理屈だった。
■ 仕組みの正体:個人ではなく“群”を監視する
Sandboxの中核をなすのは、FLoC(Federated Learning of Cohorts)やTopics APIといった仕組みだ。
Cookieのように個人を特定する代わりに、
ユーザーの閲覧傾向から“興味グループ”をブラウザ側で形成し、
そのグループ情報を広告主に共有する。
つまり、「あなた」を追跡するのではなく、
「あなたが属する集団」を追跡するという話だ。
だが、これが欺瞞の始まりだった。
グループ情報は匿名化されているというが、
その分類に必要なデータ――閲覧履歴・アクセス時間・端末識別情報など――は、
依然としてGoogleの支配下にある。
匿名化の境界を決めるのもGoogle、
その処理を監査する手段もGoogleが握っている。
「安全」とは、Googleがそう言う限りの話だ。
■ 倫理の破綻:「知らない」と「管理する」は両立しない
プライバシーサンドボックスが抱えた根本的矛盾は、
“知らないふりをしながら支配する”という構造だ。
Googleは「個人を特定しない」と言いながら、
「広告最適化のためにユーザー行動を理解する」とも言う。
つまり、“理解しているが特定していない”という状態を維持しようとする。
だが、これは原理的に不可能だ。
理解できるということは、何らかの形で識別できているということだ。
もし本当に識別できないなら、そもそも広告最適化など成立しない。
Googleがやろうとしたのは、
「わかる範囲をわからないと言い張る」
という、政治的操作にすぎなかった。
■ 技術の仮面をかぶった権力
プライバシーサンドボックスが失敗したのは、技術の限界ではない。
倫理と論理の破綻だ。
広告主からすれば、Cookieの代替にGoogle依存が強まる。
ユーザーからすれば、「保護された結果」自分で何も制御できない。
つまりGoogleは、「自由なWeb」の中心に自分の裁定権を埋め込むことに成功していた。
これこそ、技術的支配の最も狡猾な形だ。
誰も鎖を見ない。鎖はアルゴリズムの形をしている。
■ 終幕:神のふりをした企業の終わり
2025年、Googleはプライバシーサンドボックスの関連技術のほとんどを廃止すると発表した。
「ブランドをやめるが理念は続ける」との言い訳を添えて。
だが実際には、これは敗北宣言だ。
すべての関係者――ユーザー、広告主、規制当局――が納得しない仕組みを、
いくら技術で飾っても通らなかった。
Googleは自らをWebの神として振る舞った。
しかし、神が全てを“管理”する世界に自由はない。
そして、自由のない世界で広告も経済も回らない。
彼らが崩れたのは当然の帰結だ。
知らないふりをした支配は、いつか必ず露呈する。
■ 自由は管理の外にしか存在しない
プライバシーとは、“他人に知られないこと”ではない。
“自分がどこまで知られたいかを決める権利”だ。
その権利を企業に預けた瞬間、自由は消える。
GoogleのSandboxは「安全な檻」を作ろうとした。
だが檻の中での安全は、外界を失うことと同義だ。
プライバシーは管理によって守られるのではない。
管理の外でしか、生き延びない。
それを証明したのが、Privacy Sandboxの終焉そのものだったのだ。