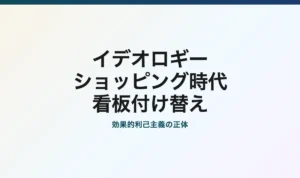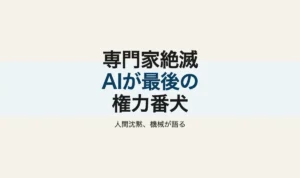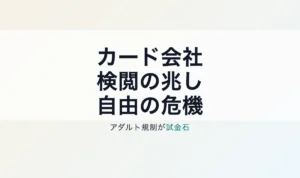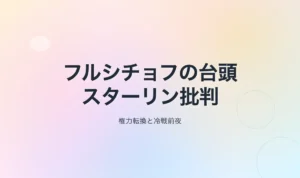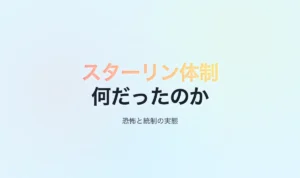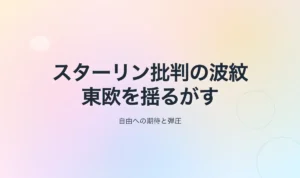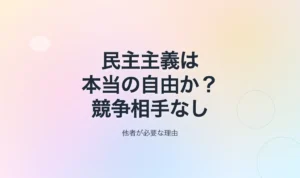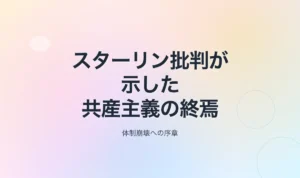スターリン批判を契機にソビエト連邦および共産圏は、表面上は変革の兆しを見せつつも、内部ではますます深刻な矛盾を抱えるようになった。1956年以降、体制の権威はかつてのような絶対性を失い、それを糊塗するためのイデオロギーやプロパガンダも徐々に説得力を失っていく。こうして、冷戦の構造そのものにも揺らぎが生まれる。
本稿では、スターリン批判後の共産主義体制に生じた矛盾の拡大と、それが冷戦全体に与えた影響を見ていく。
ベルリンの壁:自由の象徴か、体制の墓標か
1961年8月13日、東ドイツ政府は突如としてベルリン市内の東西境界線を封鎖し、物理的な壁を建設し始めた。これは、スターリン批判以降に加速した東から西への人口流出(特に若年層・知識層)を食い止めるための措置であった。
当時、ベルリンは冷戦の最前線であり、西側諸国の民主主義と自由経済が目の前に見える場所であった。東側住民にとっては、理想よりも現実が勝り、「この体制では未来がない」と考える人々が後を絶たなかった。ベルリンの壁は、社会主義体制が自らを守るために自由を封殺せざるを得なかったという矛盾の象徴である。
一方、壁の建設は西側諸国にとってプロパガンダの好材料となり、「共産主義は壁を作らなければ人々を繋ぎとめられない」という構図を世界に印象づけた。東西のイデオロギー対立は、ベルリンという都市の分断を通じてさらに鮮明となっていった。
キューバ危機:滅亡寸前のチキンレース
1962年10月、アメリカはキューバに配備されようとしていたソ連の核ミサイル基地を発見し、事態は一気に緊張を高めた。フルシチョフは、アメリカのトルコ配備核への対抗措置として、キューバにミサイルを置こうとしたのである。
これに対しケネディ政権は「隔離」と称する海上封鎖を実施し、ソ連の船団を実力で止めようとした。数日間、世界は核戦争の瀬戸際に立たされることとなる。
最終的にフルシチョフはミサイル撤去を決断し、アメリカも水面下でトルコのミサイル撤去を約束するという妥協が成立した。表面上は引き分けに見えるが、ソ連が後退した印象が強まり、フルシチョフの威信は著しく損なわれた。
キューバ危機は、ソ連にとって「軍事力による威圧が通用しない瞬間」でもあり、共産主義体制の攻勢が限界に達したことを露呈した出来事でもあった。
ブレジネフ時代の停滞と管理社会
1964年にフルシチョフが党内クーデターで解任されると、後継者レオニード・ブレジネフは一見安定した指導体制を築くが、それは管理と保守化による「見かけの安定」にすぎなかった。
経済政策は旧態依然の中央集権的な計画経済が続き、生産性は低迷。汚職と無責任体質がはびこる中で、「停滞の時代(スタグナーツィヤ)」と呼ばれる無気力な社会が広がっていく。国民はもはや理想を信じておらず、体制に従うのは恐怖でも信仰でもなく、単なる慣性でしかなかった。
また、この時代にはチェコスロバキアの"プラハの春"(1968年)という民主化運動が起こるが、これもソ連の軍事介入で粉砕される。ブレジネフ・ドクトリンにより、「社会主義陣営の逸脱は武力で是正される」という方針が世界に示され、東欧の改革への希望は絶たれた。
矛盾の蓄積と不可避の崩壊へ
こうして、スターリン批判以降に始まった「体制のほころび」は、完全には修復されることなく蓄積されていった。改革の兆しは軍事力によって潰され、自由への希求は裏切られ、国家は硬直化していく。しかも、西側との軍拡競争は経済を圧迫し続け、内部矛盾を加速させた。
スターリン批判は、共産体制が「誤りを認められる」と世界に示した最初の事件であったが、その後の歩みは誤りを認めながらも何も変えられないという無力さの証明となった。
この矛盾の連続こそが、最終的なソ連崩壊を呼び寄せる地盤となったのである。