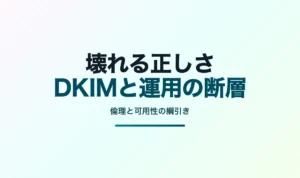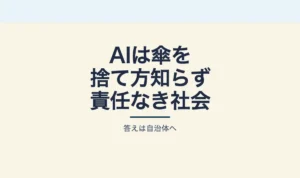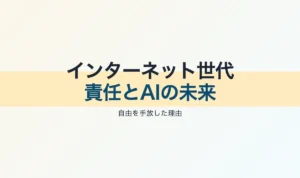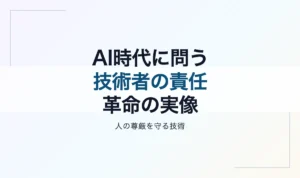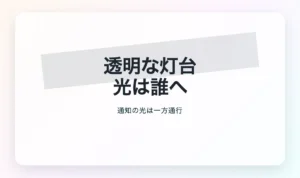「論理的に正しい」。この言葉の裏には、しばしば見落とされた“仮定”が横たわっている。
理系の論理思考は美しい。明示された前提、定義された語彙、演繹的な構造。そしてその体系の中で、必要条件と十分条件は厳格に区別され、論理は矛盾なく整然と構築される。しかしその構築物は、現実という地形にうまく接地できているだろうか。
科学者が社会に向けて発言するとき、往々にしてズレが生じる。「言っていないが、言ったも同然だ」「その発言は、そう受け取られても仕方がない」。科学者は驚く。自分は正しく語ったと信じているからだ。しかし、世間が受け取るのは「論理」ではなく「文脈」だ。その文脈には、当たり前のように、数式には書かれない“暗黙の仮定”が組み込まれている。
理系の人間にとって、この暗黙の仮定こそが最大の障壁となる。なぜなら、科学の対象である自然には、解釈がないからだ。重力は“だいたい”働くわけではないし、原子は“空気を読んで”振る舞うわけでもない。だからこそ科学は美しい。だが、人間社会はそうではない。そこには「文脈」と「解釈」と「意図」が渦巻いている。
専門化とは、縦に深く潜ることだ。その過程で、人は自らの専門言語を習得し、専門内の文脈に適応していく。しかし、その分だけ外部の世界との接続は失われていく。上に立つ者ほど、より高度に専門に最適化されており、専門外の話法や前提に対しては不寛容になる。これは単なる性格の問題ではなく、構造的な問題だ。
そして、悲劇はそこで起きる。
たとえば科学系のトップと行政系のトップが、言葉の使い方を巡って激しく対立した。「そんなことは言っていない」と言う科学者に対し、「言ったも同然だ」と受け取る行政官。どちらも、自らの論理体系の中では正しい。だが、すれ違っているのは論理ではなく、前提である。
このような局面で本当に必要なのは、両者の前提の違いを指摘できる“横断的な人間”である。だが現実には、そのような人材はほとんどいない。学問の世界は縦にしか掘られない。「横断的な学問」という看板も、実際には幅を持たせた縦の延長に過ぎない。真に横断的な知は、現場の摩擦の中からしか生まれない。
理系にとって、「不文律」や「空気」はノイズに等しい。だが人間社会においては、それらこそが前提であり、規範であり、時に論理以上の効力を持つ。そのギャップに目をつぶったまま、正しさを主張しても、社会はそれを受け止めきれない。
科学の言葉が社会に届くためには、翻訳が要る。そしてその翻訳は、単なる“やさしい日本語”ではなく、異なる前提と論理を理解し橋渡しできる能力である。その役割を果たす人がいなければ、専門家同士が言葉尻で争い続ける構図は今後も繰り返されるだろう。
論理とは構築物である。しかし、その構築物が立っている地盤こそが、我々が無意識に共有する「暗黙の仮定」である。その存在を見落とすことは、論理の成立そのものを危うくする。専門化が極まった現代にこそ、論理の地盤に目を向ける勇気が求められている。