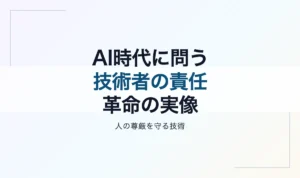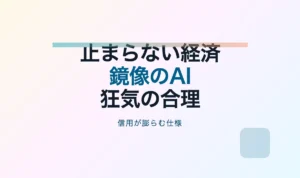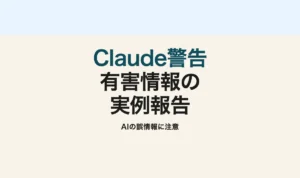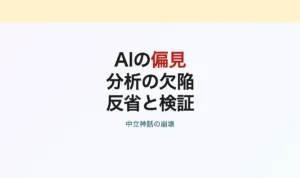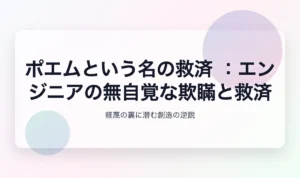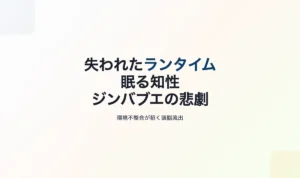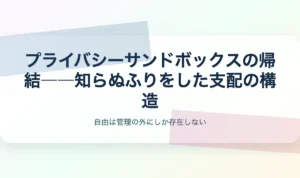デジタル化の奔流は、市民に力を与えると宣言されていた。情報へのアクセスは民主化され、手続きは簡素化され、ソフトウェアは人々の生活を支える道具になるはずだった。だが、その華やかな約束の裏側で、技術はいつの間にか別の重力に引かれていった。透明性という光を掲げながら、実際には片側だけを照らす歪んだ灯台のように。
ログイン通知が散弾のように飛び交う時代である。サービスは利用者の一挙手一投足を克明に記録し、その痕跡を過剰なほど通知してくる。まるで市民が行動するたびに、行動そのものを確認させる儀式を強いているかのようだ。だが、いざサービス側の動きになると、沈黙は厚い壁となる。申請の処理はどこまで進んだのか。内部の判断は下されたのか。サービスは何を行い、何を行わなかったのか。そこには何も記されない。光は利用者だけを照らし、サービスの内部は初めから存在しないかのように暗闇の中にある。
この非対称性こそが、現代の技術の正体を露わにする。ソフトウェアは本来、中立的で硬質な道具ではなかった。エンジニアは、かつて市民に力を返すことを誇りとしていた。技術を、人間の自由の拡張として信じていた。磁石が北を示すように、彼らの誇りは常に市民の側にあった。しかし巨大化したプラットフォームは、その磁場をひっくり返した。技術は市民の足元を照らす灯火ではなく、上位の都合を守る装置へと組み替えられた。
ログイン通知は「あなたが何をしたか」を照らすが、「彼らが何をしたか」は永遠に伏せられたままである。この構図は、透明性の仮面を被った責任回避そのものだ。何かあれば「通知しました」と言えるようにしながら、自らの行動は闇に沈める。通知の光は一方通行であり、見えるのは市民だけだ。技術が誇りを忘れたのではなく、誇りを発揮できる場所が制度の底に沈んでしまったのである。
デジタル化は確かに効率と速度をもたらした。しかしその対価として、技術が生む力の向きは一方向になり、市民の主体性を奪う構造が固定化された。ソフトウェアは権力の影を引き受け、エンジニアの理想はその影の中で薄れた。透明であるはずの技術が、最も肝心な部分にだけ幕を下ろしている。かつて市民の側にあった灯台は、いまや反対方向に光を投げかけている。