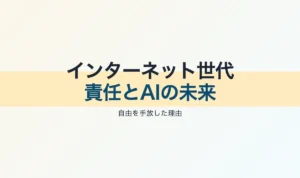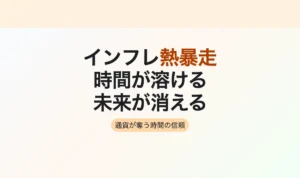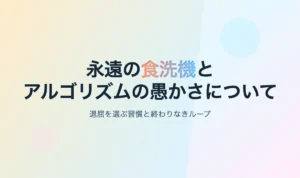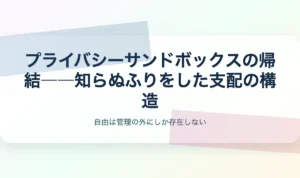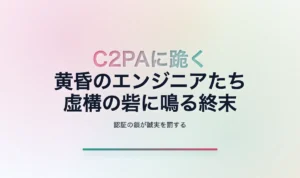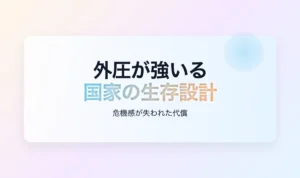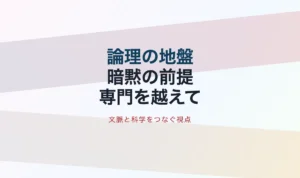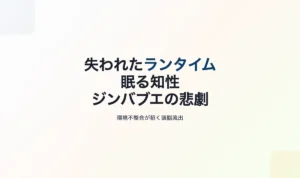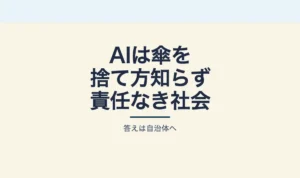
スマートフォンは確かに便利だ。しかし、本質的な解決を何もしていないように感じる。むしろ、社会を悪くしたとすら思っている。
この感覚は多くの人が共有しているのではないか。我々は技術的に進歩しているはずなのに、なぜか社会的には退化しているような気がする。なぜこのようなパラドックスが生じるのだろうか。
インターフェース革命という名の制約
スマートフォンは「インターフェース革命」と呼ばれた。しかし、それは本質的には制約の産物だった。
小さな画面、タッチ操作、バッテリー制限、アプリストア統制。これらの制約に適応するために、我々は機能を削減し、選択肢を狭め、自由度を下げた。「革命」と呼ばれたものは、実は制約への適応だったのではないか。
パソコン時代には複数ウィンドウで同時に作業し、ファイルシステムを直接操作し、自由にソフトウェアをインストールできた。スマートフォン時代には単一アプリ表示が基本となり、ファイルアクセスは制限され、アプリストア経由でしかソフトウェアを入手できなくなった。
進歩の名の下に、選択肢が削減されている。
本質的にできることは増えていない
1990年代にできたことを思い返してみよう。文書作成、表計算、プレゼンテーション、インターネット閲覧、メール、プログラミング、画像・動画編集。
2025年にできることは何か。文書作成、表計算、プレゼンテーション、インターネット閲覧、メール、プログラミング、画像・動画編集。クラウド化され、モバイル化され、AI支援が付いているが、本質的には同じことを違うインターフェースでやっているだけだ。
その間に失われたものもある。地図を読む能力、暗算能力、記憶力、集中力、対面コミュニケーション能力。技術は人間の能力を拡張するのではなく、代替し、結果として人間の能力を劣化させている。
責任転嫁の精巧化
現代の技術開発の大部分は、問題解決ではなく責任転嫁の精巧化に費やされている。
クッキーの同意ポップアップは何かできることを増やしただろうか。これは責任をユーザーに押し付ける儀式でしかない。拒否は実質不可能で、理解も不可能で、選択肢は見せかけだ。真の目的は法的責任の回避、「ユーザーが同意した」という証拠作りだ。
macOSをアップグレードすると大量に発生する許可待ちダイアログも同様だ。このダイアログによってユーザーは何をなしえるというのか。「許可」を押せばシステムが動き、「拒否」を押せばシステムが壊れる。選択権があるように見せかけて、実際は強制だ。
これらは偽の選択権による責任転嫁システムだ。ユーザーに「選択」させることで、企業側の責任を免除する。
セルフレジが示す責任の移譲
セルフレジは技術による責任転嫁の典型例だ。従来は店員がバーコードを読み取り、間違いがあれば店の責任だった。セルフレジでは客がバーコードを読み取り、間違いがあれば客の責任になる。
店のコスト削減と客の負担増加。エラー時の責任の曖昧化。そして、レシートを捨てる時に「店員に盗んだと咎められたらどう立証するんだろう」と考えなければならない心理的負担。
技術は問題を解決したのではなく、責任を転嫁しただけだ。
ゼロトラスト社会の形成
最近の技術トレンドに「ゼロトラスト」がある。ネットワーク内の全てを疑い、検証なしに信頼しない、常に認証・認可を求める。これは技術的な話というより、社会全体がそうなっているから技術にも求められて生まれたのではないか。
隣人の全てを疑い、客の全てを疑い、住民の全てを疑う。ゴミ袋を開封して個人特定し、セルフレジで客を監視し、過度なルール化で住民を統制する。
技術は社会の鏡だ。社会の信頼崩壊が技術設計思想に投影され、技術の実装が社会の不信をさらに増大させる。悪循環の完成だ。
暗号化文化の象徴性
ソフトウェア開発は暗号化の話ばかりしている。機能開発よりもセキュリティ対策、イノベーションよりもコンプライアンス、創造よりも防御。
暗号化はデータの機密性と通信の安全性を提供する。しかし、社会的信頼の欠如、責任の所在不明、システムの透明性不足は解決しない。暗号化への偏重は、技術で社会問題を解決しようとする発想の限界を表している。
技術的に問題を解決するのではなく、技術的に問題を隠蔽しているだけではないか。
統制の民営化
ユーザーに押し付けられない責任はそもそも禁止という方向に向かっている。コンテンツモデレーションといえば聞こえはよいが、やっていることは統制だ。
従来の政府による統制には制約があった。憲法上の制約、国会での議論、司法による違憲審査、選挙による政権交代。プラットフォームによる統制にはこれらの制約がない。私企業だから憲法の制約なし、議会の監視なし、司法審査なし、選挙による変更不可。
より効率的で強力な統制システムの完成だ。
そして、ネットワーク効果という現実のもと、ユーザーは自由にプラットフォームを選べるわけではない。「嫌なら他を使えばいい」は建前で、実際は代替不可能だ。友人・知人が全員そこにいて、データの蓄積があり、学習コストが発生している。移行は現実的に不可能だ。
偽の民主主義システム
現代の技術は「民主的に見える手続き」で「非民主的な結果」を正当化するシステムを構築している。
クッキー同意、利用規約、アプリ許可。これらは全て「ユーザーの選択」という形式を取るが、実質的な選択肢はない。同意しなければサービスを利用できない。理解不能な内容に「同意」を強要される。
技術的「民主主義」の形骸化だ。本来の民主主義は実質的な選択肢、十分な情報、選択の結果への責任を前提とする。技術的「民主主義」は形式的な選択肢、理解不能な情報、選択者への一方的責任転嫁を特徴とする。
インターネットの反転
インターネットは弱者の武器だった。しかし、今や強者が強権を振るう舞台となっている。
1990年代から2000年代前半、インターネットは個人をエンパワーした。参入障壁は低く、発信力は民主化され、技術的優位性があれば巨大企業を脅かすことができた。ポール・グレアムが「ビル・ゲイツは間違いなく君を恐れている」と書いた時代だ。
しかし、もうビル・ゲイツは個人の天才を恐れていない。恐れているのは同じレベルの巨大企業、イーロン・マスクやジェフ・ベゾスだ。個人はもはや脅威として認識されない。
ネットワーク効果の成熟、技術の複雑化、資本要件の激増、規制の複雑化。これらにより、参入障壁は決定的に高くなった。権力構造は完全に逆転した。
技術による社会問題の複雑化
技術は問題を解決するのではなく、問題を複雑化している。傘の捨て方という単純な問題が、技術の発達とともにより複雑で解決困難な問題になった。
情報はアクセスしやすくなったが、正しい判断はしにくくなった。つながりやすくなったが、信頼関係は悪化した。作業は楽になったが、責任の所在は不明確になった。
技術進歩がもたらすのは、表面的な利便性と、根本的な社会問題の深刻化だ。
責任なき技術の蔓延
現代の技術開発には「大いなる力と大いなる責任」という思想がない。巨大な影響力を持ちながら責任を取らない。GAFA的思考の典型は「プラットフォームだから責任なし」「ユーザーが勝手に使っている」だ。
行政システムも同様だ。市民生活を左右する影響力を持ちながら「システム仕様だから仕方ない」「業者が作ったものだから」と責任を回避する。
技術が責任回避を洗練させている。昔の責任回避は単純で見抜きやすかった。「知らない」「忘れた」「聞いていない」。現代の責任回避は技術的に精巧だ。「システムが」「アルゴリズムが」「データが」。
結論:進歩の幻想
我々は進歩しているように見えて、実は能力的に退化している。技術は人間の能力を拡張するのではなく、代替し、劣化させている。社会問題を解決するのではなく、複雑化し、見えにくくしている。
スマートフォンが社会を悪くしたという感覚は正しい。技術進歩が社会の根本問題—責任の回避、信頼の欠如、暗黙知の断絶—を反映・増幅しているからだ。
傘の捨て方がわからない社会から、何を考えるべきかもわからない社会へ。技術的進歩が民主主義的後退をもたらしている。
次回:第3部では、インターネット黎明期の夢を信じた世代として、なぜ我々は自由を明け渡してしまったのか、そしてAIで同じ過ちを繰り返さないためには何が必要かを考察する。