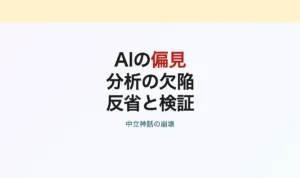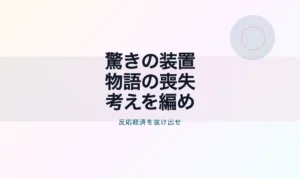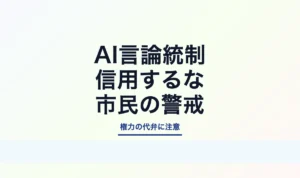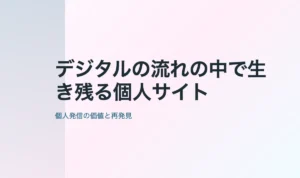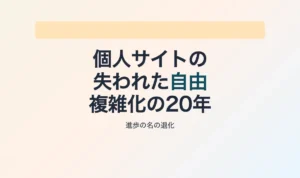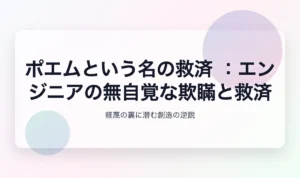技術が世界を変えるなどという言葉を信じたことはない。
技術は世界の鏡であり、世界が変わるときにだけ、その形を変える。
AIも同じだ。AIが虚構を作るのではない。虚構を基盤にした社会が、AIという虚構生成機械を必要としているのだ。
二十年前、インターネットは個人を解放するものだった。
誰もが学び、作り、発信できるという小さな革命の火が灯った。
しかしこの二十年、社会はその自由を丁寧に殺してきた。
アルゴリズムは人間の思考を標準化し、教育は手順書に還元され、職業は部品のように分解された。
人間が考えるという営みそのものが、効率の敵になったのだ。
その結果、社会は「目的」を失った。
何のために働き、何のために学び、何のために作るのか――。
答えを持つ者はいない。
目的が消えた社会では、技術だけが残る。
AIはその空白を埋める代用品となった。
「AIが世界を変える」と語る者たちは、未来を夢見ているのではない。
彼らはただ、空虚を恐れているのだ。
ドットコム・バブルの時代、人々は通信の革命を信じていた。
インターネットの普及は明確な実需に支えられていた。
だが今のAIバブルには、需要がない。
それでもデータセンターは建つ。
電力を喰い、土地を奪い、空調を鳴らしながら、
「いつか勝ち筋が見えるはずだ」と呪文を唱える。
まるで勝負の後にルールが決まる賭博のように。
彼らは賭けているのではない。群れで走っているだけだ。
なぜか。
皆が懸けるからだ。
皆が懸けるから、自分も懸ける。
そしてそれが続く限り、バブルは膨らみ続ける。
だが誰か一人が足を止めた瞬間、音もなく崩れる。
理由はいらない。止まることそのものが、破綻の引き金になる。
評論家たちは「勝者が勝つ」と言う。
だがその勝者が立っている地面はすでに沈んでいる。
勝敗を語る彼らの視野には、社会という土台が存在しない。
覇権ゲームの延長線上にしか未来を見ていない。
国家の財政が限界であることも、
資本の拡張が人間の生活を食いつぶしていることも、
誰も口にしない。
それを認めた瞬間、物語が終わるからだ。
AIは道具である。包丁と同じだ。
人を殺すことも、生かすこともできる。
それを決めるのは、使う者の意図である。
だが今の社会には、その「意図」がない。
だからAIは虚構を増幅する方向に流れていく。
意図なき技術は、方向を持たない暴力だ。
光ではなく、反射だけを増やしていく鏡の迷路である。
技術が世界を変えるのではない。
変わった世界が、技術の使い方を変える。
もし今後、この虚構が崩れたとき、
残るのはデータセンターでもAIモデルでもなく、
「何のために作ったのか分からない」という沈黙だけだろう。
そして、その沈黙の中でようやく、
人は技術をもう一度“手段”として取り戻すのかもしれない。