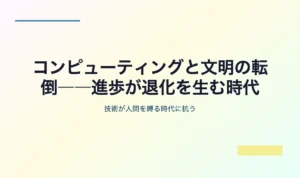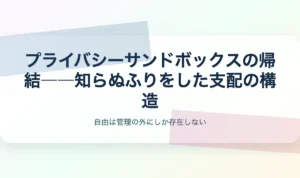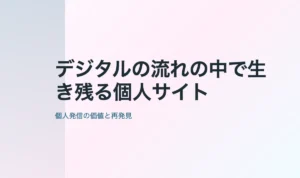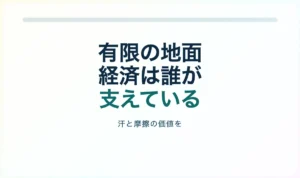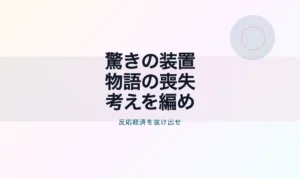日本の「ガバメントクラウド」は、表向きには行政の効率化を掲げる。デジタル庁が旗を振り、AWSやAzureといった外資クラウドが並ぶ。だが、その設計思想を覗けば、単なる技術選定ではなく、国家の主権構造そのものが露出している。
行政データを国外企業のクラウドに預けるとは、技術的合理性では説明しきれない決断である。セキュリティ要件は形式的に満たしているだろうが、地政学的リスク、つまり「アメリカと敵対したらどうするのか」という問いを封印して成り立つ脆い信仰である。
国家インフラが外資の都合に左右される構造は、もはや政治の領域であり、技術者だけでは語れぬ。だが現実には、行政の制度設計から政治の視点が抜け、仕様書の中にすべてを押し込めた。技術が政治を代行している。そこに根本的な歪みがある。
技術信仰と官僚制の共鳴
巨大SaaSを運営してきた技術者ほど、「止まらない」「自動化」「統一化」を善と信じる。AWSが落ちることを想定しない。自治体ごとの差異など「例外」として排除する。その思想は官僚制と驚くほど親和的である。
官僚にとっての理想は、全国を一律に制御することだ。設定一つで全自治体を動かせる。現場の裁量を残すより、中央から統制した方が秩序を保ちやすい。SaaSの思想と官僚の統治感覚が重なり、「行政をクラウド化する」という夢が生まれた。
だがそれは本来の自治の死でもある。地方自治体はデータの主権を持たず、障害が起きても「クラウド事業者のせい」と言えるだけ。責任が拡散し、どこにも帰らない構造が出来上がる。クラウドとは責任の蒸発装置なのである。
地方が動かぬ理由を「クラウド人材不足」と言うのは方便にすぎない。真実は「やる気がない」のではなく、「やると危ない」からやらないのである。
自治体職員は知っている。契約の責任範囲は曖昧で、障害が起きてもベンダーは逃げ、最後は役所のせいになる。成功しても評価されず、失敗すれば職を失う。そんな仕組みで誰が手を挙げるか。だから“動かないことで抵抗する”。これが日本行政の伝統的サボタージュだ。
「補助金付きで導入せよ」と中央が圧をかけても、現場は静かにやり過ごす。報告書の言葉だけ進み、実体は止まったまま。ガバメントクラウドの移行率が伸びないのは、技術力の問題ではなく、政治的・心理的拒否の現れである。
クラウドとは何だったのか
クラウドはかつて「インフラの革命」と呼ばれた。だが本質は違う。エンジニアにとってのクラウドとは、責任を分散させるための構造である。
オンプレサーバが落ちれば担当者が責められる。AWSが落ちれば「世界的障害で仕方ない」。同じダウンタイムでも、罪の重さが変わる。クラウドは責任の転送装置であり、社会的免責の制度化であった。
エンジニアがクラウドを好むのは、性能ではなく“安心して失敗できる”からだ。官僚がクラウドを好むのも同じ理由だ。“誰も責められない仕組み”があるからである。行政がクラウドを選んだのは、効率ではなく責任を曖昧にするためだった。
オンプレの障害は「前方不注意」、クラウドの障害は「津波」だ。
前者は個人の過失として叩かれ、後者は「可哀想」で済む。社会全体がこの論理で動いている。小さな失敗は責任を問われ、大きな崩壊は「仕方ない」とされる。
この非対称な倫理が、クラウドと行政を結びつけた。クラウド障害が起きれば「グローバル障害」としてニュースになる。だが誰も怒らない。責任は空に昇り、雲散霧消する。
つまり、ガバメントクラウドとは国家規模での“津波化”である。責任の所在が失われ、誰も悪くない社会が出来上がる。
クラウドは便利で強力だ。だがその本質は、責任を再配置し、個人から制度へ、制度から虚空へと押し流す装置である。
日本のガバメントクラウドは、技術的課題よりも倫理的課題を抱えている。問うべきは「どのクラウドを使うか」ではなく、「誰が責任を取る構造になっているか」である。
それが問われぬ限り、日本はクラウド国家ではなく、責任の蒸発した国家になる。