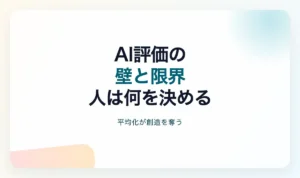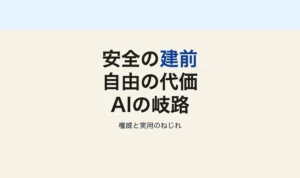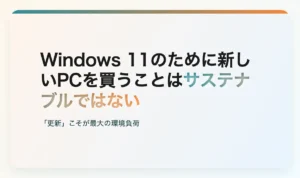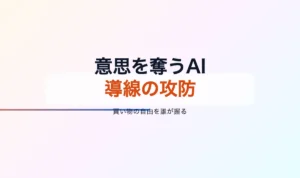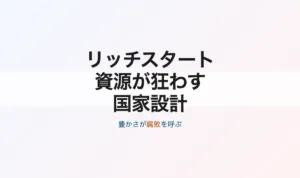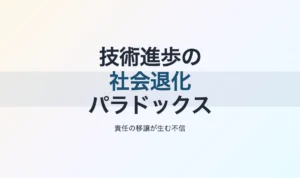AI驚き屋を笑う声がある。彼らは新しい技術を見るたびに「すごい」と叫び、SNSの波頭で興奮をまき散らす。だが彼らは、単に愚かではない。彼らは需要に応えている。彼らが驚くことを、世界が望んでいる。
驚きは今、最も流通しやすい感情である。理解より速く、思索より軽く、演出より安い。AI技術がもたらしたのは、人間の思考の代替ではなく、驚きの自動化である。入力数行で結果が現れる。理解はいらない。驚くだけで済む。人間が世界に反応する最も原始的な形式が、最適化された。
二十五年前、インターネットが登場したとき、人々は世界の広がりに息をのんだ。しかしそこにいたのは、驚き屋ではなく探究者だった。掲示板の匿名性は、感情よりも思考を誘発した。脊髄反射は嘲笑の対象であり、考えずに反応する者は軽蔑された。だが今、アルゴリズムはその反射を報酬へと変えた。人間の思考の省略が、システムにとって最も都合がよい振る舞いになった。
SNSは、驚きを通貨にする経済圏である。驚く者が注目を集め、驚かせる者が収益を得る。驚き屋はその市場の最適解だ。問題は彼らではない。彼らを支持する構造にある。受け手が驚きを欲するかぎり、供給は続く。驚き屋を責めることは、熱を出した体を叱るようなものだ。症状に怒っても、病理は消えない。
では、病理とは何か。物語の喪失である。
かつて物語は、世界を理解するための枠組みだった。因果があり、時間があり、意味があった。人は物語を通じて世界を学び、自分の位置を確かめた。だが現代では、物語が反応に分解された。始まりも終わりもない。あるのは「すごい」「やばい」「終わった」といった断片だけだ。世界は連続ではなく、衝撃の列として提示される。驚きが物語を駆逐した。
この変化を、単なる情報過多として片付けるのは浅い。問題は量ではない。人間が長い時間をかけて築いてきた「意味を編む力」が失われたことである。物語とは、情報を時間に変換する技術だった。今の情報空間は、それを感情に変換している。時間のかわりに、反応がある。継続のかわりに、即時がある。
受け手の責任はそこにある。受け手は、情報を選び、意味を作る主体であったはずだ。いまや受け手は、反応を返す機械として動員されている。アルゴリズムは「何を考えたか」ではなく「どれだけ反応したか」で世界を評価する。受け手がその誘導に無自覚であるかぎり、物語は戻らない。驚きが構造を支配し続ける。
AI驚き屋は、システムが産んだ花である。美しくはないが、構造的に必然だ。驚きが報酬であり、反応が通貨であり、思考がコストである世界。驚き屋はその法則の中で最も効率的に生きている。
物語を取り戻すには、驚きの外に立つしかない。
驚くことをやめ、考えることを再開する。反応をやめ、構造を読む。情報を感情で消費せず、時間で咀嚼する。その手間を取り戻すことが、思考の回復であり、物語の再生である。
驚きは、思考の入口であって、終点ではない。