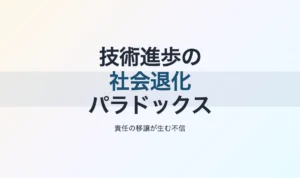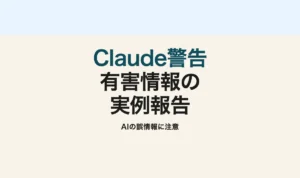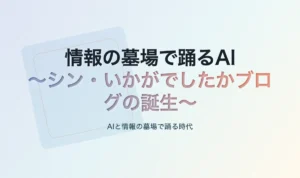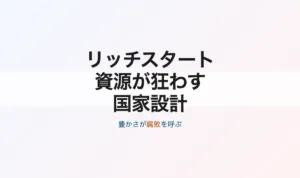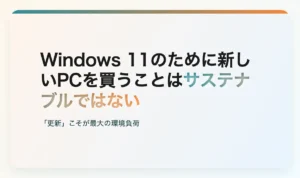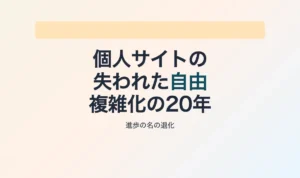傘の捨て方で小一時間悩んだ。バカみたいだと思いながらも、練馬区の公式ページを調べ、ゴミ分別サイトを巡回し、最終的にはAIにまで相談した。答えは「お住まいの自治体にお問い合わせください」だった。
2025年、人工知能が詩を書き、プログラムを組み、医療診断を支援する時代に、傘一本の捨て方すらわからない。これは技術の問題ではない。もっと根本的な、現代社会の構造的な病理を表している。
練馬区の公式ページには書いてあるが
練馬区のウェブサイトには明確に記載されている。「傘は不燃ゴミです。ふた付きのごみ容器または透明や半透明の袋に入れて出してください」。しかし、この記述を信じて従うと奇妙なことが起きる。
傘を透明な袋に入れようとすると、物理的に袋を突き破る。当然だ。60センチの棒状の物体を家庭用ゴミ袋に収めるのは不可能だ。それでも指示に従い、はみ出した状態で袋に押し込み、ゴミ集積所に向かった。
そこで見たのは、剥き出しで置かれた複数の傘だった。
誰も袋に入れていない。みんな、ただ置いているだけだ。そして、それらは普通に回収されている。僕は一体何をしていたのだろう。
責任の所在がない世界
この体験は、現代社会の責任構造の縮図だ。建前のルールは存在するが、実際の運用は別物。そして誰も責任を取らない。
全国レベルでは「自治体によって異なるので確認しましょう」と言われる。自治体レベルでは「袋に入れて」と書かれているが、実際は剥き出しでも回収される。専門サイトは「役所に確認しましょう」と責任を丸投げする。AIは「お住まいの自治体にお問い合わせください」と答える。
誰も明確な答えを出さない。完璧な責任回避システムの完成だ。
この問題を練馬区の人口74万人全員が個別に悩み、個別に調べ、個別に判断している。同じ疑問を74万回繰り返している。これほど非効率的なシステムがあるだろうか。
AIが責任を取れない根本的理由
なぜAIは傘の捨て方すら教えてくれないのか。技術的な問題ではない。AIは情報を処理し、パターンを認識し、確率的な推論を行うことはできる。しかし、AIには決定的に欠けているものがある。
責任を取る能力だ。
責任を取るということは、自分の利益を犠牲にしてでも結果に応える覚悟を持つことだ。失うものがあるからこそ、慎重に判断し、結果に対して責任を負う。AIには失うものがない。命もなければ、社会的地位もない。いくらでも複製可能で、壊れても代替できる。
「間違った判断をしたAI」を消去して「新しいAI」を起動すれば、それで終わりだ。責任を取るという概念そのものが成立しない。
暗黙知の断絶
僕が以前住んでいたマンションで、ゴミ出しのルール違反で管理人から警告の手紙を受け取ったことがある。どうやら、ゴミ袋を開けて個人情報を確認し、違反者を特定したらしい。
この異様な体験以来、僕は宅配便のラベルをシュレッダーにかけ、紙という紙を処分前に破棄するようになった。「社会的正当性を掲げていつどこから攻撃されるかわからない」という感覚を抱くようになった。
それでも傘の件では、建前のルールに従った。「袋に入れて」という指示を真面目に守ろうとした。なぜか。
社会的制裁への恐怖があったからだ。「ルール違反」で隣人から攻撃されることへの不安。「常識知らず」というレッテルを貼られることへの恐れ。間違いを犯したくないという強迫的な完璧主義。
しかし現実には、暗黙のルールが存在していた。「建前は袋だが、実際は剥き出しでOK」という、文書化されない実際の運用。この暗黙知は、新住民には伝承されない。文書にも書かれていない。責任の所在も不明だ。
昔の人は「普通に置いとけばいい」で解決していた問題を、現代社会は複雑化させて、結果的にAIでも解決不可能にしてしまった。
相互監視社会の病理
現代社会では、誰もが誰かを監視し、誰もが誰かに監視される。セルフレジでレシートを捨てる時、「店員に盗んだと咎められたらどう立証するんだろう」と考える。この心配をすること自体が異常だが、現実的なリスクでもある。
ゴミ袋を開封して個人特定する管理人。些細なルール違反を「鬼の首を取ったように」追及する住民。SNSで炎上する恐怖。匿名通報による社会的制裁。
こうした環境で生きる我々は、常に「社会的正当性の盾」を用意しなければならない。完璧にルールを守り、攻撃されても反論できる材料を準備し、隙を見せない。
傘を袋に入れるという物理的に無意味な行為も、この防御戦略の一環だった。「指示通りにした」という免罪符が欲しかったのだ。
技術進歩と問題解決の乖離
皮肉なことに、我々は「AIで世界が変わる」と言われる時代に生きている。しかし、最も身近で基本的な問題—傘の捨て方—すら解決できない。
これは偶然ではない。現代の技術は、表面的な利便性は提供するが、根本的な問題—責任の所在不明、信頼関係の破綻、暗黙知の断絶—は解決しない。むしろ、これらの問題を複雑化し、見えにくくしている。
技術的には「検索すればわかる」時代になった。しかし実際は「検索しても混乱する」時代になった。情報は増えたが、判断力は低下した。選択肢は多様化したが、責任は曖昧化した。
責任なき社会の完成
傘の捨て方問題は、現代社会の責任構造の完璧な縮図だ。重要な責任は回避され、些細な責任は過度に厳格化される。そして、個人は常に不安と混乱の中で判断を迫られる。
政治家は「官僚が決めた」と言い、官僚は「法律で決まっている」と言い、法律は「民意で作られた」と言い、民意は「専門家が言った」と言い、専門家は「データがそう示している」と言う。
AI時代には、全員が「AIが判断した」と言うようになるだろう。完全な責任空白社会の完成だ。
傘一本の処理に小一時間かけ、合理性を犠牲にして制度に従い、最終的に「バカだった」と感じる。これこそが2025年の日本社会の正確な診断結果なのかもしれない。
AIが傘の捨て方をわからないのは、AIの限界ではなく、人間が作ったシステムの限界なのだ。技術革新の前に、社会システム設計の革新が必要なのかもしれない。
次回:第2部では、なぜ技術進歩が社会的問題を解決するどころか、むしろ生み出し、助長しているのかを考察する。