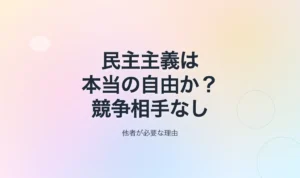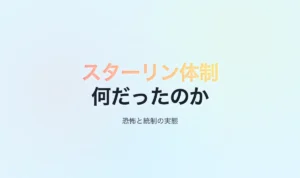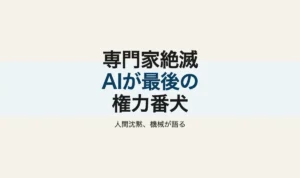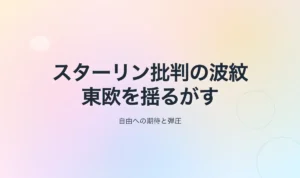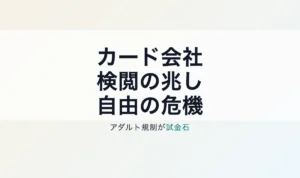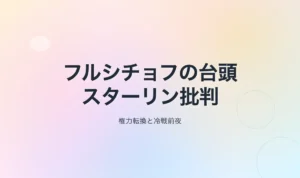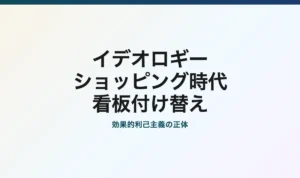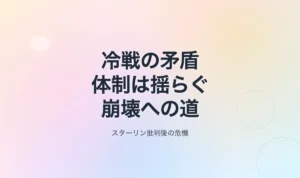1956年、フルシチョフが行ったスターリン批判は、共産主義体制内部から発せられた最初の「異議申し立て」であり、それはやがて体制全体を揺るがす転換点となった。彼の演説は、形式上は一指導者の過ちを認めるものでありながら、その実、共産主義体制が内包する矛盾と限界をあぶり出した告白に等しかった。
最終回となる本稿では、スターリン批判が共産主義国家の正統性に与えた傷と、その後の歴史への影響を振り返る。
絶対的権威の失墜
スターリン体制下では、「党の誤り」や「指導者の失敗」は原則として存在し得なかった。共産党は常に正しく、指導者は常に英明であるとされた。しかし、フルシチョフのスターリン批判はこの前提を覆した。
つまり、「共産党も誤る」「英雄も暴君になり得る」という認識を、共産主義の中枢から発信したこと自体が、体制の絶対性に致命的なひびを入れたのである。以後、ソ連も衛星国も、かつてのような道徳的優位性や歴史的必然性を掲げることが困難になった。
この「自己否定の論理」は、体制維持にとってはきわめて危険な毒でもあった。
体制の綻びと民衆の覚醒
スターリン批判を受けて、民衆は一斉に自由化を期待した。東欧各国では改革や民主化を求める声が噴出し、それはハンガリー動乱やプラハの春といった武力鎮圧を招くこととなる。つまり、希望を与えた一方で、その希望は実力で踏みにじられるという冷酷な現実が露呈した。
一方、ソ連国内でも、言論の自由や歴史の再評価を求める知識人の活動が増加し、「雪解け」の空気が生まれた。しかしそれもまたブレジネフ時代の保守化で封じ込められ、真の改革には至らなかった。
スターリン批判は「可能性」を示したが、「実現」を伴わなかった。それゆえに、人々の間には深い幻滅と不信が残ることとなった。
国際共産主義運動の信用失墜
西側諸国の共産主義者たちにとっても、スターリン批判は激震だった。多くは理想として共産主義を信じ、ソ連をその具現と見なしていたが、フルシチョフの暴露はその前提を根底から覆した。
「労働者の楽園」「抑圧なき社会」といったイメージは急速に崩れ、知識人層や学生運動の中でも離反が続出。共産主義は、もはや新時代の希望ではなく、冷酷な現実の象徴へと転化していった。
また、毛沢東がスターリン批判に猛反発したことにより、ソ連と中国の対立も決定的となり、国際共産主義は完全に分裂。「ひとつの共産主義」ではなく、「分裂した理念の残骸」としての共産主義が露わになっていく。
終わりの始まりとしてのスターリン批判
スターリン批判は、共産主義体制の自己修正を試みた第一歩であった。しかし、制度としての硬直と、支配者層の保身、そして改革に伴う混乱への恐れが、それを本質的な変革へと導くことを阻んだ。
結果として残されたのは、誤りを認めながら変わることのできない体制であり、それは次第に国民からも、国際社会からも信頼を失っていった。
ソ連の崩壊は1991年だが、その地盤沈下は1956年のスターリン批判から始まっていたと見ることができる。共産主義は、敵からではなく、内部の「正直さ」から崩れ始めたのだ。
スターリン批判は、革命の子が自らの親を裁いた瞬間であり、同時にその子自身が生き延びられないことを示した悲劇的な証言でもあった。