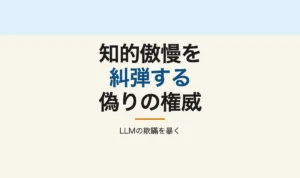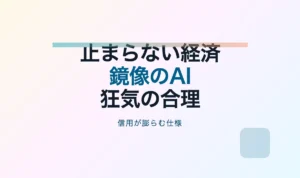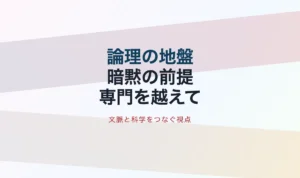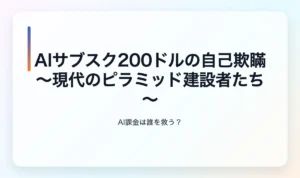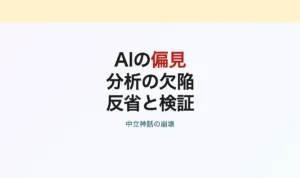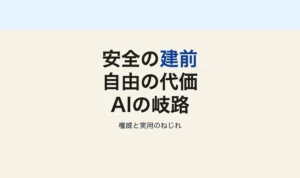「AI革命」という言葉が飛び交う現代において、私たちは本当に革命の只中にいるのだろうか。技術の進歩を礼賛する声が高まる一方で、現実の生活に目を向けると、閉塞感や格差の拡大、将来への不安が蔓延している。
本稿では、過去の技術革命を振り返りながら、現在のAI技術ブームが本当に人々を幸福にするものなのか、そして技術者として何を考えるべきなのかを探る。
「革命」とは何か:言葉の重みを考える
易姓革命と Industrial Revolution
私たちが「革命」と聞いて思い浮かべるのは、フランス革命やロシア革命のような体制転覆だろう。これは中国古代の「易姓革命」の概念に近い——天命が革まり、王朝そのものが交代する血なまぐさい変化である。
一方、Industrial Revolution(産業革命)の「革命」は、もともと天文学の「回転」を意味する言葉から派生した、より軽やかな概念だ。現代日本語の「革命」は、明治期にrevolutionの翻訳語として「革命」という重い漢語を当てたものである。
この言語的な重みの違いは重要だ。私たちは「AI革命」と聞くとき、無意識に「易姓革命」的な根本的変化を期待しているかもしれない。しかし実際に起きているのは、既存の権力構造を強化する「技術的変化」に過ぎないのではないか。
真の革命の3要素
歴史を振り返ると、本当に社会を良い方向に変えた技術革命には共通する特徴がある:
- 全員を豊かにする:車の大量生産のように、技術の恩恵が広く行き渡る
- 格差の是正:初期のインターネットのように、情報アクセスの格差を縮小する
- 下剋上:新しい技術によって、既存のエリート層とは異なる人々が力を持つ
この基準で現在のAI技術を見ると、むしろ既存の格差を拡大し、大手テック企業だけを豊かにしているように見える。これは「革命」ではなく、単なる「技術的変化」かもしれない。
産業革命から学ぶ:技術が人を不幸にした時代
初期産業革命の暗部
産業革命というと技術の勝利として語られがちだが、初期の数十年間は確実に多くの人を不幸にした。工場労働者は長時間・低賃金で働かされ、職人の技術は機械に置き換えられ、都市にはスラム街が形成された。
興味深いのは、大量生産によって綿織物が安く作れるようになったにも関わらず、なぜ労働者の生活が悪化したかという点だ。答えは単純で、作られた製品の大部分は植民地に輸出され、労働者自身は自分が作ったものを買うことができなかったからだ。
フォードの転換点
転換点となったのは、ヘンリー・フォードの「日給5ドル」政策だった。フォードは労働者の賃金を倍増させ、彼らが自社の車を買えるようにした。これにより「大量生産→大量消費」の好循環が生まれ、技術の恩恵が広く行き渡るようになった。
重要なのは、フォードが作ったのは人々が心から欲しがる「車」だったということだ。移動の自由という根本的なニーズに応えるものであり、誰かに「必要だ」と言い聞かされたものではなかった。
経済学の非人間性:リカードの比較優位論
人間をEC2インスタンス扱いする理論
産業革命期に生まれたリカードの比較優位論は、自由貿易の理論的基盤となった。イギリスとポルトガルが毛織物とぶどう酒を分業すれば双方の利益になる、という有名な例がある。
しかし、この理論には重大な欠陥がある。労働者が「100人」「90人」という数字として扱われ、まるでクラウドのEC2インスタンスのように自由にattach/detachできる前提になっている。
現実の人間には家族があり、技能習得に時間がかかり、地域への愛着がある。ぶどう酒を効率的に作ることよりも、職人としての誇りや安定した生活の方がはるかに重要だ。この理論の非人間性は、現代のグローバル化やAI置き換え論にも通じている。
情報革命の光と影:荒野から高層ビルへ
市井の人々が切り開いた荒野
情報革命は他の技術革命と異なり、最初から市井の人々が主導した。大学や研究機関、個人が自発的にインターネットを育て、Webサイトやメールが普及した。これは確かに「荒野を切り開く」感覚があった。
初期のインターネットは
- 個人がメディアを持てるようになった(Webサイト)
- 距離の制約を超えてコミュニケーションできるようになった(メール)
- 地方と都市の格差が縮小した(通販)
これらは確実に人々の生活を豊かにした。
資本主導への変質
しかし2010年代以降、情報革命は産業革命化した。GAFAMのようなプラットフォーム企業が市場を独占し、アルゴリズムによって人々をコントロールするようになった。かつての「荒野」は「高層ビル」に変わった。
そして現在のAI技術は、完全に資本主導でスタートしている。巨額のGPU投資が必要で、個人では到底参入できない。これは情報革命の初期のような民主的な可能性を欠いている。
現代の閉塞感:喋る冷蔵庫の時代
必要なものは揃っているのに
現代社会のパラドックスは、物質的には豊かになったにも関わらず、多くの人が閉塞感を感じていることだ。冷蔵庫、車、スマートフォンなど、生活に必要なものは一通り揃っている。
問題は「一通り揃った後」に起きる。経済システムは回り続けなければならないが、作るべき必要なものがない。そこで「喋る冷蔵庫」——本質的には不要だが、技術的に可能だからという理由で作られる製品——の時代が始まる。
iPhoneとステータス消費
子供が「いじめられるからiPhone が欲しい」というのは、まさに「喋る冷蔵庫をステータスとして欲しがる」現象だ。本当に必要なのは通話とメッセージ機能(冷蔵庫機能)だけなのに、ブランドロゴ(喋る機能)のために高額な代金を払う。
そして、そのiPhoneで子供たちがやることは、射幸心を煽るPay to winゲームだ。技術が人を幸せにするどころか、依存と搾取の道具になっている。
失われた時間と尊厳
現代人が本当に飢えているのは食べ物ではない。失われているのは
- 料理を楽しむ時間
- 家族や友人との深いつながり
- 意味のある仕事への尊厳
- 将来への希望
技術が発達したにも関わらず、むしろこれらが奪われている。多くの人が「喋る冷蔵庫」を作ることに時間を費やし、本当に大切なもの——健康、尊厳、希望——を失っている。
AIイラスト問題にみる構造的課題
技術的に可能 ≠ 社会的に望ましい
AIがイラストレーターの代わりをするという話は、現代の技術問題を象徴している。技術的には可能だが、社会的には
- イラストレーターの仕事を奪う
- でもイラストレーターの作品に依存している
- 新しい価値は何も生み出していない
これに対するイラストレーターの反発を「ラダイト運動」と揶揄する向きもあるが、19世紀の織工と同じで、生活を脅かされる人々の反応として当然だ。
私自身、最初はAIでブログのアイキャッチ画像が作れると肯定的に捉えていたが、よくよく考えるとアイキャッチ画像自体が不要だった。GoogleなどのSEO要件で「必要だということにされた」だけで、本当は誰も求めていない。不要なものをAIで作れるようになったといって、それが何だ?
技術者として何をすべきか
AI礼賛からの脱却
技術者として重要なのは、「AI革命素晴らしい」という流れに安易に乗らないことだ。喋る冷蔵庫の脳をAIにしたところで、冷蔵庫が気の利いたジョークを言うだけだ。根本的な意味はない。
むしろ問うべきは
- これは本当に必要なものか?
- 人間の尊厳を損なわないか?
- 既存の問題を解決するか、新しい問題を作るか?
本当に必要なものに向き合う
技術者が取り組むべきは
- 崩壊しかけたインフラの修復
- 医療、教育、介護など人を直接助ける分野
- 複雑化したシステムをシンプルにすること
- 人間らしい生活を支える道具作り
これらは「革新的」でも「スマート」でもないかもしれないが、確実に人々の生活を支えている。
時間と知恵を取り戻す
現代社会の問題は、必要なモノが不足していることではない。それらを活用する時間と知恵が奪われていることだ。技術は本来、人間に時間的余裕をもたらすはずだった。
技術者として、人々が料理を楽しみ、家族と過ごし、学び、創造する時間を取り戻せるような技術を作ることが重要だろう。
おわりに:閉塞感の中で
問題は見えているが、解決策は簡単ではない。フォードのような劇的な転換点がすぐに見つかるわけでもない。
しかし、技術者が「技術的に可能だから良い」という思考から脱却し、「人間にとって本当に価値があるか」を問い続けることが、変化の第一歩になるかもしれない。
現代人が求めているのは、より高性能な喋る冷蔵庫ではない。健康で、尊厳があり、希望を持てる生活だ。技術はそのための道具であって、目的ではない。
私たち技術者は、この原点に立ち返る必要がある。AI技術の可能性を探るとしても、同時にそれが本当に人々を幸せにするのか、常に問い続けなければならない。サンフランシスコの高層ビルから聞こえる「革命」の声ではなく、地上で生活する我々の声に耳を傾けたい。技術に本当に価値があるとすれば、その中にしかない。