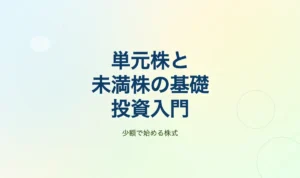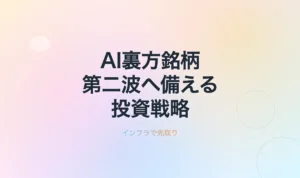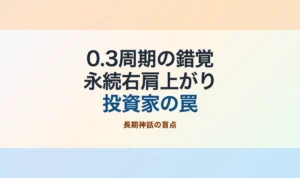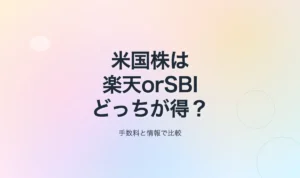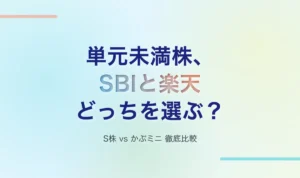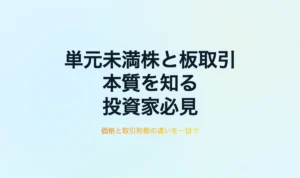参考
安心の代名詞だった特定保管に何が起きているのか
「特定保管だから安心」「あなたの金はあなたのもの」──こんな謳い文句で多くの人が始めた純金積立に、いま重大な変化が起きています。2025年12月16日から田中貴金属の純金積立サービスで実施される新ルールは、特定保管制度の根幹を揺るがす内容となっています。
特定保管とは、預けた金の所有権が利用者にあることを法的に担保する仕組みです。業者が破綻しても顧客の資産は保護され、いつでも現物として引き出せる──これが制度の大前提でした。しかし今回の変更により、この前提が根底から覆されようとしています。
変更の内容を端的に表現すると、12月16日以降に口座を解約した場合、現物の金やプラチナを引き出すことができなくなり、強制的に現金化されてしまうというものです。これまで当然のように行えていた「自分の金を現物で受け取る」という行為が、解約という手続きを経た途端に不可能になってしまうのです。
契約の巧妙な仕組みが生み出す合法的な権利剥奪
この変更が法的に可能な理由は、契約構造の巧妙さにあります。利用者は確かに金の所有権を持っていますが、同時にその金を預け入れや引き出しする際には業者の約款に従うという契約にも同意しています。約款には「社会情勢の変化に応じてルールを変更することがある」という条項が含まれており、今回の変更はこれに基づいた法的に正当な手続きとされています。
さらに問題となるのは、解約という行為の法的解釈です。12月16日以降、解約手続きは単なる契約終了ではなく「所有している金やプラチナを田中貴金属に売却し、代金として現金を受け取ることに同意する」という積極的な意思表示とみなされることになります。つまり解約を選んだ瞬間に、利用者は自らの意思で金の所有権を手放し、現金を受け取ることに同意したと法的に解釈されてしまうのです。
この仕組みを分かりやすく例えるなら、自分の所有物が他人の敷地にあって、それを取りに行くには相手の決めたルールに従わなければならない状況です。そして「これは確かにあなたのものですが、渡すときにはいったん私にこれを売ってもらう必要があります。価格は私が決めます」と言われているようなものです。
特定保管制度の実質的な骨抜き化
このルール変更により、特定保管制度は実質的に意味を失ったと言えるでしょう。特定保管の最も重要な価値は「いざという時に現物を受け取れる安心感」にありました。しかし現在の仕組みでは、まさに現物が必要になる金融危機やインフレの状況で、慌てて解約すると現金しか受け取れなくなってしまいます。
これは価値保存という目的を完全に破綻させるものです。利用者は価値を保存するために金やプラチナの現物との交換を前提に手数料を支払っているにも関わらず、最も重要な局面で現金化を強制されてしまうのです。しかも現金化の価格は業者側が決定するため、利用者には選択の余地がありません。
さらに深刻な問題として、現物引き出しに対する様々な制限が段階的に強化されてきた経緯があります。2022年には店頭での引き出し上限が100万円に設定され、今回は自由な重さでの引き出しも禁止されました。これらの制限は全て「現物の大量引き出しを防ぐ」という同じ目的に向かっており、実際に現物を十分に確保していない可能性さえ疑われます。
投信やETFとの本質的な違いがなくなった現実
現物アクセス権を実質的に失った純金積立は、もはや投資信託やETFと何ら変わらない金融商品となってしまいました。投信やETFは最初から現物引き出し不可で現金償還のみですが、現在の純金積立も実質的に同じ状況です。
残る違いは税制と手数料体系だけという状況になっています。純金積立は購入時非課税で売却時に譲渡所得課税、投信やETFは信託報酬や販売手数料という違いはありますが、「金に投資する」という経済的実質は完全に同じです。むしろ金ETFの方が手数料が透明で安く、流動性も高く、最初から現金償還前提なので利用者を騙すこともありません。
特に問題なのは、純金積立が「現物を持てる安心感」という付加価値で高い手数料を正当化しながら、実際にはその最も重要な機能を骨抜きにしていることです。これは明らかに商品説明と実態の乖離であり、利用者に誤解を与えながら高い手数料を徴収する構造となっています。
信用リスクという根本的な問題
この問題を突き詰めると、現代の金融システム全体に内在する根本的な課題に行き着きます。手元にない以上、どんなに「特定保管」「所有権はあなた」と言われても、結局は業者が本当に保管しているか、約款通りに引き渡してくれるか、システムが正常に機能するかという信用に全て依存しているのです。
真の現物保有を目指すなら、自宅金庫での保管や貸金庫の利用が必要ですが、盗難や火災のリスク、高いコスト、アクセス制限などの問題があります。利便性とコストを考えると、多くの人にとって現実的な選択肢ではありません。
重要なのは、この根本的な信用関係を正しく認識することです。特定保管制度は、この信用リスクを曖昧にして、利用者に「信用リスクを負っていない」という錯覚を与えていたのが最大の問題でした。
今後求められる透明性と選択の自由
この一連の変化が示しているのは、金融サービスを利用する際には、その法的性質だけでなく、付随する契約書まで理解し、そこに潜むリスクを正確に把握する必要があるということです。「特定保管だから安心」という漠然とした信頼感は、もはや通用しない時代になったのです。
利用者としては、現物の引き出しを希望する場合、解約前に必ず引き出し手続きを完了させ、口座残高をゼロにしてから解約するという手順を踏む必要があります。この順序を間違えると、現金化を強制されてしまう可能性があります。
しかし根本的には、業者側にはより透明で誠実な商品設計が求められます。現物アクセス権を実質的に制限するなら、最初から「金価格連動の金融商品です、現物は受け取れません」と明示し、適正な手数料で提供すべきでしょう。
現在の仕組みは、制度の名前だけ残して中身を骨抜きにし、利用者に誤解を与えながら高い手数料を徴収する構造となっています。この現実を広く認識し、真に利用者の利益を守る制度設計を求めていく必要があるのではないでしょうか。