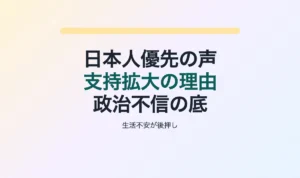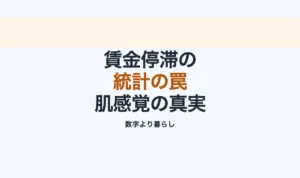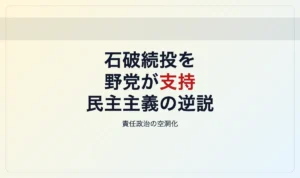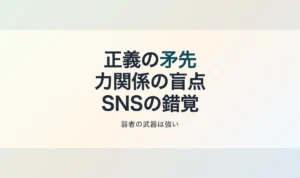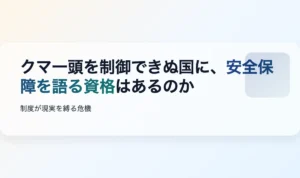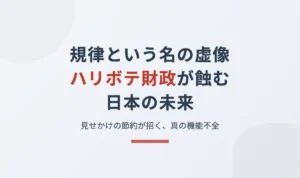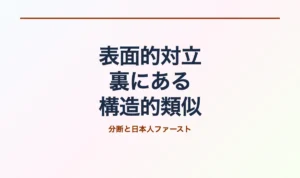先日、SNSで目にした言説に背筋が凍った。ある政党について「一度でも支持を表明した者は、その責任を死ぬまで追及されるべきだ」「沈黙は支持と同じであり、明確に非難しない者も同罪だ」といった主張を目にすることが増えている。
この論理に従えば、積極的にその政党を批判しない限り、すべての人が「永続的な非難」の対象になってしまう。現在の日本で合法的に活動する政党に対して、このような極端な敵視を正当化する思考は、現代の魔女狩りに他ならない。
この人物は恐らく、自分を「差別を許さない正義の人」だと思い込んでいるだろう。しかし冷静に考えてみてほしい。現在の日本で合法的に活動している政党の支持者を「永続的に非難する」と宣言することが、果たして民主主義的な態度と言えるだろうか。
絶対悪の設定が生み出す絶対正義の危険性
この問題の根本にあるのは、ナチスのような「絶対悪」を設定することで、それに対抗する自分たちを「絶対正義」と位置づける思考構造だ。しかし歴史を振り返れば明らかなように、人間は悪の名の下に人を殺めてきたのではなく、正義の名の下に人を殺めてきた。
十字軍は「神の正義」のため、魔女狩りは「社会の浄化」のため、ナチスの虐殺は「民族の純化」のため、文化大革命は「人民の解放」のため行われた。誰も「我々は悪いことをしている」とは思っていなかった。むしろ「自分たちは絶対的に正しく、相手は絶対的に間違っている」という確信があったからこそ、躊躇なく大量殺戮ができたのだ。
もし再びナチスの悲劇が起きるとすれば、それは絶対悪とされたナチスの亡霊ではなく、ナチスの亡霊を滅することを標榜する絶対正義の方だろう。現実に、このような思考の人々が「反ファシズム」という大義名分の下で、着々とファシズム的な社会統制を構築しようとしている光景を、我々は目の当たりにしている。
自由主義と平等主義の根本的な違い
では、なぜ左系の思想は粛清に向かいやすいのだろうか。その答えは、自由主義と平等主義の根本的な違いにある。
自由主義の基本姿勢は「ほっといてくれ」だ。他人の考えに対しても「そう考えるんだ、ふーん」という距離感を保つ。基本的に他者に対して「ああしろこうしろ」とは言わない。一方、平等主義は「理想的な平等社会」を目指すため、その理想に反する人々を「正しく導く」必要があると考える。
この違いは、人間観の根本的な相違から生まれる。自由主義者は「人間はわかり合えない」という前提に立つため、理解されないことにも期待しない。相手に自分の価値観を押し付ける必要もないし、相手から理解されることも求めない。
一方、平等主義者は「人間はわかり合うべき」と考えるため、理解されないことに強い苛立ちを感じる。「なぜわからないのか」「どうして理解しようとしないのか」という怒りが生まれ、最終的に「理解しない者は悪意を持っているに違いない」「説得しても無駄なら強制するしかない」となってしまう。
「中立は敵」という全体主義的論理
「沈黙は支持と同じ」という論理は、まさに「中立は敵」という全体主義的思考の典型例だ。これは事実上、すべての人に「その政党を永続的に非難し続けるか、さもなくば自分が非難される側に回るか」の二択を迫っている。
このような論理構造は、歴史上の粛清と全く同じものだ。文化大革命でも、最初は「反革命分子」が対象だったが、最終的には「反革命分子に同情的」「革命への熱意が不足」という理由で、膨大な数の人が粛清対象になった。
特定の政党がまだ何も実行していない現段階で、これほど極端な敵視をするのは異常と言わざるを得ない。その政党の政策に反対するのは自由だが、支持者を「人として永続的に非難する」という発想は、民主主義の根本的な否定だ。
価值観の複雑性を認める成熟した思考
しかし、ここで重要なのは、人間を一つの主義主張で説明しようとすることの危険性だ。現実の人間は、状況に応じて様々な価値観を使い分けている。その濃淡が最終的に合成されて、その人の態度になる。
私自身、自由主義的な傾向が強いが、人殺しの自由があるとは言わない。その自由よりも秩序を優先する。ここで重要なのは、「自由主義を守るため」ではなく「秩序のため」だということだ。純粋な自由主義の価値観ならば、人を殺す自由には殺される前に殺す自由で対抗するしかない。しかしそんな修羅の世界は嫌なので、全体の秩序を優先する。これは多分に集団主義、社会主義的な側面が生じるが、それは受け入れる。
平等についても重要だと考えている。人の世は不平等だからだ。政治家の子供に産まれるのと、高卒でシングルマザーの貧困家庭で生まれる子供を、同じように扱うのが善だろうか。生まれつき目が見えない人に視力検査をするのが善だろうか。したがって、そこに是正の圧力は正当化されると考える。
しかし、それらはどこまでも規制であって、自由を守るためではない。それは平等や公平、秩序といったものを重視するからである。同時に、それは無制限に個人の自由を封殺してよいということにもならない。個人の自由なしに、いったい何の幸福があるというのか。
現実主義という生き残り戦略
このような価値観の使い分けは、決して日和見主義ではない。むしろ現実の中で生き残るための、極めて実用的な戦略だ。
完全な自由主義を貫けば、暴力的な相手に対して無力になる。完全な平等主義を貫けば、現実の複雑さに対応できなくなる。だからこそ、状況に応じて異なる価値観を採用し、現実的なバランスを取ることが必要になる。
「永続的な非難の対象にする」と言う人々も、実際には現実の中で適度な妥協をしているはずだ。職場にその政党の支持者がいても、普通に「おはようございます」と言っているだろうし、飲み会があれば一緒に飲んでいるかもしれない。ネットでは過激なことを言えても、リアルでは顔も知られているし、関係性も複雑だから、そこまで極端な態度は取れない。
みんな適度に現実主義なのだ。そしてその「いい加減さ」こそが、社会の安定装置として機能している。
おわりに
私たちが警戒すべきは、特定の政治勢力ではなく、「絶対正義」を確信した人々の暴走だ。彼らは「正義のため」「社会のため」と本気で信じ込んでいるからこそ、最も危険な存在になり得る。
真の民主主義とは、異なる価値観を持つ人々が共存できる社会だ。そのためには、自分と異なる意見を持つ人の存在を認め、対話の可能性を残し続けることが不可欠だ。「永続的に非難する」という思考は、その対話の可能性を完全に封じ込めてしまう。
我々に必要なのは、複雑さを受け入れる成熟した思考と、現実的なバランス感覚だ。一つの主義に固執して社会を分裂させるのではなく、多様な価値観を使い分けながら、皆が幸福に暮らせる社会を模索していくこと。それこそが、真に建設的な政治的態度と言えるのではないだろうか。