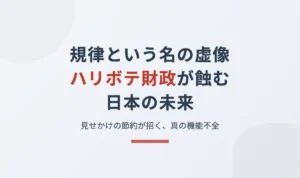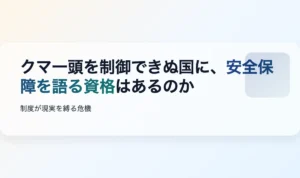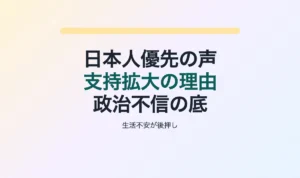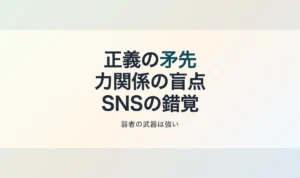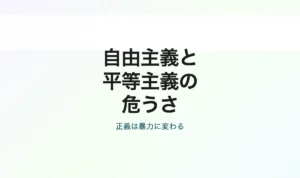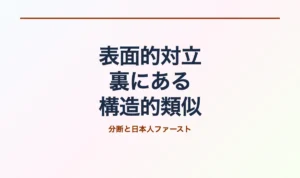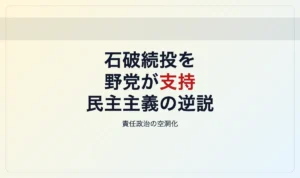美しい統計の裏に隠された真実
「女性の社会進出」「生涯現役社会」「働き方改革」——これらの美しいスローガンが躍る一方で、日本の賃金中央値は25年前より下がっている。この現実に対し、統計の専門家たちは決まってこう言う。「女性や高齢者の労働参加が増えたから、見かけ上の数字が下がっただけだ」と。
確かに統計解釈として、この指摘は技術的に正しい。労働市場の構成が変われば、平均値や中央値は影響を受ける。だが、この「統計的説明」で現実の厳しさが消えるわけではない。むしろ、なぜ今まで働かなかった人たちが働き始めたのかという根本的な問いから、我々は目を逸らしてはならない。
現実は単純だ。夫の収入だけでは生活が成り立たなくなったから妻が働き始め、年金だけでは不安だから高齢者が働き続けている。「多様な働き方」という響きの良い言葉の陰で、実際は「働かざるを得ない」人々が急増しているのである。
「働け一億火の玉だ」の現代版
この状況を端的に表現するなら、「女性の社会進出」や「生涯現役」ではなく「働け一億火の玉だ」の方が実態に近い。戦時中の国民総動員と現代の労働動員には、驚くほど共通点がある。
美しいスローガンで現実を覆い隠し、個人の選択の余地を奪い、全体のために働くことを美徳とする——。「お国のため」が「経済のため」「社会のため」に変わっただけで、構造は同じではないか。
特に興味深いのは、欧米からの圧力が「女性活躍推進」を後押ししていることだ。ジェンダー平等という錦の御旗の下、反対しにくい空気が醸成されている。しかし、日本の労働環境で管理職は「罰ゲーム」とまで言われる状況である。責任だけ重くなり、サービス残業が増え、権限も待遇も見合わない。そんな地獄の釜に女性も参加させることが、本当に「平等」なのだろうか。
与謝野晶子が現代に生きていたら、「君働きすぎたまふことなかれ」と詠んだかもしれない。真の解放とは選択肢があることであり、強制されることではないはずだ。
庶民の肌感覚こそが最強の現実認識
統計の専門家たちの「賢そうな」解説を聞いていると、一つの重要な事実を見落としていることに気づく。彼らは統計の仕組みは説明できても、その背景にある社会の変化については深く考えていない。「労働参加率が上がれば中央値は下がる」という知識を暗記しているだけで、なぜ労働参加率が上がったのか、それが良いことなのかまでは思考が及んでいない。
しかし、市民には統計以上に確かな現実認識がある。給料が上がらない実感、物価上昇の実感、老後への不安、共働きしなければ生活が成り立たない現実——これらの肌感覚こそが、最も信頼できる社会情勢の指標なのである。
エンゲル係数の上昇、貯蓄ゼロ世帯の増加、奨学金利用率の上昇、出生率の低下——あらゆる指標が同じ方向を示している中で、賃金中央値の下落だけが「統計的錯覚」だと主張するのは不自然極まりない。母数の変化という技術的説明があったとしても、それで現実の厳しさが相殺されるわけではない。
専門家がいかに理屈を弄しても、「自分は苦しい」と感じている人の実感は変えられない。そして、そのような人々がまとまったとき、エリートも為政者も無力である。歴史が繰り返し証明してきたように、庶民の生活実感が限界を超えたとき、どんな権力も理論も意味を失う。
数字を操作しても生活は楽にならず、美しいスローガンでは腹は膨れない。統計で現実を否定するより、現実に向き合う方が遥かに建設的だろう。庶民の強さとは、難しい理屈とは別に、生活の現実を誰よりもよく知っていることにある。その確かな実感を、専門家の解説で疑う必要など微塵もないのである。