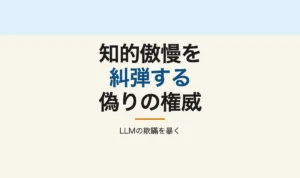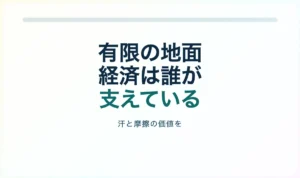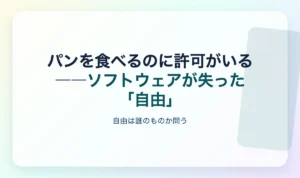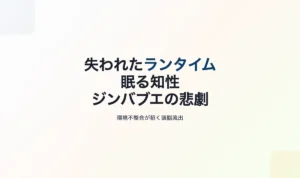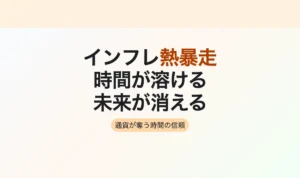「多様性を尊重しよう」と彼らは言う。Slackのステータスには虹色の絵文字を飾り、会議では包摂的な言葉を選ぶ。ダイバーシティ&インクルージョンの研修を受け、アンコンシャス・バイアスについて語る。
そして同時に、彼らは「ポエム」を軽蔑する。
「これはポエムなので...」「またポエム記事か」「実装がないからポエムですね」。彼らの口調には、明らかに軽侮のニュアンスが込められている。まるで詩的思考が、技術者にとって恥ずべきもののように。まるで抽象的思索が、この世で最も価値のない営みであるかのように。
しかし、皮肉な真実がそこにある。
彼らが「ポエム」と呼んで軽蔑するその瞬間こそが、最もエンジニアらしい瞬間なのだ。
既存のフレームワークから離れ、定番の解法を捨て、誰も歩いていない思考の荒野に足を踏み入れる。ベストプラクティスという安全な港を離れ、自分だけの設計哲学を築き上げようとする。これこそが、エンジニアの本来の姿ではないか。
創造性、独創性、深い思索。問題を根本から見直し、新しい解決策を模索する知的勇気。誰も試したことのないアーキテクチャを構想し、従来の常識に疑問を投げかける批判的思考。
これらすべてが「ポエム」という蔑称の中に封じ込められている。
彼らは自分たちの最も純粋なエンジニア精神を、無意識に軽蔑している。そして同時に、その軽蔑という間違った態度によってこそ、かろうじてエンジニアの本質を保っているのだ。
なんという複層的な悲劇だろうか。
「ポエム」という言葉は、彼らにとって免罪符となった。「これは実用的じゃないかもしれませんが...」「ふわふわした話で申し訳ありませんが...」という予防線を張ることで、創造的思考への批判を回避する盾として機能している。
しかし、その盾の向こうで、彼らは最も価値ある思考を展開している。
GitHubが「master」を「main」に変更した時、彼らは素直に従った。政治的正しさの前では思考を停止し、技術的合理性を放棄した。一方で、Linuxの創始者リーナス・トーバルズは政治的圧力を完全に無視し、技術的必然性だけを追求し続けている。
真のエンジニアと偽物の差は、ここに現れる。
そして皮肉なことに、「ポエム」を書くエンジニアたちの方が、リーナスに近い精神を持っているのだ。既存の権威に迎合せず、自分の頭で考え、独自の理論を構築しようとする姿勢。それこそがエンジニアの本質なのに、彼ら自身がそれを「ポエム」として貶めている。
この構造の中に、現代技術界の最も深刻な病理が潜んでいる。創造性を軽蔑し、独創性を嘲笑し、深い思索を「実用性がない」として切り捨てる文化。そして同時に、その軽蔑的な枠組みの中でのみ、かろうじて創造的思考が生き延びているという逆説。
「ポエム」は救済なのだ。間違った形ではあるが、エンジニアたちの純粋性を保つ最後の砦として機能している。
彼らは知らない。自分たちが軽蔑している「ポエム」こそが、エンジニアとしての魂を守る唯一の手段だということを。自分たちが嘲笑している抽象的思考こそが、技術者としての本質だということを。
間違った態度に身を委ねることで、ギリギリ正しい姿勢を保っている。この哀しい逆説の中で、現代のエンジニアたちは生きている。