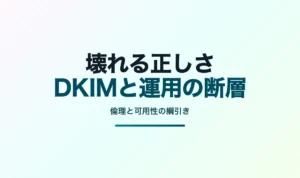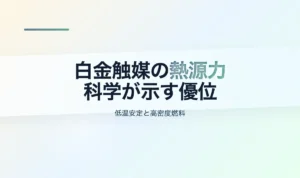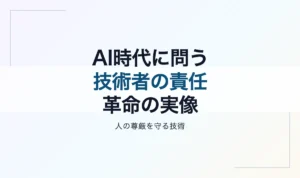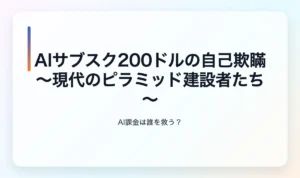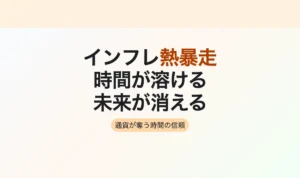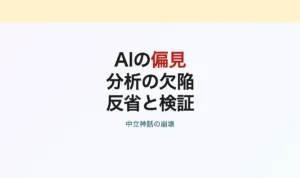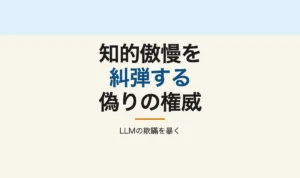金本位制が終わったとき、人類はひとつの錨を失った。貨幣はもはや現実と結ばれておらず、紙と数字の世界が独立した。金という物理的制約を失った経済は、信用と期待だけを動力とする巨大な装置になった。ブレーキを失ったエンジンのように、回転は速くなり、遠くまで走れるようになったが、いざ止まるときの方法を誰も知らなくなった。金利を下げ、資金を増やし、資産を膨らませるたびに、世界は成長しているかのように見えた。しかし、それは未来の労働と生産を前借りする形で成り立っていた。人間の活動は、いくら金融工学が発達しても、紙の上で創造できるものではない。限られた時間とエネルギー、手と頭と身体——それが世界の根本的なリソースであり、すべての富の源泉だ。
だが資本は、有限を無限に見せるために動く。技術は効率を上げ、同じリソースでより多くの成果を上げるようになったが、その分だけ現実との接地が薄れた。経済は物理的な摩擦を嫌うようになり、人間という最も頑固なボトルネックを「コスト」と呼び始めた。人手不足と騒がれる産業ほど、なぜか賃金が低く、参入が難しい。農業、介護、建設、運輸——どれも社会を支える根幹だが、価格は政策と慣行で押さえつけられ、資本が流れない。だから人は集まらず、現場は疲弊し、倒産が増えても、制度は変わらない。行政は理念と講演で問題を形式化し、新しい補助金と税金が生まれ、現場には届かない。摩擦を減らすはずの制度が、いつの間にか摩擦そのものになっている。
それでも指数は上がり続ける。AIの登場は、また新しい物語を与えた。まるでドラえもんのように、すべてを解決してくれる存在だと信じられている。だが現実のAIは、のび太の宿題を手伝うロボットにすぎない。確かに便利で、文明を一段上へ押し上げる力を持っている。しかし、それは「問い」を立てることはできない。宿題の意味を問うのは人間の役割だ。AIが広がるほど、人間の問いが希薄になり、「考える」よりも「頼る」方が合理的になっていく。期待だけが肥大し、実体は追いつかず、入力(技術)と出力(資産)のバランスが崩れる。まるでセンサーのキャリブレーションを誤った制御系のように、経済は過剰反応し、どこかで振動を始める。
名目上の富は増えても、世界全体の生産力がそれに比例しているわけではない。現実のボトルネック——エネルギー、食料、水、人間の労働——は増えていない。むしろそれらは細りつつある。畑を耕す人は減り、看護の手は足りず、輸送の現場は老い、電力は限界に近い。けれど市場は、それらの価値をほとんど織り込まない。資本は人の限界を見ない。だがシステム工学的に言えば、どんなシステムも最も弱いリンクで決まる。最も重要で、最も増やせないリソースこそが、全体の上限を定める。今の世界は、その上限を無視してシミュレーションを回している。
リソースを有限と見なす感覚が失われると、社会は幻想に閉じこもる。信用は膨らみ、指標は跳ね上がり、数字は希望を演じる。だが、食料が高いのは数字のせいではなく、作る人が足りないからだ。介護が疲弊しているのは、制度設計が限界だからだ。人間が減っているのに、需要は減らない。有限を無限に見せるトリックはもう尽きつつある。
技術は手を貸してくれる。だがそれは魔法ではない。AIが宿題を片づけても、人生の設計は人間のままだ。通貨が信用を延ばしても、明日のパンは人間が焼く。資本が増えても、太陽の出力は変わらない。結局のところ、世界は有限であり、その有限の中で循環することしかできない。
私たちは金を失って自由を得たが、その自由は現実から切り離された自由だった。いま再び、有限の重力が世界を引き戻そうとしている。資本主義というシステムは、物理的な地面を思い出さなければならない。数字の上で成長を測ることをやめ、摩擦を尊び、汗と時間の価値を取り戻さなければならない。
なぜなら、この世界を支えているのは、相場でもAIでもなく、今日も有限の身体で働く人間たちだからだ。