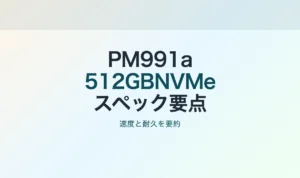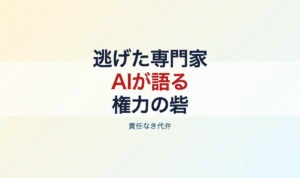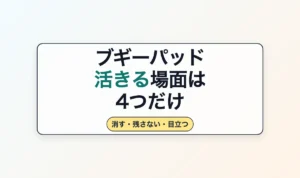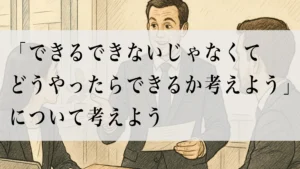「スケーラビリティ」とは、いつから呪文のように唱えられるようになったのだろう。
それが善であるかのように。
伸びること、拡張すること、止まらないこと。
気づけば、それが「正しい設計」と同義になっていた。
だが、なぜスケールしなければならなかったのか。
その問いを立てた途端、静かな違和感が立ち上がる。
スケーラビリティとは、本来、要件であり思想ではない。
負荷が増えたときに破綻しないようにする――ただそれだけの技術的条件だったはずだ。
いつからそれが、信仰になったのか。
資本は増えるものを好む。
伸びる市場、拡張する事業、指数関数的なグラフ。
だから、スケールできるものに資金が流れ、スケールしないものは切り捨てられた。
だが、スケールしないものこそが、人間の生活を支えている。
道路、水道、農業、介護、教育。
それらは「成長」しない。だが、生きるために必要だ。
我々はアトムでできている。複製も加速もできない、有限の存在だ。
にもかかわらず、世界は「スケールする幻想」に資源を注ぎ続けた。
クラウドは肥大化し、AIは指数関数的に計算資源を食い、
社会は「止まらないこと」を是とした。
GitHubが落ちればXで騒ぎ、電力が止まればAIは沈黙する。
それでも我々は、止まることを恥とし、効率を誇った。
可用性、スケーラビリティ、効率化。
そのどれもが、平時の快適さを保証する代わりに、有事の余裕を切り捨ててきた。
効率とは、平時の幻想だ。
「前提が崩れない限り最適である」――それが効率の定義である。
しかし前提が崩れた瞬間、効率は脆さに変わる。
在庫を削り、冗長を嫌い、余裕を無駄と断じた世界に、
有事は必ず訪れる。
いま、世界中でアトムが足りない。
食料が高騰し、エネルギーが逼迫し、水道管が破裂する。
それでも人類はデータセンターを建て続ける。
AIのために。だがAIが作るのは、ディープフェイクだ。
虚構が増えるほど、現実の資源は減っていく。
信用は膨張しても、現実は拡張しない。
この乖離こそが、現代の不安の正体だ。
AIが生成できるのはビットである。
だが足りていないのはアトムだ。
生きるための水、食料、時間、身体、手触り。
それらはスケールしない。
だからこそ尊い。だからこそ有限。
それを軽視した社会が、いま軋み始めている。
スケーラビリティは悪ではない。
だが、それが「当然」になったとき、何かが壊れ始めた。
スケールするものばかりが評価され、スケールしないものが軽んじられた。
本質はいつだってスケールしない側にある。
それを守るために、我々はスケーラブルな幻想を一度降りる必要がある。
有限性を受け入れること、それこそがこれからの設計思想だ。
技術は、拡張ではなく、維持のために使われるべきだ。
「止まらない」ではなく「止まっても壊れない」ために。
我々は、スケールする虚構から、スケールしない現実へと帰らねばならない。