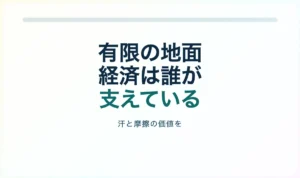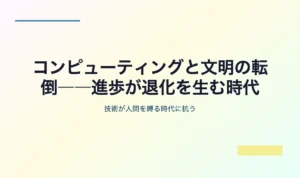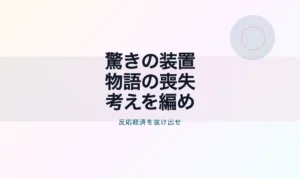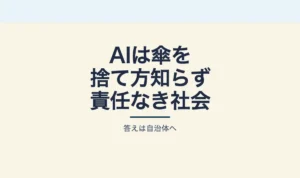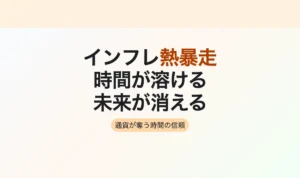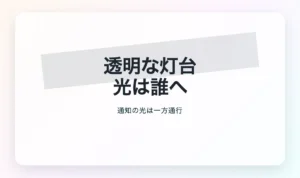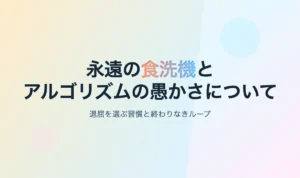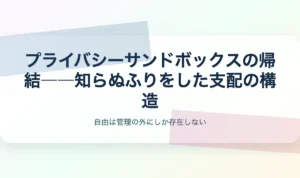バブルは、いつだって止まれないものとして生まれる。
誰もがそれを知っている。狂っていると知りながら、前へ進む。
おかしい、と感じながら進むことが、最も合理的になってしまう。
この矛盾の中に、現代の経済のすべてが凝縮されている。
AIバブルが話題になるとき、多くは「過熱」「期待」「合理的投資」といった言葉で語られる。
だが、どれだけ理屈を積み上げても、「なぜ止まらないのか」という根本には届かない。
それは理屈の問題ではなく、構造の問題だからである。
成功者は自分の成功を合理の証拠とみなす。
「今日まで生きてきたのだから、明日も生き残れる」と信じる。
その信念は経験から導かれるが、同時に最も危うい罠でもある。
勝者の論理は、勝った者にとってだけ合理なのだ。
だから市場は、崩壊を予感しながら走り続ける。
止まらないのは、狂気ではなく制度の仕様である。
この「止まれなさ」は、何もAIに始まった話ではない。
経済そのものが、もはや停止という選択肢を失っている。
それが始まったのは半世紀前、金本位体制が終わったときだ。
通貨は金という実体から切り離され、信用という幻想を基盤に動き出した。
信用は拡張できる。限界がない。
つまり、世界は「膨らむことをやめられない」仕組みになった。
かつてのチューリップ・バブルでは、狂乱の対象は花弁で済んだ。
だが今、投機の対象は経済そのものだ。
信用が増え、資金が溢れ、資本が新しい幻想を求めてさまよう。
その先に見つけたのがAIだった。
AIは夢のように巨大で、説明不能なほど希望に満ちている。
そこに資本が集まらないはずがない。
だが、その熱狂の奥にあるのは、依然として「止まれない世界」の欲望である。
だから、AIバブルが崩壊するかどうかは問題ではない。
問題は、崩壊が「止まること」ではなく、「次の膨張の始まり」であることだ。
金という錨を失った世界では、バブルは事故ではなく呼吸のようなものになっている。
吸って、膨らみ、弾け、また吸う。
それがこの半世紀の経済のリズムだ。
AIバブルとは、その呼吸の最新の一拍にすぎない。
AIそのものが虚構なのではない。
虚構に支えられているのは、むしろ世界のほうだ。
私たちは「信用」という目に見えない酸素の中で生きている。
そして、その酸素が過剰になるとき、呼吸はバブルという名の過換気に変わる。
止まらない世界は、狂っているようで、精密に動いている。
狂気のように見えるのは、その合理があまりに透明だからだ。
バブルは壊れるために生まれる。だが壊れることでしか、次のバブルを生めない。
それがこの時代の宿命であり、AIという幻想の背後に流れる静かな脈動である。