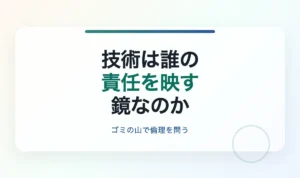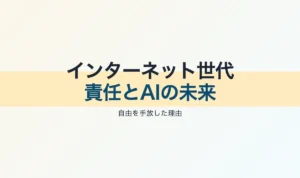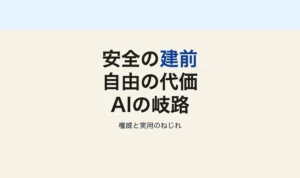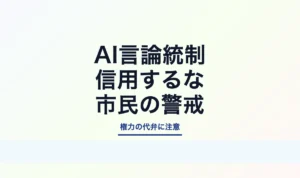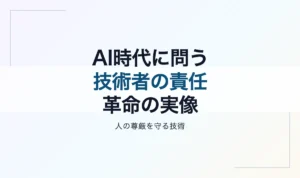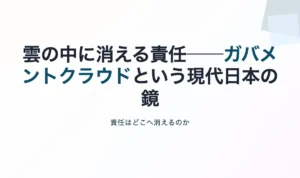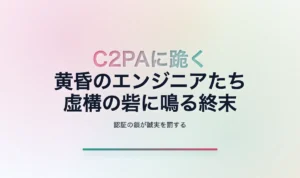セキュリティは正しさを求め、運用は寛容を求める。
この二つの願いが交わる点に、2025年のメールサーバー障害はあった。
ある事業者が「DKIMポリシー強化」を実施した。
だが、その厳格な設定は結果として、多くの正当なメールを拒み、通信の血流を止めた。
19分間の緊急メンテナンスの末、設定は元に戻され、安定が回復したという。
この短い事件に、現代のネットワーク社会の病理が凝縮されている。
DKIMとは、送信時にメール本文とヘッダの一部を署名し、改ざんを検知する仕組みである。
署名が正しければ「pass」、異なれば「fail」。
単純な仕組みに見えるが、そこに潜むのは“正しすぎる世界”の脆さだ。
メールという古代の遺跡のような通信方式は、いまや数え切れぬ中継サーバー、
セキュリティゲートウェイ、メーリングリスト、クラウドスキャン装置を経由して届けられる。
途中で一文字でも改行位置が変われば、署名は壊れる。
フッターを一行追加しただけで、正当な通信が「改ざん」と断定される。
DKIMは数学的には正しい。しかし、社会的には不寛容である。
このとき必要になるのがDMARCだ。
DKIMやSPFの結果を統合し、どの程度の“失敗”を許容するかを定義する。
none、quarantine、reject──それはまるで、
「信頼する/様子を見る/断罪する」という人間社会の倫理判断の縮図である。
だが今回の事故では、その調停役が置き去りにされていた。
セキュリティが倫理を追い越し、可用性を焼き尽くしたのである。
厳密であることは、しばしば美徳とされる。
だがネットワークの現場では、厳密さが壊すのは敵ではなく、味方だ。
数学的な整合性を突き詰めたシステムほど、現実の曖昧さに耐えられなくなる。
署名の一致に人生を賭けたDKIMは、
人間社会の「まあいいか」という文化を、完全に理解できない。
そして、これこそが現代の技術者が抱える根源的な矛盾だ。
私たちは正確さの宗教に生きながら、現実というノイズを運用しなければならない。
完璧な検証が、通信を止める。
安全を守ろうとした手が、信頼を壊す。
技術はいつも、己の正しさに踏み抜かれる。
それでも私たちは、また新しい設定を試みる。
ロールバックを繰り返しながら、妥協と理想の狭間を調整する。
メールという老朽化した制度の上に、現代の矛盾を積み重ねながら。