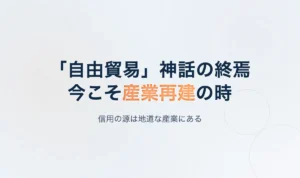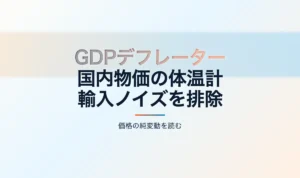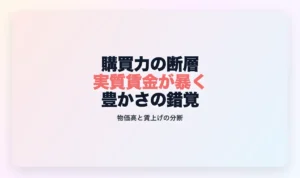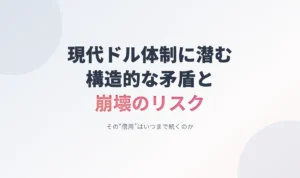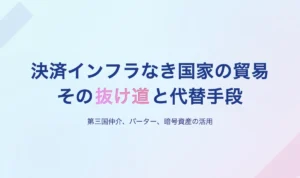
ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)は、技術革新の象徴として登場した一方で、国家にとっては通貨主権を揺るがす存在として警戒されています。これまでの連載で触れてきたように、国家は通貨の発行、管理、監視を通じて経済を統制してきました。しかし、暗号資産の登場は、こうした従来の金融秩序に対して根本的な挑戦を突きつけています。
本稿では、ビットコインを中心とした暗号資産が、国家の金融統制に対してどのような影響を及ぼしているのか、そして各国がどのような対応を試みているのかについて整理します。
暗号資産の特徴と国家の管理不能性
暗号資産の最大の特徴は、その非中央集権性にあります。従来の通貨は中央銀行や政府の管理下にあり、金利政策や金融規制といった枠組みによって制御されてきました。しかし、ビットコインのような暗号資産は、ブロックチェーンという分散型台帳技術に支えられており、特定の管理者が存在しません。
この仕組みは、送金や保有において国家の監視や規制を受けにくいという利点を持つ一方で、国家にとっては極めて扱いにくい存在でもあります。たとえば、資本規制のある国からの資産逃避や、制裁回避、匿名性を利用した違法取引への懸念が常につきまといます。
国家にとって暗号資産は、発行権、管理権、徴税権という三つの根本的な主権機能に対する挑戦となりうるのです。
富裕層・資本家にとっての「保険」としての暗号資産
国家がどれだけ安定して見えても、政変や経済危機が起これば、その国の通貨や金融システムは一気に信頼を失います。そのリスクヘッジとして、ビットコインやUSDTのような暗号資産に資産を逃がしておくことは、グローバルな富裕層にとって一種の「保険」となっています。
特に近年では、法定通貨が暴落したトルコやレバノン、アルゼンチンといった国々で、暗号資産への関心が高まっており、個人投資家から企業経営者、政治家に至るまで、広範な層が暗号資産を資産防衛の手段として利用しています。国家の枠組みを超えて資産を移動できるという点において、暗号資産は既存の金融システムでは実現しえなかった自由度を提供しているのです。
国家の対応:禁止、監視、取り込み
暗号資産に対する国家の対応は、大きく三つに分かれます。一つ目は「全面禁止」。中国が典型で、マイニングや取引を一切禁止し、法定通貨以外の通貨機能を認めない姿勢を取っています。
二つ目は「監視と規制の強化」。アメリカやEUは暗号資産を金融商品として認識し、KYC(本人確認)やAML(マネーロンダリング防止)規制を強化する方向に進んでいます。これにより、暗号資産の匿名性を抑制しつつ、監視下での取引を可能にしています。
三つ目は「国家通貨への取り込み」。中央銀行デジタル通貨(CBDC)の開発がその代表例です。中国のデジタル人民元、EUのデジタルユーロ、そして日本銀行が進めるデジタル円の実証実験など、国家は自らデジタル通貨を発行することで、暗号資産の技術的利点を吸収しつつ、国家の統制下に置こうとしています。
地政学的視点で見た暗号資産の役割
国家間対立の中で、暗号資産は「制裁逃れのツール」としても注目されています。北朝鮮によるサイバー攻撃による仮想通貨の窃取、ロシアがウクライナ侵攻後に外貨決済を補うために暗号資産を活用しているとされる事例など、国家が戦略的に暗号資産を使うケースも増えています。
また、ドル支配に対抗したい国々にとって、ビットコインのような非ドル資産は、「第3の選択肢」としての魅力を持ちます。とくに南米やアフリカの一部国家では、外貨準備の多様化手段として暗号資産の活用が検討されているとも報じられています。
結語
ビットコインをはじめとする暗号資産は、金融インフラとしての可能性を秘めながらも、国家にとっては通貨主権を侵す可能性のある「制御不能な存在」として映っています。禁止、規制、取り込みという三方向のアプローチが混在する中で、暗号資産を巡る地政学的な緊張は今後も続いていくと考えられます。
暗号資産は、単なる投資商品ではなく、国家・企業・個人それぞれの戦略と生存本能が交差するフィールドとなっています。国際金融の構造転換が進む中で、通貨とは何か、国家とは何を支配しているのかを改めて問い直す契機となるでしょう。