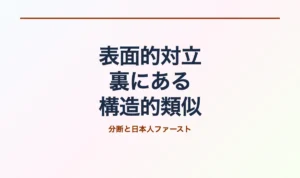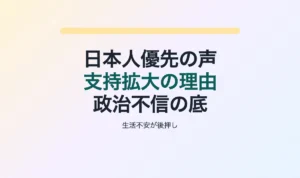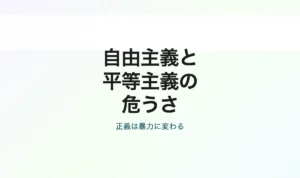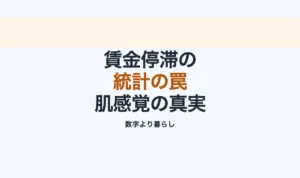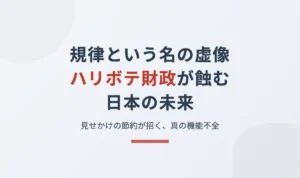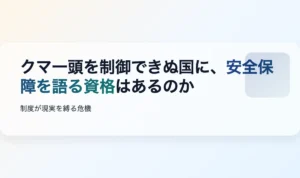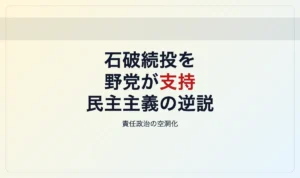象と蟻を同じ檻で戦わせる愚
現代のSNSは奇妙な闘技場である。そこでは巨象のような大企業と、蟻のような零細事業者が同じリングに立たされ、観客席からは容赦ない批判の矢が飛んでくる。しかし、多くの批判者は重要なことを見落としている。象には蟻を踏み潰す矢は刺さらないが、蟻には致命傷となることを。
私たちは日常生活では自然とこの力関係を理解している。総理大臣への批判と近所の商店主への苦情では、当然ながら言葉を選ぶ。前者はどれほど厳しく言おうとも権力の座から転落することはないが、後者は評判ひとつで廃業に追い込まれかねない。この感覚は社会人としての基本的なマナーであり、多くの人が無意識に実践している常識である。
ところが、SNSという平坦な画面の向こうでは、この常識が霞んでしまう。フォロワー数百人のアカウントが、上場企業も地方の個人商店も同じトーンで批判する光景は、もはや珍しくない。批判者にとっては「同じTwitter上の企業アカウント」でしかないが、現実の影響力は天と地ほど違う。
「弱者の武器」が持つ破壊力
特に注意すべきは、社会的正義を掲げた批判の威力である。現代社会において「差別批判」は極めて強力な武器となった。大企業を相手にすれば適切な社会的制裁として機能するが、零細企業に向ければ過剰な懲罰となりかねない。
この構図には深刻な逆説が潜んでいる。正義を掲げる側は「弱者」として社会的同情を集めながら、実際には強大な破壊力を行使できる立場にある。彼らの批判ひとつで企業が炎上し、個人が社会的に抹殺される事例は枚挙にいとまがない。にもかかわらず、依然として「差別と戦う弱者」としての認識が維持され、その批判行為は正当化され続ける。
ここで思い出すべきは、力を持つ者の責任である。銃を持った人間が、相手を選んで引き金を引くように、強力な「正義」という武器を持つ者もまた、その使用に際して慎重であるべきだ。総理大臣を批判するのと同じテンションで、地方の小さな商店を攻撃することは、道徳的に正当化できない。
実際のところ、正義を掲げる運動の強さは、まさにこの「容赦のなさ」にある。相手の立場や事情を考慮せず、一切の手加減をしないからこそ、既存の権力構造に風穴を開けることができる。しかし、その同じ武器が、本来保護されるべき弱者に向けられた時、運動の正当性は大きく揺らぐ。零細企業や個人事業主のような、真の意味での社会的弱者を標的とした瞬間、「正義の戦い」は「強者による弱者いじめ」へと変質してしまう。
作品から学ぶべき教訓
興味深いことに、多くの批判者が愛好する創作物には、まさにこの問題への答えが隠されている。例えば、長年愛され続ける漫画作品の多くは、力と正義の関係性を丁寧に描いている。主人公たちは強大な力を手にしながらも、相手を見て手加減し、無力な一般人を巻き込まないよう細心の注意を払う。一方で、「自分こそが絶対的正義」だと確信した敵キャラクターたちは、その傲慢さゆえに破滅への道を歩む。
しかし、作品の受容は受信者次第である。同じ物語を読んでも、ある読者は深い人間洞察を得て、別の読者は表面的な興奮だけを味わう。批評や文学研究が存在する理由も、まさにここにある。作品が持つ多層的な意味を掘り起こし、読者により深い理解をもたらすためだ。
残念ながら、現実の批判者の多くは、愛する作品から「力の使い方」について学ぶ機会を逸している。彼らは作品のメッセージを受け取りながらも、それを現実の行動に反映させることができない。これは単に個人的な損失にとどまらず、社会全体にとっての機会損失でもある。
大人の知恵としての「使い分け」
結局のところ、この問題の解決策は拍子抜けするほど単純である。大企業には遠慮なく、零細企業には言葉を選んで批判する。ただそれだけのことだ。これは特別な理論や複雑な分析を必要としない、社会人としての基本的な常識に過ぎない。
重要なのは、批判する側が自分の持つ「武器」の威力を正しく認識することである。現代社会において、正義を掲げた批判は実際に人や企業を潰せる破壊力を持っている。その事実を受け入れ、相手の規模や立場に応じて表現を調整する知恵こそが、真に成熟した社会人の条件だろう。
SNSという平坦な空間が生み出す錯覚に惑わされることなく、現実の力関係を見極める眼力を養うこと。これこそが、デジタル時代を生きる私たちに求められる新しいリテラシーなのである。