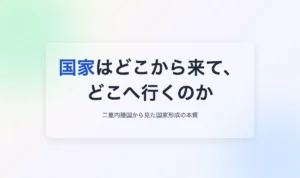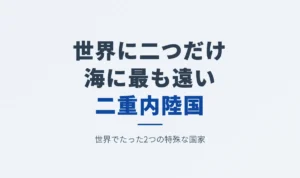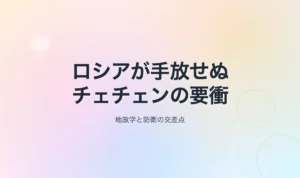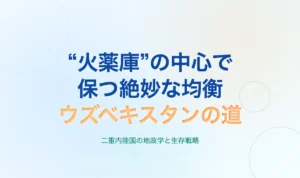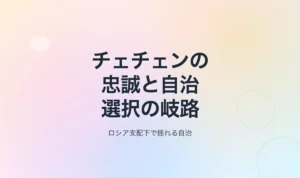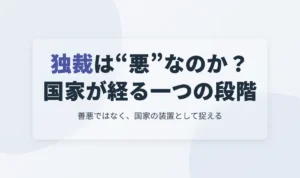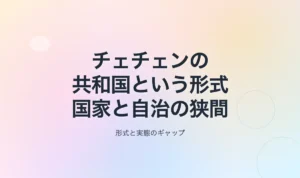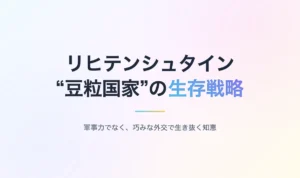国家としての要件とチェチェンの実態
国家とは何か――この問いに明確な答えを与えるのは難しい。しかし国際関係においては、一定の基準が存在する。1933年のモンテビデオ条約では、国家の要件として①恒常的な住民、②明確な領域、③政府、④他国との関係を結ぶ能力、の4点が示されている。
チェチェン共和国は、これらの一部を形式上は満たしている。住民と領土、そして行政機構は存在し、「共和国」という政府体制も整備されている。しかし、国際関係を自らの意思で結ぶ能力については、ロシア連邦の一部である以上、独自の外交権は持たない。これが、国家としての承認における大きな障害となっている。
独立の宣言と承認されない現実
1991年、ソビエト連邦の崩壊とともにチェチェンは独立を宣言し、独自の通貨や軍、行政機構の設置を進めた。だが、この独立を国際的に承認した国家は一つも存在しなかった。ロシアはチェチェンの行動を「反乱」として位置づけ、内政問題として処理した。
国際社会も、ロシアの領土保全という立場を尊重し、チェチェンの国家承認には極めて慎重な態度をとった。たとえ事実上の独立が一定期間保たれていても、法的な承認がなければ国家とは認められない。
こうした現実は、国家の成立が単に事実の積み重ねではなく、国際政治の中での合意と利害調整の結果であることを示している。
比較される存在:台湾・北朝鮮・未承認国家
チェチェンのように、形式や機能はあっても国際的に承認されていない地域は他にも存在する。たとえば台湾は、独自の政府、経済、軍を持ちながらも、国連には加盟しておらず、多くの国が公式には「中国の一部」と認識している。
北朝鮮は国連加盟国ではあるが、その国家としての正当性や承認については政治的議論の対象となってきた。また、北キプロスやアブハジア、南オセチア、沿ドニエストルなどは、限られた国家のみが承認している“部分的承認国家”にあたる。
チェチェンの場合、一度も他国から国家として承認されたことがない点で、これらの例よりさらに国際的孤立度が高い。 つまり、国家の要件を満たしていても、国際社会がそれを承認しなければ“国家”とはなりえない現実がある。
国家とは自称だけでは成立しない
チェチェンの経験は、国家の存在が自己宣言だけで成立しないことを教えてくれる。名称、政府、住民、制度があったとしても、それが他国から認知され、外交関係を構築できなければ、国際社会では“存在しないも同然”とされる。
国家とは、実効支配と国際承認の両輪によって初めて形を持つ。どちらか一方が欠けていても、その存在は不完全であり、時に危ういものになる。
チェチェンは、「国家の形を持ちながら国家でない」という独特の位置にある。そこにあるのは、国家とは何か、誰がそれを決めるのかという根源的な問いである。そしてそれは、現代国際秩序のあり方そのものに対する静かな疑問でもある。