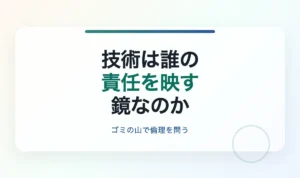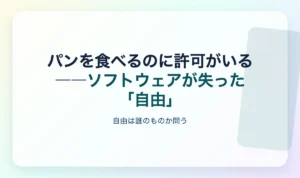3Dプリンタという言葉が、日本の技術業界を賑わせてからもう十年以上が経つ。あの頃は「未来の家庭には3Dプリンタが並び、誰もが自宅で必要な部品を作るようになる」と大真面目に語られていた。確かに、聞こえは良い。家の片隅で小型の工場が動き、失われた部品や欲しかった形状が一夜にして生まれる──まるでSF映画のようだ。しかし、現実にその光景を目にした者は少ない。筆者自身、エンジニアとして大手IT企業に在籍し、独立した今も技術に囲まれて生きているが、周囲に家庭用3Dプリンタの所有者は驚くほどいない。数十人規模ではなく、百人規模で見回しても「一人もいない」。家にオシロスコープがあるような人間が、それでも3Dプリンタは買わなかったのである。
この“空白”は偶然ではない。生活者としての現実と、技術としての理想が噛み合わなかったのだ。それは、砂漠でヨットを売ろうとしたようなものだ。どれだけ優雅で美しい船を作っても、水がなければ決して走らない。3Dプリンタは家庭における“必要という名の水”を持てなかったのである。
既製品の圧倒的強さと、家庭用プリンタの無念
筆者が初めて3Dプリンタを触ったのは、会社の工作室に設置されていた業務用の機材だった。たしかに便利ではあったが、ひとつプリントするたびに「本当にこれを家庭で使うべきか」と考えてしまった。調整に手間がかかり、ノズルは詰まり、ベッドレベリングに気を遣う。出力した部品はサポート材で埋まり、バリ取りをしてヤスリをかけ、何とか形にしたところで「これは百均で売っているものより脆い」という現実に直面する。樹脂という素材は、軽くて扱いやすい一方、熱や衝撃には弱い。家庭で本当に求められるのは、耐久性のある部品や既製品と互換性を持つ形状であることが多い。わざわざ自分で造形するより、ホームセンターへ行き、金具や樹脂パーツを買ってきて少し加工するほうが早くて確実だった。
この「売っているもののほうが強くて早くて安い」という圧倒的な事実は、3Dプリンタを家庭に根付かせる最大の障壁となった。プリンタで作れるものは、既製品がすでに埋め尽くしていたのである。必要とされる土俵に上がる前に、勝負がついていたと言ってよい。
それでも“刺さる人”には確実に刺さった領域
しかし、3Dプリンタが完全に失敗したかというと、そうではない。むしろ、一部の領域では唯一無二の存在となった。その象徴が、コスプレ、フィギュア造形、自作キーボード、ドローンやロボットといった“個人の創作性が極端に高いジャンル”である。
これらの領域には共通点がある。求められる形状が高度に個別的であることだ。コスプレの小道具はキャラクターごとに異なり、ミニチュアやフィギュアは作者の想像力の数だけ形を持つ。自作キーボードは手の大きさや姿勢に合わせて最適形状が変わり、ドローンやロボットは環境や目的に合わせて細部を変えざるを得ない。既製品が追いきれない“個の差分”がここにはある。3Dプリンタはその差分を埋めるための最後の砦、いわば「現代の指物師」として機能したのである。
特にTPU素材が普及し始めてからは、ドローンの衝撃吸収部品やカメラマウント、ロボットの足回りなど、柔軟性が求められる部分の造形が一気に進んだ。強度や耐熱ではカーボンや金属に敵わないが、カスタム性だけは市販品を凌駕する。ここに3Dプリンタの“ほんとうの居場所”が生まれた。
技術の末路は、必ずしも“普及”ではなくてよい
3Dプリンタは“一家に一台”にはならなかった。それは失敗ではなく、この技術が向かうべき場所が最初からそこではなかったというだけである。必要のない家庭に無理やり押し込むのではなく、必要としていた手に自然と収まっていった。その軌跡は、鍛冶屋が町工場に姿を変えたようなものだ。誰もが槌を握らなくても、槌を必要とする人間は着実に残る。
技術の本当の価値とは、世界を塗りつぶすことではない。必要とする者を確かに助けることである。家庭用3Dプリンタは万人の道具ではないが、“創る”ことを愛する人にとっては、かけがえのない相棒となった。砂漠で走らないヨットでも、海を求める者が乗れば確かに進む。技術とは、本来そういうものであっていい。